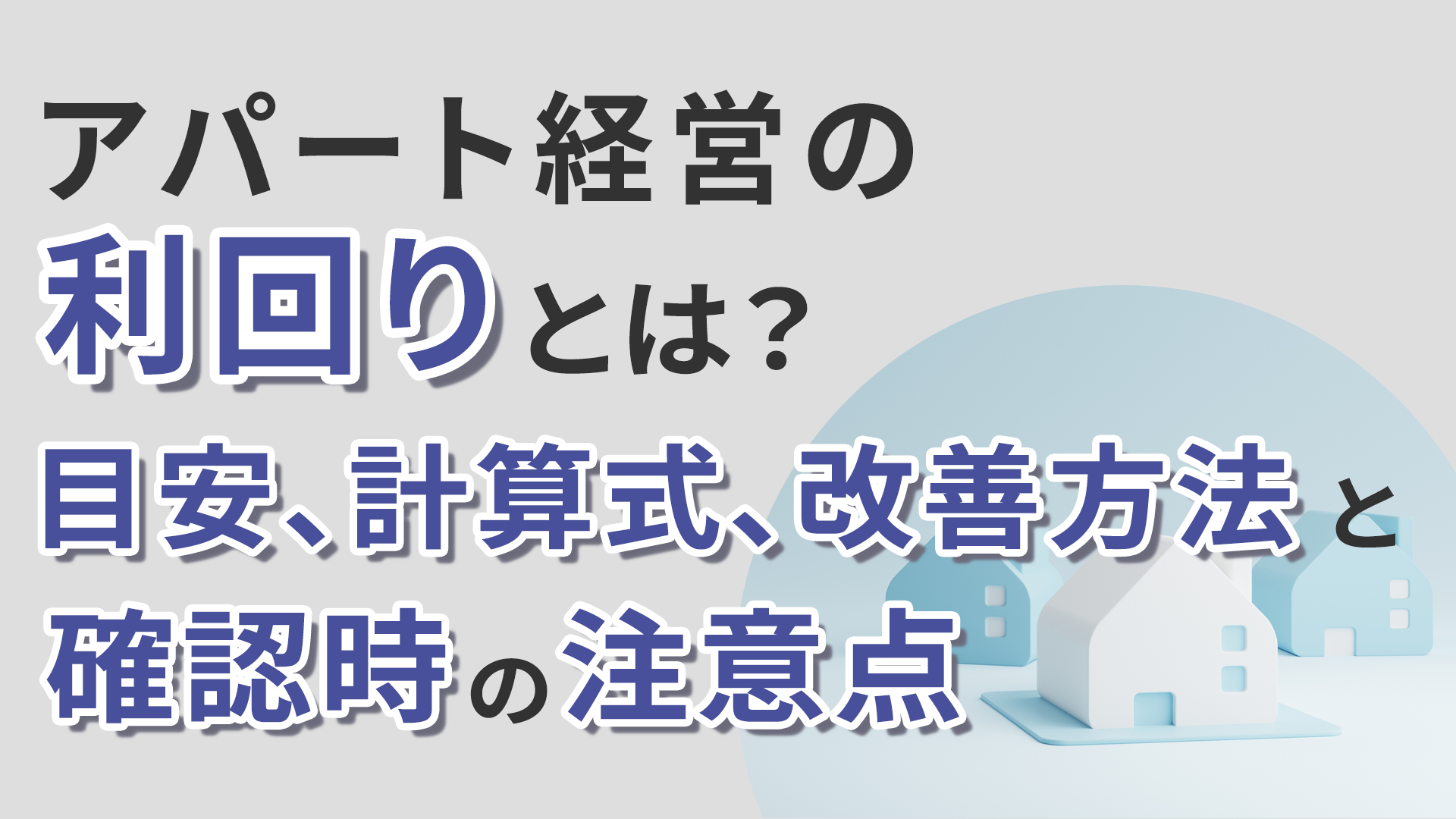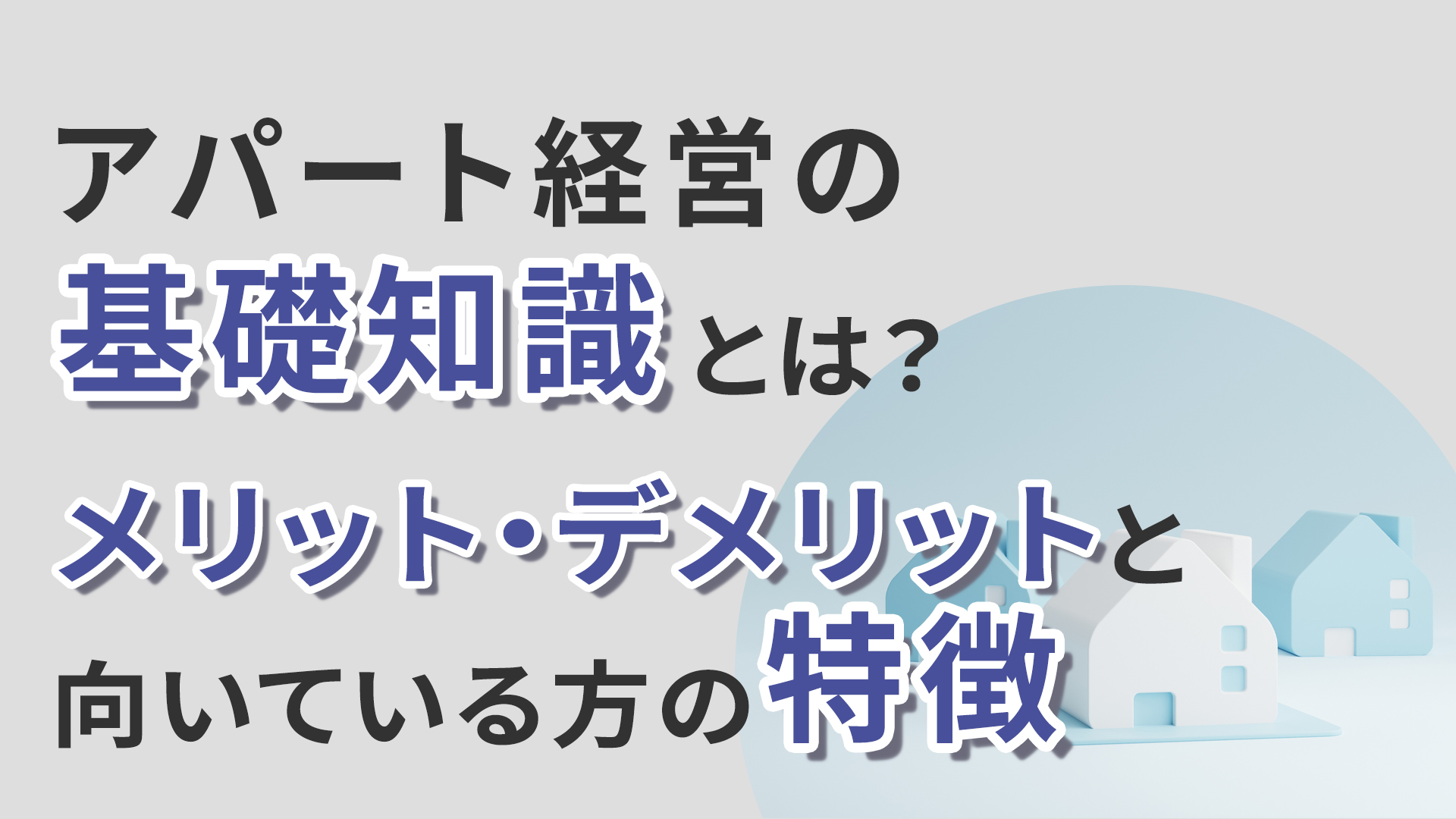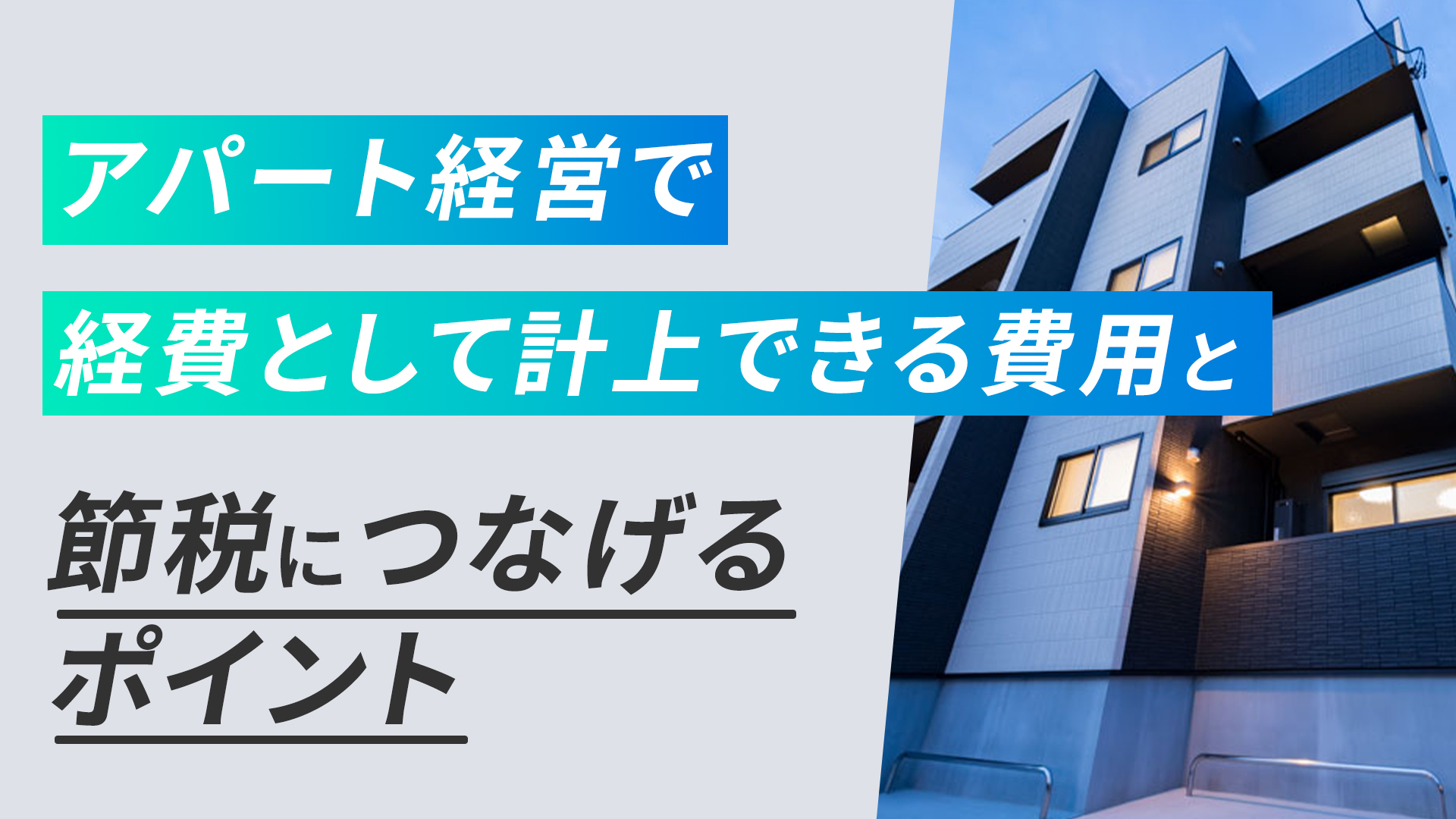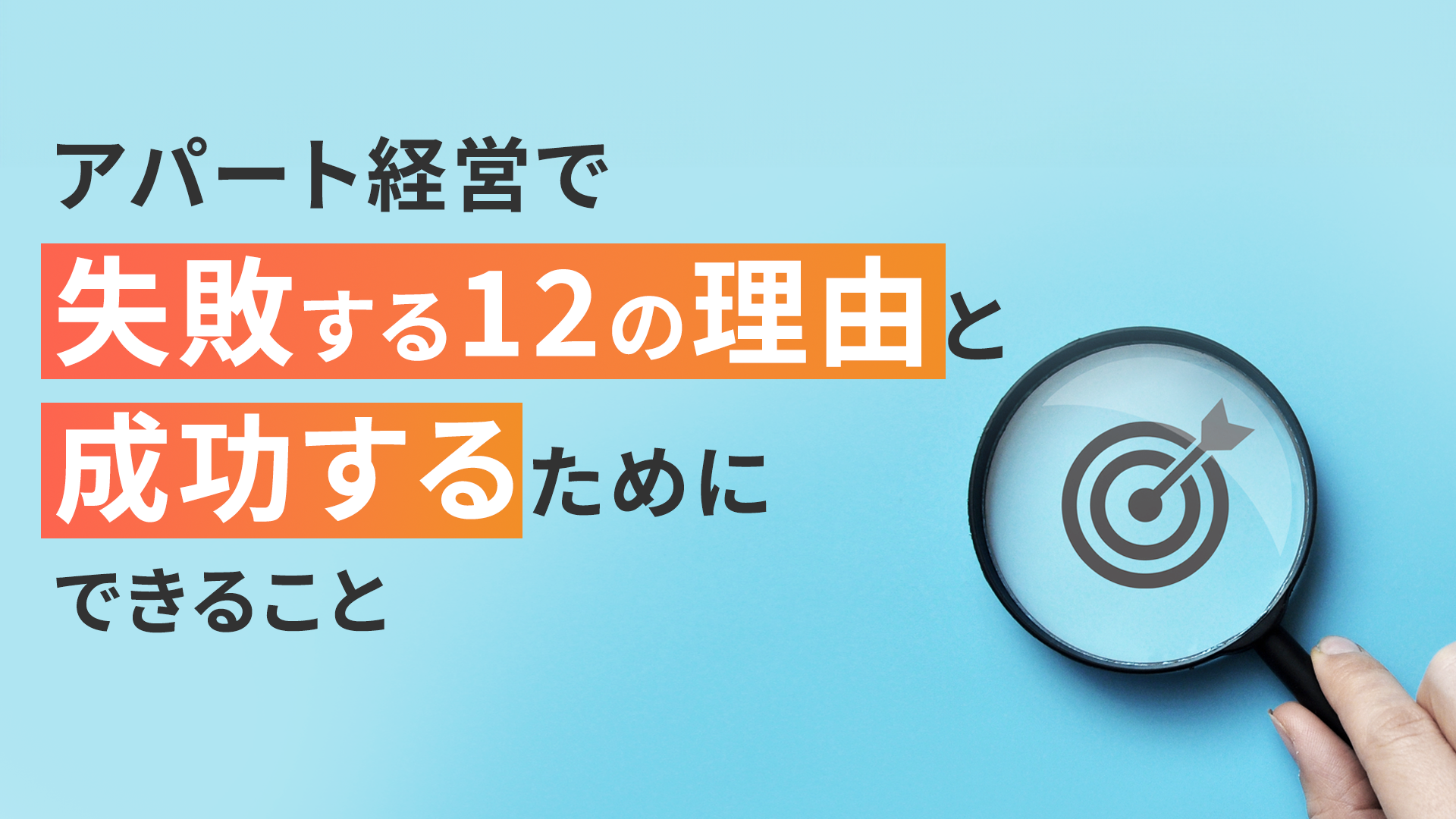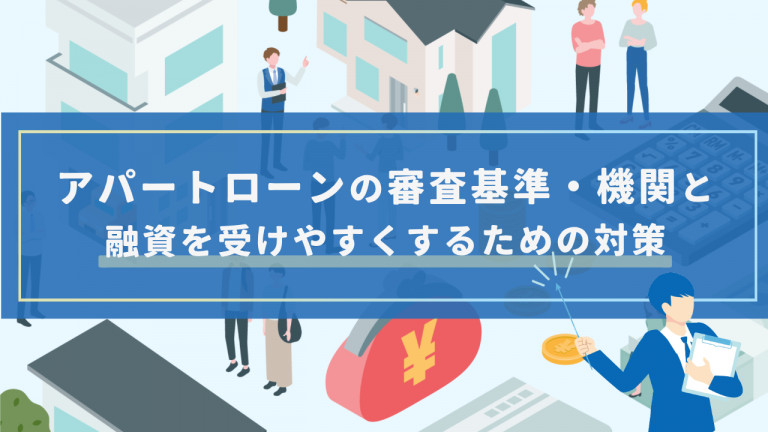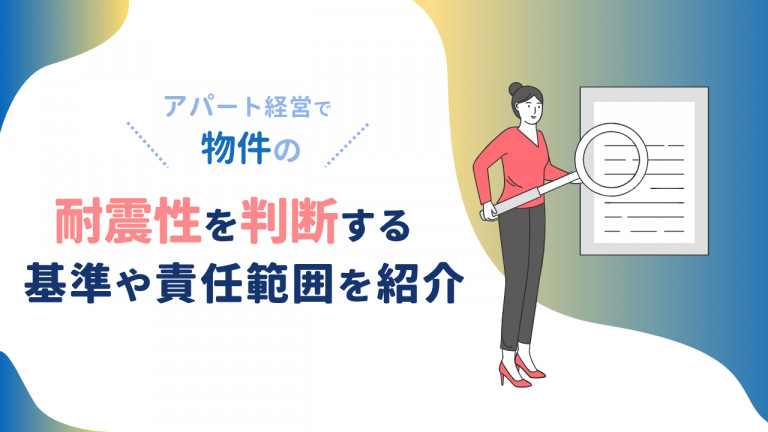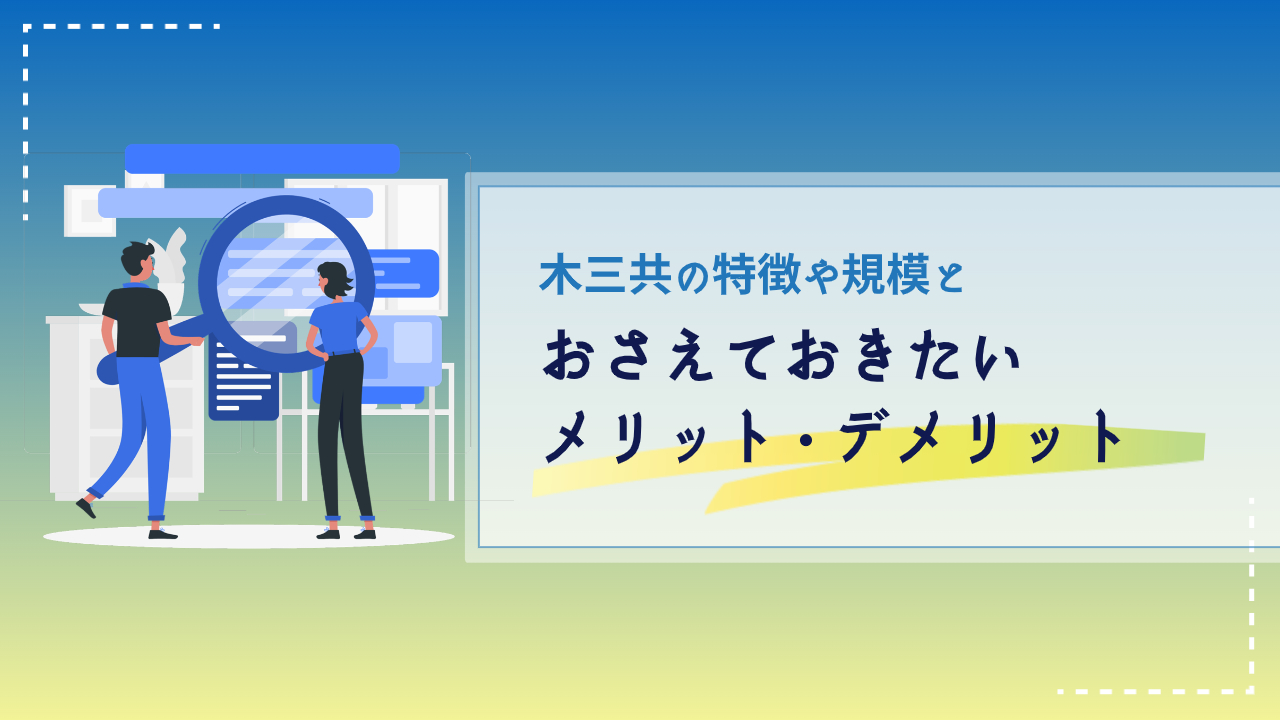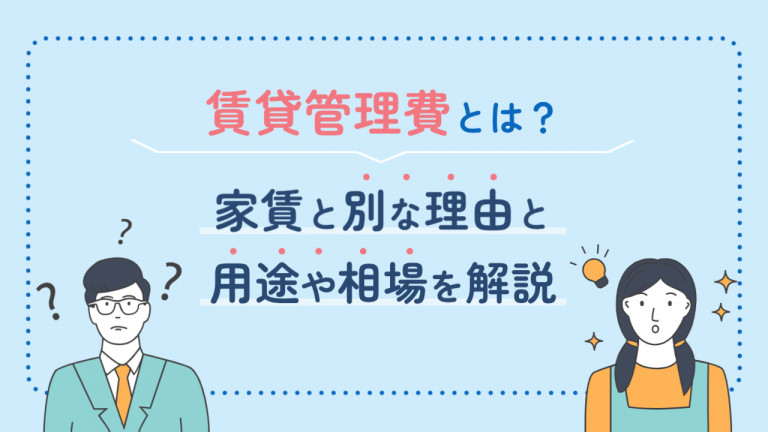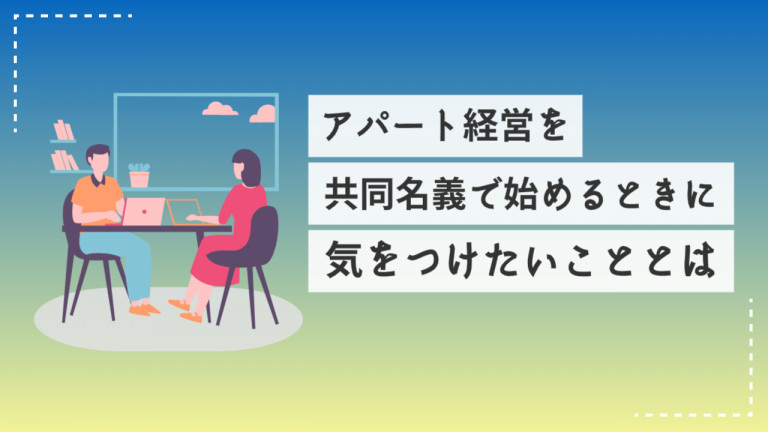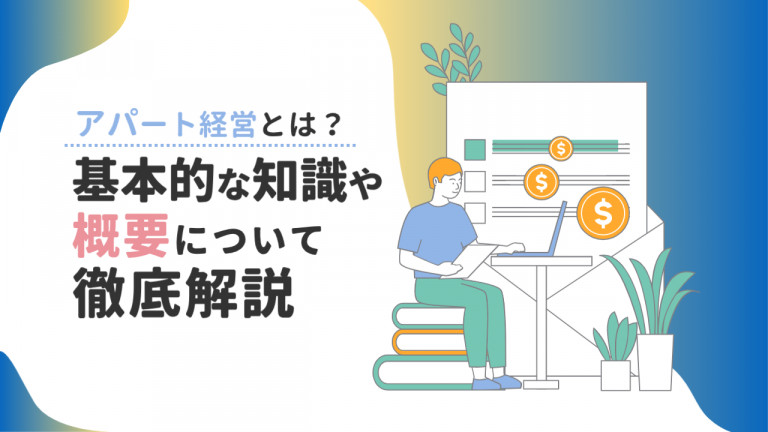
アパート経営を始めてみたいと思っていても、そもそも何から始めればよいのかわからないという方もいるでしょう。
アパート経営には投資としての考え方や、さまざまなリスクを想定した綿密な準備や計画が必要です。
そこで本記事では、アパート経営における基本的な知識や概要を解説していきます。
アパート経営を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. アパート経営とは
アパート経営とは、建売のアパートを購入する、もしくは一からアパートを建設して所有し、それを第三者に賃貸して家賃収入を得ることをいいます。
土地を所有しているものの、どう活用しようか迷っている方の選択肢として、人気のある活用方法です。
2. アパート経営の仕組み
アパート経営の仕組みには、以下2通りがあります。
・管理業者への委託
・自分で管理運営する
アパート経営では、管理運営に手間がかかるため、管理業者へ委託する方が楽に賃料を得られます。アパート経営で行う管理運営は、以下のものがあります。
・入居者の募集と確保
・建物の管理・点検・修繕
・クレームなどのトラブル対応
自分で管理運営する場合、これらの業務をすべて一人で行います。
管理業者へ委託すればすべて行ってくれるため、本業が忙しい方などは費用を払ってでも委託すると良いでしょう。
自主管理と委託管理のメリット・デメリットについては以下の記事で紹介しています。
3. アパート経営とマンション経営との違い
アパート経営とマンション経営との違いは以下のとおりです。
【アパート経営】
・基本的に1棟単位で経営する
・1棟でもマンション経営と比較すると規模は小さい
・少ない予算ではじめられる
・初心者でも取り組みやすい
【マンション経営】
・1室から経営可能
・資金に余裕があれば部屋数を増やせる
・1棟まるごと経営するには潤沢な予算が必要
・自由度が高い
アパート経営は1棟単位で経営することが基本ですが、マンションを1棟所有するより小さい規模で行えるため、初心者向けです。
まだ投資経験がない方でどちらにしようか迷っている場合は、アパート経営を選択しておくのが無難でしょう。
マンション・アパート経営と言ってもいくつもの物件タイプに分かれます。以下の記事ではタイプ別にマンション・アパート経営の違いやメリット・デメリットについて紹介しています。
4. アパート経営と他の投資との違い
アパート経営と他の投資との違いを解説します。
株式投資を例にしましょう。
株式は、その会社の業績や世間からの評価で価格が大きく変動する特徴があります。
一方アパート経営の場合、土地価格の変動は緩やかで安定しています。
株式投資は管理・運営の必要はなく、することといえば日々変動する価格のチェック程度です。
アパート経営ではさまざまな管理運営の手間が生じ、建物の管理・修繕やクレーム対応が必要です。
アパート経営の成功率について知りたい方はこちらをご覧ください。
5. アパート経営のメリット
アパート経営のメリットを以下で4つ解説します。
5.1 安定した不労所得が得られる
アパート経営は、1棟で経営することにより安定した不労所得が得られます。
複数の部屋を所有して貸し出すため、10部屋のうち1部屋が空室になっても、他の部屋からの家賃は確保され、90%に下がるだけです。
一方でマンションの1室のみを経営していると、万が一空室になると収益は0になります。
このようにアパートは1棟経営で複数の部屋を貸し出せば、安定した不労所得が得られるのです。
5.2 相続税や固定資産税の節税対策になる
アパート経営では、相続税や固定資産税の節税対策が可能です。
【相続税】
・5,000万円を現金で相続すると、5,000万円すべてに課税される
・アパート経営の場合、土地の価格が現金よりも2~3割安く評価された価格に課税される
【固定資産税】
・一定の要件を満たすと土地と建物に軽減措置を受けられる
・小規模住宅用地は課税標準の1/6、一般住宅用地は1/3になる
・新築・耐火構造の建物などによって税額が1/2になる
余っている土地があれば、アパート経営で相続税や固定資産税の節税が可能です。
以下の記事では、アパートオーナーであったら知っておきたい固定資産税の基礎知識について解説しています。
5.3 定年後の生活資金になる
物価高・公的年金の減額・受給時期の遅延などによって、これから老後をむかえる世代は金銭的不安を抱える方が多いでしょう。
アパート経営で定期的な収入があれば、生活資金に余裕が生まれます。
家賃収入で生活資金が確保できると金銭的不安が和らぎ、精神的な支えになるでしょう。
以下の記事では、労所得を得ることができるアパート経営は老後の備えとして有効な手段なのか、押さえておくべき注意点について具体的に解説していますのでご覧ください。
5.4 生命保険の代わりになる
アパート経営では、住宅ローンを組む際に加入する「団体信用生命保険」が適用される場合があります。
この保険は、借入れしている方が不慮の事故などで返済できなくなっても、保険会社が代わりに支払ってくれるものです。
万が一亡くなり家族が残されてしまっても、返済の必要がないだけでなく、家賃収入も得られるメリットがあります。
以下の記事では、アパート経営のメリットやデメリット、アパート経営に関する基礎知識を紹介しています。
6. アパート経営に向いている人の特徴
アパート経営に向いている人の特徴を以下で解説します。
・節税対策したい(相続税・固定資産税)
・土地が余っているが活用できていない
・定年後の生活資金を得たい
・本業の給料以外に収入源がほしい
・一般的な投資商品以外の資産がほしい
・経営ノウハウがあり活かしたい
・管理運営を委託して不労所得を得たい
先述したアパート経営のメリットを活かせる方にはピッタリといえるでしょう。
以下の記事では、アパート経営を考えている人向けに職業ごとのメリットやデメリットなど解説していますのでご覧ください。
7. アパート経営で見込める年収
アパート経営で見込める年収について解説します。
年収は「賃料×部屋数×12ヵ月」で算出した金額に、共益費・礼金・更新料などの収入を合算したものとなります。
たとえば賃料8万円で6部屋を経営していれば、「8万円×6部屋×12ヵ月=576万円」となり、共益費・礼金・更新料などを合算したものが年収になるという考え方です。
注意点として、実際に手元に残る金額は年収から各種税金・ローン返済額・維持費・修繕費などの支出を引いた金額になることです。
また、家賃は入居者がいなければ発生しません。そのため、空室があればその分家賃は減ってしまうことにも注意しましょう。
8. アパート経営の利回り
アパート経営には以下3種類の利回りがあります。
8.1 表面利回り
「年間賃料収入÷投資額」で計算します。
表面利回りは目安と考えましょう。というのも、実際の利益は実質利回りを参考にするからです。
表面利回りは、固定資産税や維持・管理費などの支出が考慮されず、高い数値が算出されます。あくまでおおまかな収益です。
また、不動産情報サイトや広告に記載されている利回りは、表面利回りのことがあります。実際よりも高く見積もられている点に注意しましょう。
8.2 実質利回り
「(年間賃料収入-年間経費)÷投資額(購入時の諸費用も含む)」で計算します。
年間経費とは以下のものをいいます。
・固定資産税・都市計画税
・損害保険料
・委託管理費用
・修繕費
・入居者の募集に関する費用
購入時の諸費用は以下のとおりです。
・不動産会社仲介手数料
・司法書士への報酬
・登記の印紙代
・不動産取得税
上記の年間経費と諸費用を加味して算出するため、実際の利回りに近い値がわかります。しかし、空室率は加味されていません。空室が多くなった場合、算出した値よりも小さくなることに注意しましょう。
8.3 想定利回り
「年間賃料収入÷投資額」
想定利回りの計算方法は、表面利回りと同じです。異なるのは、満室を想定していること。
つまり、経営するアパートの年間賃料収入が最大であることを前提に算出しているため、実際はこの数値以下になることに注意しましょう。
詳しい利回りの種類や目安、最低ラインなど利回りに関しては以下の記事で紹介しています。
9. アパート経営の収益の種類
アパート経営における収益4種類を解説します。
9.1 家賃
収入の多くを占めています。部屋を貸していれば毎月発生するため、空室にならないよう入居者を確保することが大切です。
仮に家賃8万円で5部屋貸していれば「8万円×5部屋=40万円」が毎月の家賃収入となります。
家賃と似た言葉に「賃料」がありますが、厳密には異なるものです。賃料は部屋を借りるための料金のみを示していますが、家賃は共益費なども含まれているものをいいます。
9.2 共益費
共益費は賃料の5~10%ほどの料金で、毎月発生するものです。
アパートの共用施設や駐車場における維持・管理費用にあてられます。
物件によっては「管理費」と示されていることもあります。
両者の違いは以下のとおりです。
・共益費:共用部分の維持・管理費用
・管理費:共用部分を含むアパート全体の維持・管理費用
9.3 礼金
礼金は入居者がオーナーに支払う謝礼金のようなものです。金額は物件によってさまざまですが、賃料の1~2ヵ月分程度が相場になっています。
毎月発生するわけではありませんが、入居時に一度支払ってもらえれば返金する必要はなく、支払われた分が収入となります。
しかし最近では礼金なし物件も増えているため、近隣のアパート経営者が礼金をどう設定しているか調査しておくとよいでしょう。
9.4 契約更新料
アパートには通常、契約期間が定められ、期間終了後に継続して住みたい場合は契約を更新します。
その際に必要なものが契約更新料です。礼金と同様、賃料の1~2ヵ月分程度が相場です。
契約更新料が発生するのは「普通貸家契約」のみです。
契約期間終了後に退去が必要な「定期貸家契約」では発生しないため、収入にならない点には注意しましょう。
以下の記事では、共益費のこと、管理費との違い、また、家賃とは分けて表示することのメリット・デメリット、
さらには、共益費勘定科目や仕訳のことまで詳しくお伝えします。
10. アパート経営でかかる税金と確定申告の方法
アパート経営で得た収入にかかる課税方法や、経営そのものを通してかかる税金、確定申告の時期と方法について解説していきます。
10.1 家賃収入の課税方法
家賃収入は不動産所得に分類され、各種控除後に税率をかけて所得税を算出します。
以下で家賃収入の課税方法について順に解説していきます。
1. 不動産所得を算出:家賃収入-必要経費=不動産所得
2. 課税不動産所得を算出:不動産所得-所得控除=課税不動産所得
3. 所得税額を算出:課税不動産所得×税率=所得税額
4. 最終的に納付する所得税額を算出:所得税額-税額控除=納付する所得税額
なお、不動産所得を算出する時点で赤字の場合、損益通算が可能です。これは不動産所得以外の所得から、マイナスになった分を控除できるというもの。
結果的に所得税を減額できるため、税負担が軽くなります。
10.2 アパート経営でかかる税金
アパート経営でかかる税金には以下のものがあります。
・購入時:不動産取得税、登録免許税、印紙税
・保有時:固定資産税・都市計画税、所得税・住民税(家賃収入に対して)
・売却時:所得税・住民税(不動産の譲渡に対して)
税金を計算に入れずアパートを経営していると、思っていた以上に支出が大きくなり、収支計画にズレが生じてしまいます。
税金の支払いによってほとんど手残りがないといった状況にならないよう、アパート経営に関するものは把握しておきましょう。
10.3 確定申告の時期と方法
確定申告とは、所得にかかる所得税などの税金の額を計算し、納付するために行う手続きのことをいいます。家賃収入がある場合は確定申告が必要です。
時期は2月16日~3月15日で、前年分の所得が対象となります。
確定申告の方法は以下のとおりです。
1. 必要書類を用意する(源泉徴収票や支払調書)
2. 確定申告書を作成する
3. 税務署に確定申告書を提出する
4. 税金を納付する
なお、青色申告で行う場合は事前の申請が必要です。
申請には期限があり、開業してから2ヵ月以内、もしくは青色申告に変更する年の3月15日までとなっています。
特に届出しなければ白色申告になりますが、青色申告は節税できるメリットが多くあるためおすすめです。
また、以下の記事では副業としてアパート経営をされてる方への注意点と、不動産投資の税務調査について詳しく解説しております。ぜひあわせてご覧ください。
11. アパート経営で必要な資金
アパート経営で必要な資金について解説します。
11.1 建築費用
アパートの建築費用です。費用は構造によって目安となる坪単価が異なり、以下のとおりです。
・木造:77~100万円
・鉄骨造:80~120万円
・鉄筋コンクリート造:90~120万円
例として、鉄骨造で一部屋7坪のワンルームを6部屋で建築する場合、建築費用は以下のようになります。
「80~120万円×7坪×6部屋=約3,360~5,040万円」
以上はワンルームを想定していますが、規模(戸数・階数・間取り)や設備が変われば費用は大きくなります。
11.2 建築費以外にかかる費用
アパート建築費以外にかかる費用には、以下のものがあります。
・アパートローン関連費:建設費の10%程度(事務手数料・保証料・印紙代)
・登記費用:所有権保存登記・抵当権設定登記で20~50万円
・不動産取得税:アパートの固定資産税評価額×3%(2024年3月31日まで)
・火災保険費用:一般的に10年一括払い、地震保険5年つきで30~50万円
不動産取得税に関する固定資産税評価額とは、時価の70%程度です。
つまり、4,000万円のアパートであれば約2,800万円になります。
よって不動産取得税は「4,000万円×3%=120万円」と算出されます。
以下記事では、アパート経営に必要な初期費用や維持費などを詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
12. アパートの維持費・修繕費
維持費・修繕費は、初期費用とは別にかかる費用です。
以下3種類について解説します。
12.1 設備の維持・管理費
アパート経営において設備の維持や管理にかかる費用です。
・共用部分の水道光熱費
・清掃費用
・必要備品の費用
・入居者賃料の収受および督促
・クレーム対応
といった、さまざまな業務に費用が発生します。
もし管理会社へ委託する場合は業務委託費用も発生するため、さらに費用が大きくなります。
12.2 室内の修繕費
年数が経てばさまざまな部分に劣化や老朽化が生じます。そのため適宜修繕するための費用がかかります。
修繕費は以下のとおりです。
・原状回復費用:入居者の退去後、部屋を入居時と同じ状態に戻すための費用
・補修:入居中に生じた設備の修繕にかかる費用
・予防修繕:大きな修繕の予防にかかる費用
原状回復費用は敷金から充当する場合が多く、約20万円以下です。
補修費用は、水回りや機械類などの設備を補修する際にかかります。雨漏りや事故・災害による破損など、規模の大きい修繕に必要なこともあり、数万~数十万円かかります。
予防修繕は、大規模な修繕となる前の予防として行うものです。
・破損・故障の可能性がある部分に予防的に行う際の費用
・シロアリ予防のためにする検査・薬剤の散布、壁・屋根の検査費用
・退去後の模様替えや一部リフォーム
主に上記の内容が予防修繕の一環となります。費用は数万~数十万円程度です。
12.3 大規模修繕費
アパート経営においてもっとも負担の大きい修繕費です。工事内容の規模が大きく、期間が長期的になりますが、物件の資産価値を維持するために不可欠です。
大規模修繕にかかる費用は以下のものがあります。
・屋根の塗装
・屋根の葺き替え(屋根材の交換)
・外壁の塗装
・タイル張り替え・交換
・耐震性能補強工事
費用は約数百万~1千万円かかります。
13. アパート経営のリスクと対応策
アパート経営を成功させるためには、リスクと対応策を知っておくことが大切です。
以下で順番に解説していきます。
13.1 空室
アパート経営における収益は、入居者による家賃収入です。
そのため、空室が発生するとその分、家賃収入が減ってしまいます。
空室を避けたり、空室になってもすぐに入居者を確保したりすることが、空室リスクへの対応策といえます。
具体的には以下のように対策しましょう。
・間取り・設備・家賃などを地域のニーズに合わせる
・維持・管理をこまめに行い、入居者が使い勝手よく感じられるようにする
・サブリース(一括借り上げ)を利用する
・空室がいつ起きてもいいように家賃収入から一定割合を蓄えておく
・周囲の競合物件と差別化を図る
13.2 家賃滞納
空室リスクと同様に、入居者の家賃滞納も大きなリスクとなります。
やっかいなのは、家賃が払われないにもかかわらず、入居はしているということ。
空室なら次の入居者を探せばよいのですが、滞納ではそれもかないません。
そのため、家賃を滞納しないため事前の対策や、滞納があった場合の対策もしておきましょう。
具体的には以下のとおりです。
・入居審査で良心的かどうか見極める
・家賃保証サービス(家賃立て替え、滞納者への連絡・交渉など)を利用する
・2ヵ月分ほどの敷金を確保する(3ヵ月以上連続で滞納しないと退去させられないため)
13.3 建物の老朽化
建物の老朽化は避けられません。
たとえば外壁、給排水管、屋根、フローリング、エレベーターなど、経年劣化は必ず起きてしまうもの。
とはいえ、老朽化した状態で放っておけば入居者を集めることは難しく、空室リスクにつながってしまいます。
対策としては、修繕費がかかる想定で事業計画を立てるのが重要です。
特に大規模修繕費は、数百万~1千万円かかることもあるため、数十年後を見据えてコツコツと修繕費用を蓄えておく必要があります。
また、フローリングやエアコンなどの比較的小さな修繕も必要になるため、計画的に管理・修繕しておくことが大切です。
投資物件として選ぶとき、新築と中古、それぞれにどのようなメリットとデメリットがあるのかを以下で紹介しています。
13.4 入居者トラブル
アパート経営していると、入居者によるトラブルはつきものです。
たとえば以下のようなものがあります。
・早朝や深夜の騒音
・共用スペースでの喫煙
・ゴミを分別しない
・無断でペットを飼う
・上の階からの水漏れ
これらのトラブルをきっかけに、オーナーへクレームが入ったり、入居者同士のトラブルに発展したりするリスクがあります。
オーナーへのクレームは迅速に対応すれば解決できる場合もあるかもしれません。
しかし入居者同士のトラブルは、さらに他の入居者にも迷惑がかかりますし、最悪の場合退去されてしまうリスクもあります。
入居者トラブルを防ぐためには入居前の審査をしっかり行い、良心的な方に入居してもらいましょう。管理会社によって審査の対応が異なるため、実績が豊富な会社に委託することをおすすめします。
13.5 災害
災害は予測がむずかしく、建物の倒壊や消失のリスクをゼロにすることはできません。
とはいえ、災害によって命の危険にさらされるのは入居者です。
火災保険・地震保険に加入していれば建物に対する金銭面での不安はある程度解決できますが、入居者に及ぶ被害を最小限におさえることはできません。
そのため、具体的には以下のような対策をとっておきましょう。
・耐震性・防火性の高い物件を選ぶ
・経験豊富な管理会社に委託(突発的な自然災害に対応できる担当がいること)
13.6 立地リスク
立地リスクとは、大学や会社など特定の場所に通う方が多く入居していたのに、それらが移転したりなくなったりして、アパートの需要がなくなってしまうことです。
立地リスクを避けるためには以下のような対策をとりましょう。
・多様な属性の方をターゲットにする
・アパートの需要が高い立地かどうか事前に調査する
13.7 金利上昇
アパート経営をローンで行う場合、変動金利で組んでいると金利上昇によって返済額が大きく上がることも考えられます。
返済額が大きいにもかかわらず、ほとんどが金利の返済になり、元金が減らないということになりかねません。
そのため対策としては、以下のようなものが考えられます。
・返済期間を短く設定する
・繰り上げ返済する
・固定金利にする
・日頃から金利動向を確認する
・自己資金を増やし借入金額を減らす
13.8 同エリアの市場家賃の下落
経営するアパートのエリアに何らかの理由で需要がなくなることがあります。
その際に近隣の競合が家賃を下げれば、こちらも同様に対応しなければ入居者が確保できなくなるかもしれません。
しかし、家賃を下げれば収入も減ってしまうため、競合が設定する家賃を参考にするのが無難です。
また、需要がなくなってきた状況でも、入居してもらえる魅力的な策を打ち出すことも大切です。競合のアパートにない最新の設備を導入するなど対策しましょう。
13.9 サブリース契約のリスク
サブリース契約とは、サブリース業者と物件のオーナーが賃貸借契約を結び、業者が物件を借り上げてオーナーに家賃を払う仕組みのことです。
オーナーは入居者の有無にかかわらず家賃をもらえるため、メリットしかないように思えます。
しかし、サブリース契約に多くあるのは数年ごとの賃料改定です。定期的に家賃が下落することで、経営が赤字になる可能性があります。
サブリース契約におけるリスクを回避するためには以下の点に注意しましょう。
・契約書で賃料改定の有無を確認する
・家賃が下落しても収支が赤字にならないか確認する
・サブリース業者が実績と信頼のある会社か確認する
13.10 借入が多額になるときがある
アパート経営は、土地を活用した投資商品の中でも初期投資に多くの資金が必要なため、借り入れが多額になるときがあります。
ところが、返済能力を超えて借り入れたうえ空室になってしまうと、アパート経営が立ちいかなくなってしまう可能性があります。
対策としては以下のとおりです。
・空室にならないよう入居者を確保する
・自己資金の割合を増やす(借入をできるだけ減らす)
・開始前に詳細なキャッシュフローを計算する
以下の記事では、アパート経営におけるリスクとその回避策を解説しています。
14. アパートローンの申請方法と融資限度
アパートローンとは、アパートを投資用に購入したり建築したりする際に使えるローンのことをいいます。
初期投資に数千万円が必要になるケースが多いため、自己資金が限られている場合はローンを検討するとよいでしょう。
以下で申請方法と融資限度について解説します。
【申請方法】
アパートローンの申請は以下の流れで行います。
1. 融資の相談
2. 申し込み
3. 事前審査
4. 本審査
5. 融資の決定
6. 契約
7. 融資の実行
審査には約1ヵ月かかります。
また、申請には多くの書類が必要です。金融機関により多少異なりますが、主に以下のものが必要となります。
・所得を証明するもの(源泉徴収票・確定申告書・給与証明書など)
・返済予定表(すべての借り入れ)
・物件概要書
・重要事項説明書
・レントロール(不動産賃貸借条件の一覧表)
・本人確認書類(身分証明書・健康保険証・住民票など)
・売買契約書
・登記簿謄本
・公図
・建築確認済証
・職務経歴書
・金融資産がわかる書類
・納税証明書
・団体信用生命保険申込兼告知書
・実印・印鑑登録証明書
【融資限度】
アパートローンの融資限度は受ける方の個人属性(年収、職業、他のローンの借り入れ状況など)によって異なるため、一概にいくらまでとは断定しにくいものです。
目安としては年収の7~10倍程度ですので、年収500万円であれば3,500~5,000万円となります。
注意点として、融資はいくらまで受けられるかではなく、「いくらまでなら返済できるか」で決めましょう。
以下の記事では、年収別におすすめの不動産投資法や融資などについて解説しています。
15. アパート経営を成功させる方法
アパート経営を成功させる方法5つを以下で解説します。
15.1 アパート経営に必要な知識を身に付ける
まずはアパート経営に必要な知識を身に付けましょう。
主には以下のものです。
・不動産取引に関する知識:物件の見極め、メンテナンス、保険、キャッシュフローなど
・税金の知識:発生する税金の種類や時期、確定申告に関する知識など
専門的なことは資格をもっている方に相談すればよいものの、基礎的な知識がなければ何を相談すればよいのか判断できません。
トラブルが起きた際に迅速に対応できるため、上記の知識は身に付けておきましょう。
管理会社や不動産会社も活用し、相談しながらご自身でも知識を身に付けていくのが理想です。
15.2 目的や目標を明確にする
「何のためにアパート経営するのか」「家賃でどれくらい収入を得たいのか」といった、目的や目標を明確にしましょう。
どの投資やビジネスにも言えることですが、目的や目標が明確になっていないと運用スタイルが決まらないからです。
たとえば節税対策で行うのなら「固定資産税や相続税を減額するために土地を活用する」という明確な目的がわかります。
生活資金を得たいのであれば「月に〇〇万円の家賃収入を目指す」といった具体的な数値で目標が立てられるでしょう。
目的や目標を明確にし、それにあわせて経営することが大切です。
15.3 入居者のターゲットを決める
入居者のターゲットにあっていないアパートでは、空室リスクが高くなります。
たとえば、学生が多い地域では間取り数が多い部屋よりも、ワンルームで賃料の安い方に需要があると考えられます。
一方ファミリーの多い地域では、間取りの数やキッチン・バスなどに最新の設備がついている方が好まれるでしょう。
近隣のアパートをリサーチし、適切なターゲットを決めましょう。先に物件を確保するのではなく、ターゲットを決めてから物件や資金の計画を立てることに注意しましょう。
15.4 資金計画を立てる
資金計画を誤ると、空室が出たとたんに大赤字になることも考えられます。
ターゲットが決まったら、それに応じた物件の間取りや設備を考え、必要な資金を計算していきましょう。
建築費用(購入費用)、手続きに関する諸費用、税金、維持費・修繕費などから経営コストを割り出します。
ここまでできたら、賃料を設定していきましょう。
周辺の競合と比較し、入居者が確保できる賃料かどうか検討しながら、初期費用を何年で回収できるかバランスを決めます。
予期せぬ出費も考慮し、資金計画は余裕ある設定にしましょう。
15.5 リスクに備える
想定されるリスクを事前に認識しておくことが大切です。
多くは空室リスクにつながる種々のリスク、建物や入居者が被害を受ける災害リスク、キャッシュフローを誤ったことによる赤字リスクなどにより、経営が立ちいかなくなります。
リスクは常につきまとっていることを認識し、有事の際すぐ対処できるよう備えておきましょう。
その他にもアパート経営におけるリスクとその回避策を以下の記事で解説していますのご覧ください。
以下の記事では、ほかの投資との成功率の比較や、アパート経営を成功させるための方法についてもお伝えしています。
16. アパート経営を始める際に決めるべきこと
アパート経営を始める際に決めるべきこと3つを解説します。
16.1 入居者の募集内容
入居・退去に関する基本的な取り決めや禁止事項、修繕に関することなどを決めておきましょう。
契約期間と更新や手続きの方法
多くのアパートは契約期間を2年としており、契約期間が過ぎれば更新の手続きが必要になります。その際の手続きの方法を設定したり、更新しない場合の流れを契約書に記載したりといった対応をしておきましょう。
たとえば普通借家契約では、オーナーと入居者双方で手続きがなくても自動更新になる仕組みになっています。
入居者に解約の意思があっても、規定の期日までに解約を申し出ないと、更新料がかかってしまいます。そのため、解約に関する内容も契約書にしっかり記載しましょう。
禁止事項
禁止事項は、入居者がアパートに健全に住むために必要なものです。
入居しているからといって何をしてもいいわけではないため、詳細に決めておきましょう。
たとえばペットの飼育や楽器使用の可否などは、騒音によって入居者同士のトラブルに発展しかねません。
トラブルを未然に防ぐためにも、事前に禁止事項を定め、入居者の理解を得るようにしましょう。
さらに禁止事項に抵触した場合の対応についても明記すると、抑止効果を発揮できます。
修繕費用の負担者
破損や修繕が必要になった際、負担者がオーナーなのか借主なのか、あらかじめ決めておくとトラブルを回避しやすくなります。
ケースバイケースではありますが、おおまかには取り決めておいた方がよいため、仲介業者や管理業者に確認しながらすすめましょう。
16.2 メンテナンスをどうするか
アパート経営におけるメンテナンスには、以下のような業務があります。
・消火器・火災報知機の点検
・破損部分の確認・修繕
・ごみ捨て場の状況確認
・アパートと周辺の清掃
・エレベーター点検
さまざまな管理が必要になるため、わずらわしいと感じる方は少なくないでしょう。
そこで、メンテナンスを管理会社に委託することも検討してください。
管理する手間を考えると、賃料の数%を管理会社に支払う方が費用対効果は高いといえます。
以下の記事では、アパート経営を検討している方のために、ゴミ置き場の管理の重要性をお伝えします。
資金計画の確認と再検討
資金計画を立てることは重要ですが、その通りに経営できるとは限りません。
はじめに立てた計画と実際のものに、ズレが生じることは大いにあります。
その際、どこに、どのようにズレが生じているかを確認し、対応していくことが重要です。
必要に応じて資金計画を再検討し、柔軟に対応していく姿勢が求められます。
キャッシュフローを常に意識し、余裕のある資金計画にしていきましょう。
17. アパート経営をする時の不動産投資会社の選び方
不動産投資会社もいろいろあるため、どの会社を選べばよいのかわからない方もいるでしょう。
そこで不動産投資会社の選び方を以下に示しましたので、参考にしてください。
・客付け力が高い:入居者募集するとすぐに契約できる
・管理委託費が適正な金額である:賃料収入の3~5%が目安
・担当者の対応がよい:人柄のよさやレスポンスの早さなど
・社内で情報を共有できている:担当者不在でも対応が行き届いているか
・業務内容が幅広い:基本的な内容に加え、対応してもらいたい業務があるかどうか
以上を参考にしつつ、大手か地域密着型いずれかの不動産投資会社を選びましょう。
大手はネームバリューがあるため客付け力が高い反面、担当部署が分かれており迅速な対応がむずかしい場合があります。
地域密着型では地域情勢に精通してニーズを把握しやすいものの、取り扱いエリアが少なく地域が限られてしまいます。
それぞれのメリット・デメリットを把握し、ご自身のニーズにあった会社を選びましょう。
18. アパート経営には全般的な知識の習得が必要
本記事ではアパート経営における基本的な知識や概要を解説しました。
投資としての考え方がある一方で経営の側面も大きく、さまざまな知識を習得したうえで、綿密な準備と計画が必要になります。
収入を左右する空室リスクをはじめとしたさまざまなリスクを想定し、長期的な資金計画を立てていく必要性も高いことを知っておきましょう。
株式会社マリモでは、耐震性に優れる投資用アパートを多数ご用意しております。
アパート経営を成功させたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
弊社の木造アパート経営の情報はこちらからご確認ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要