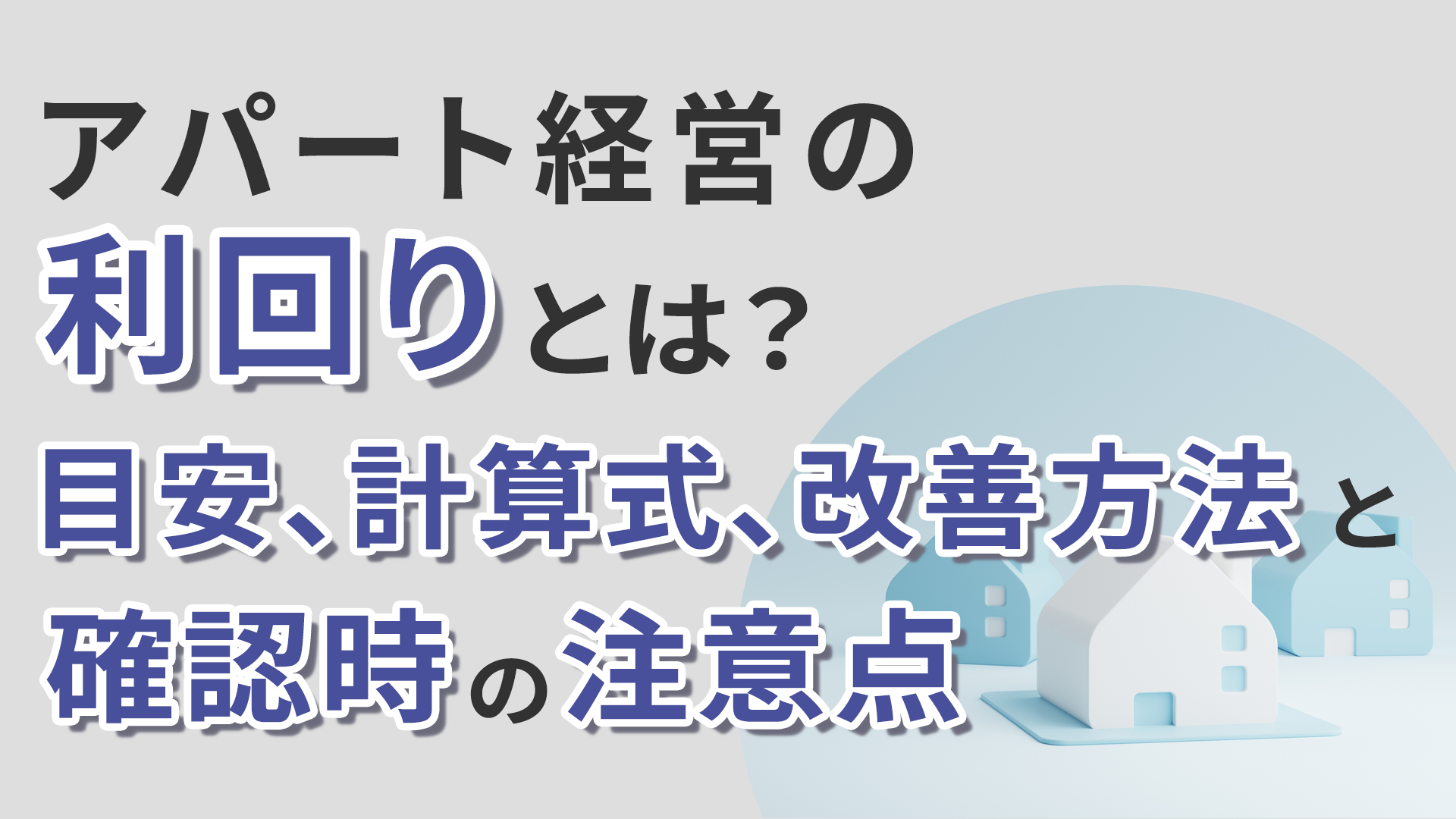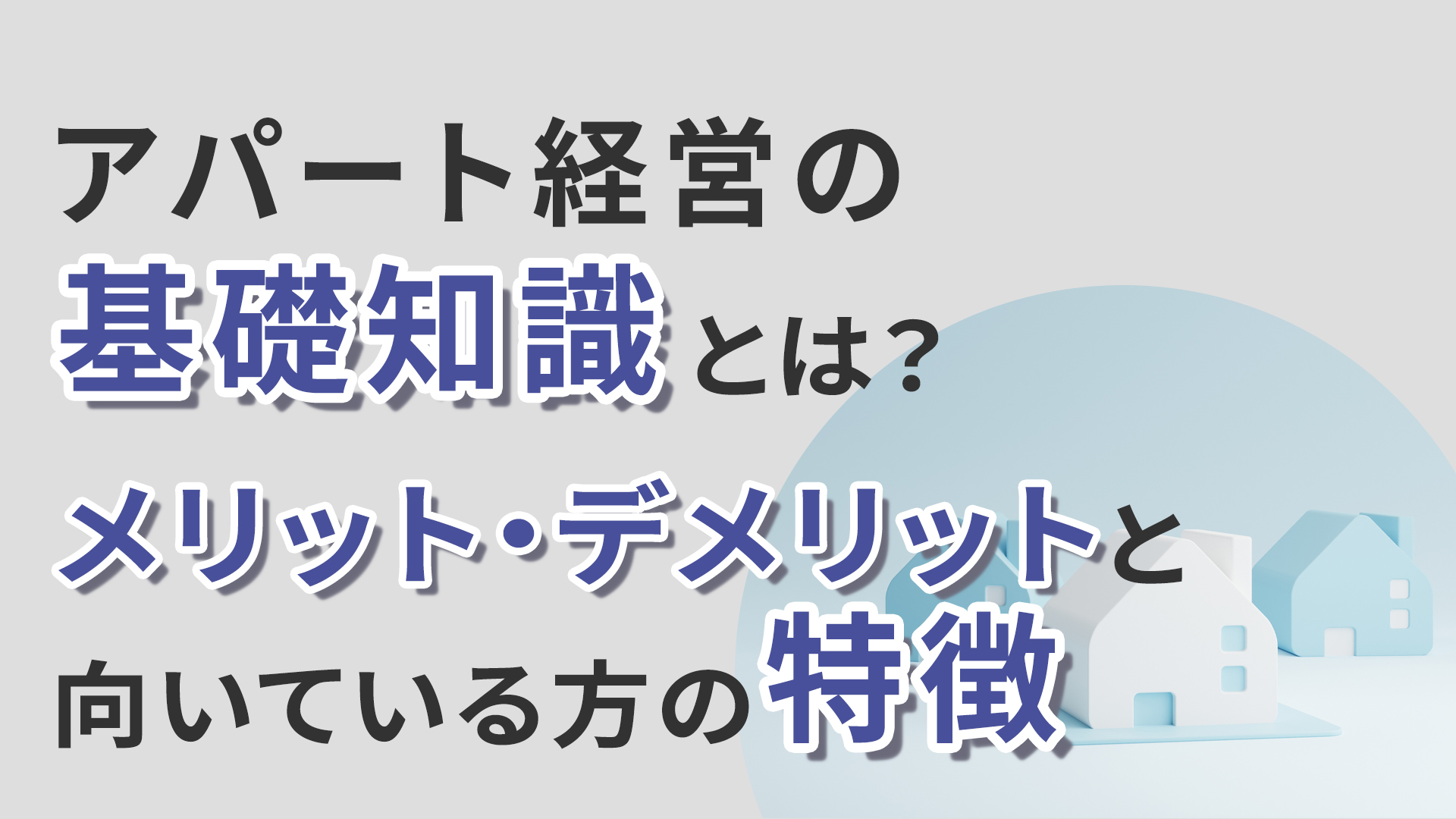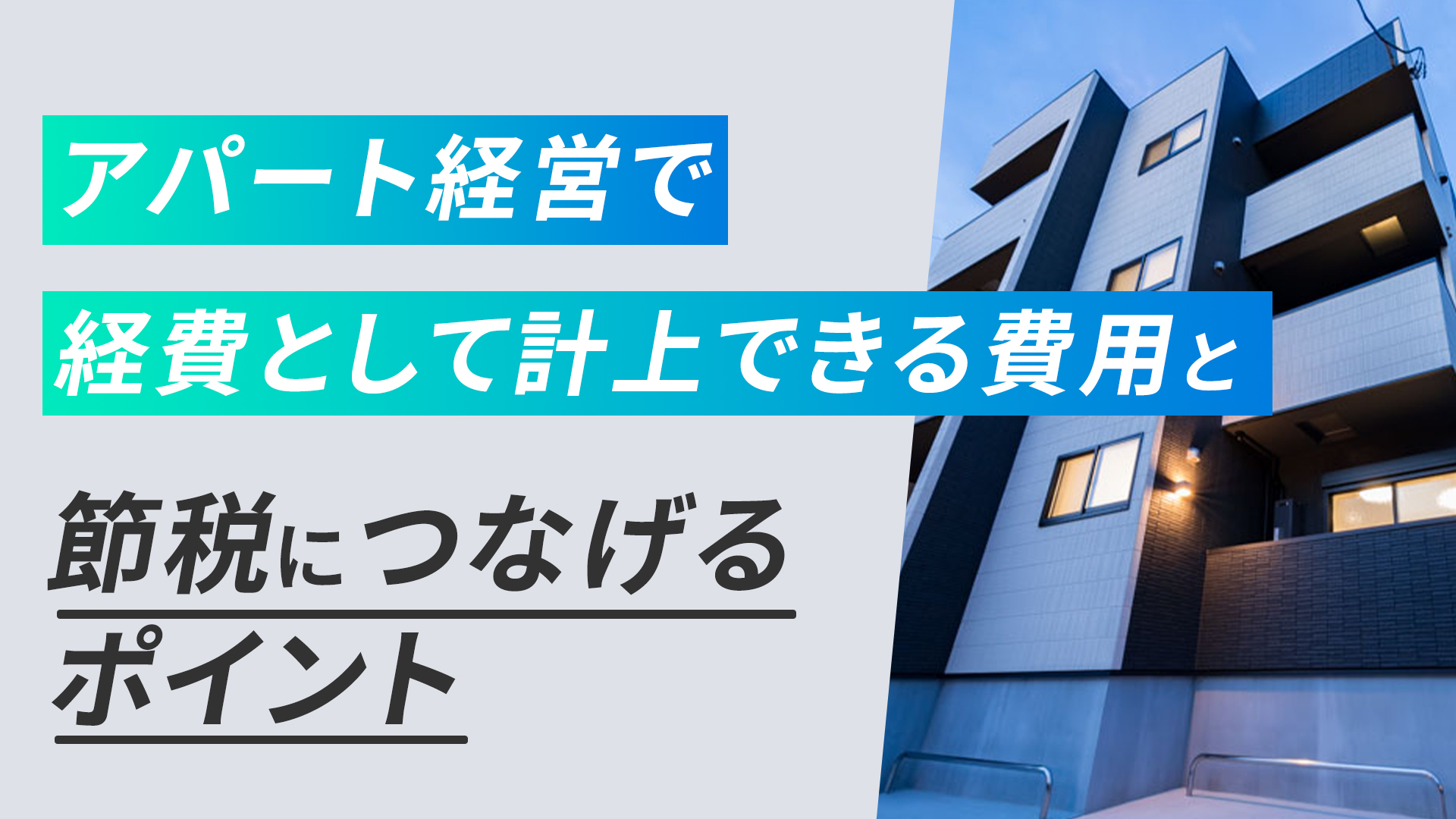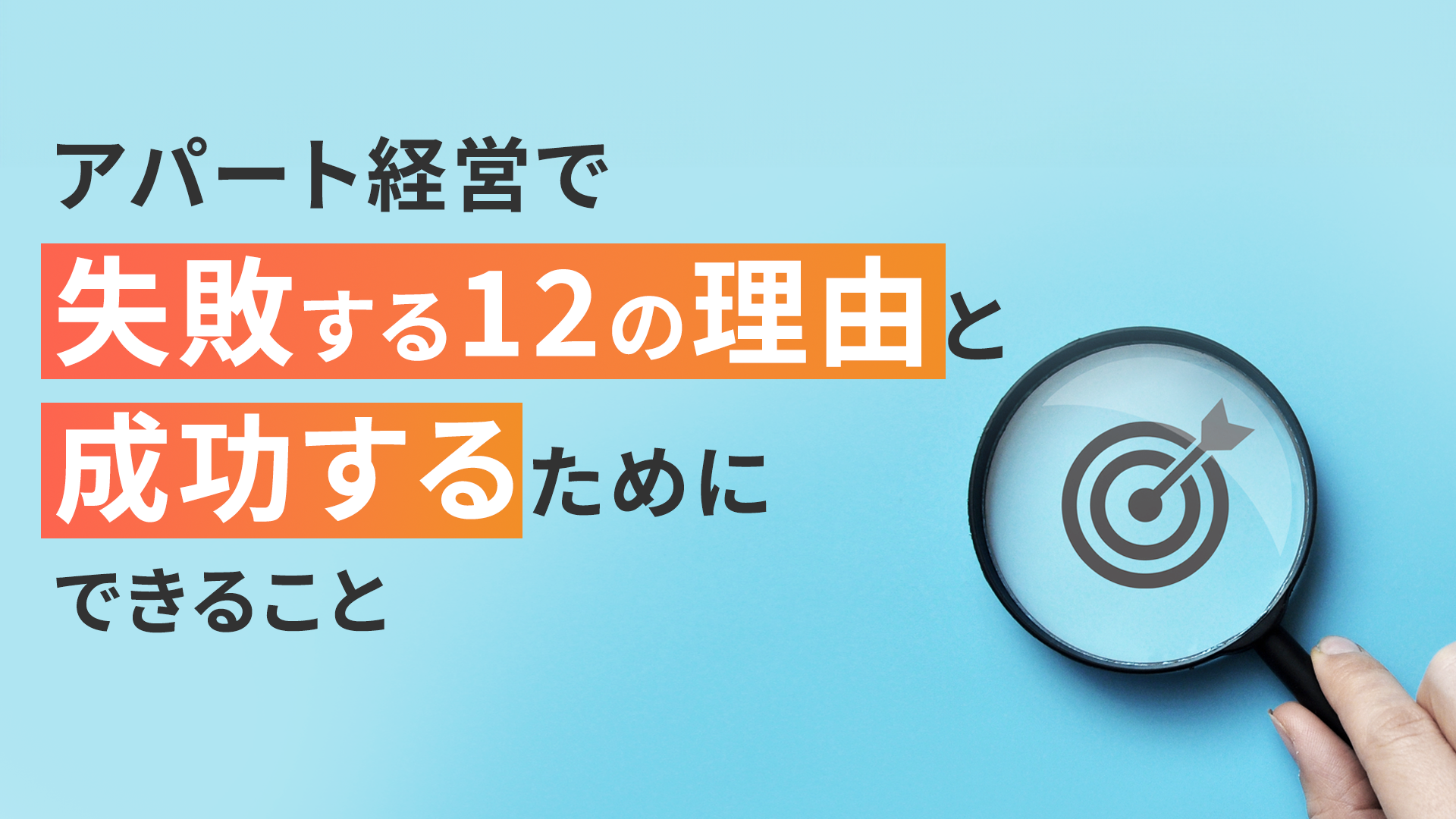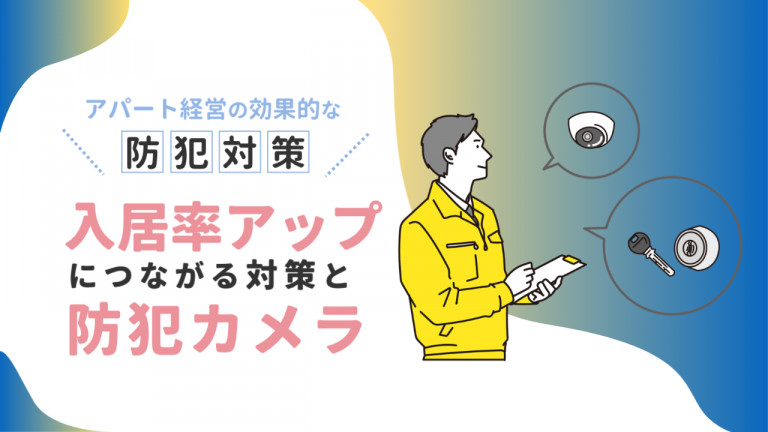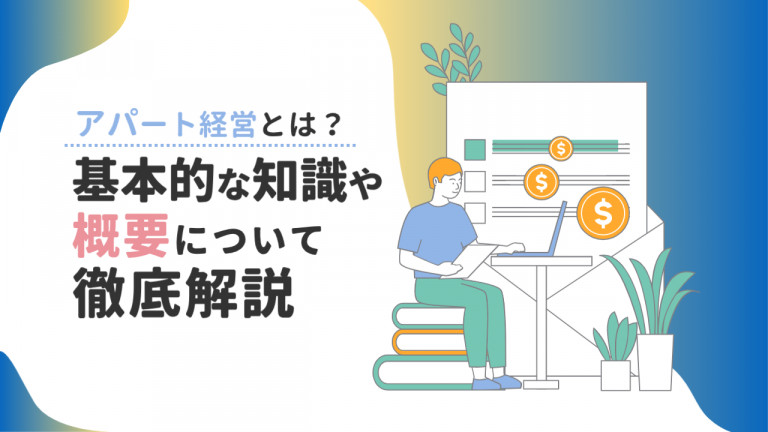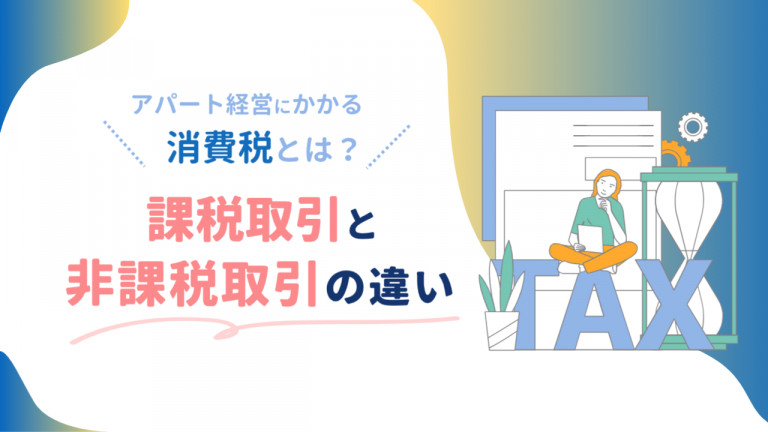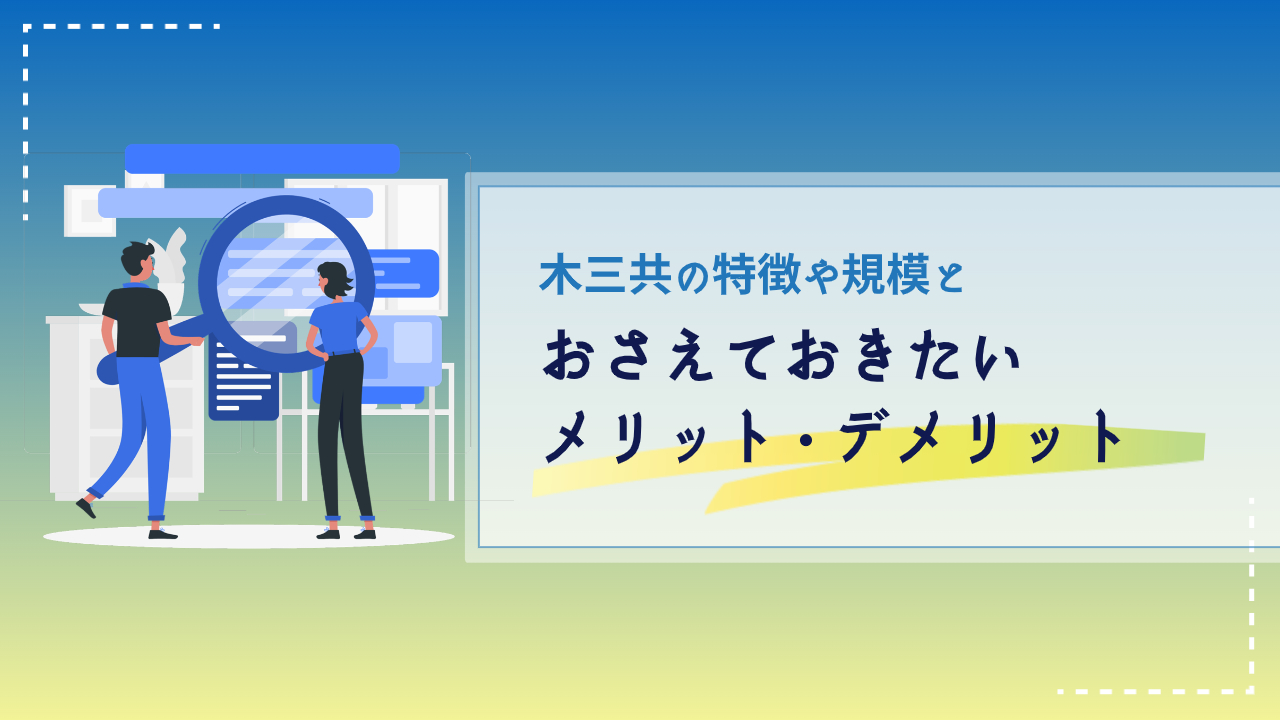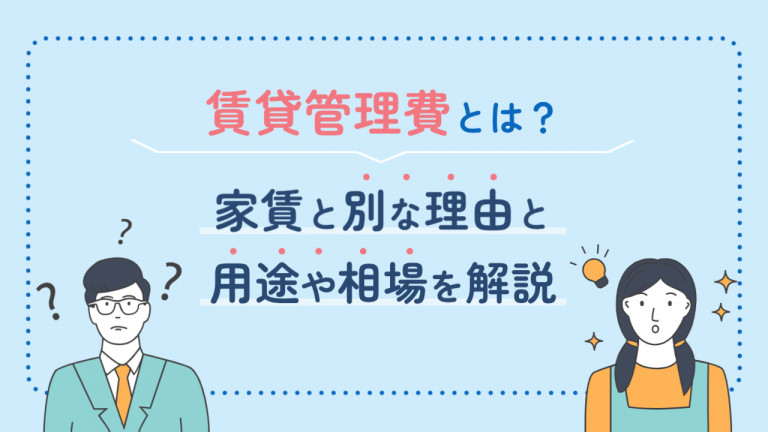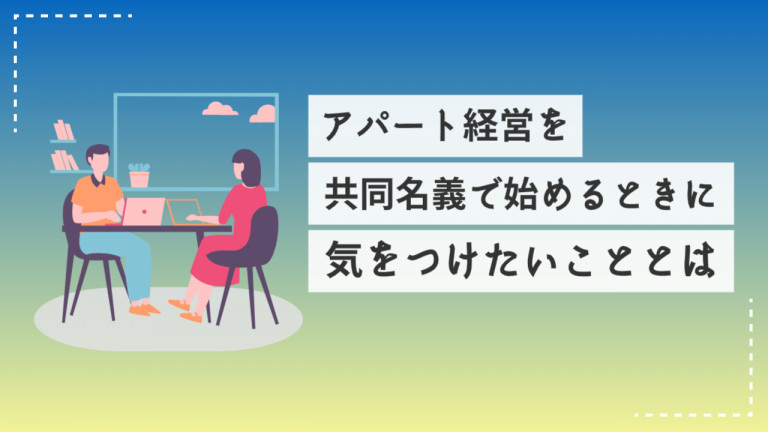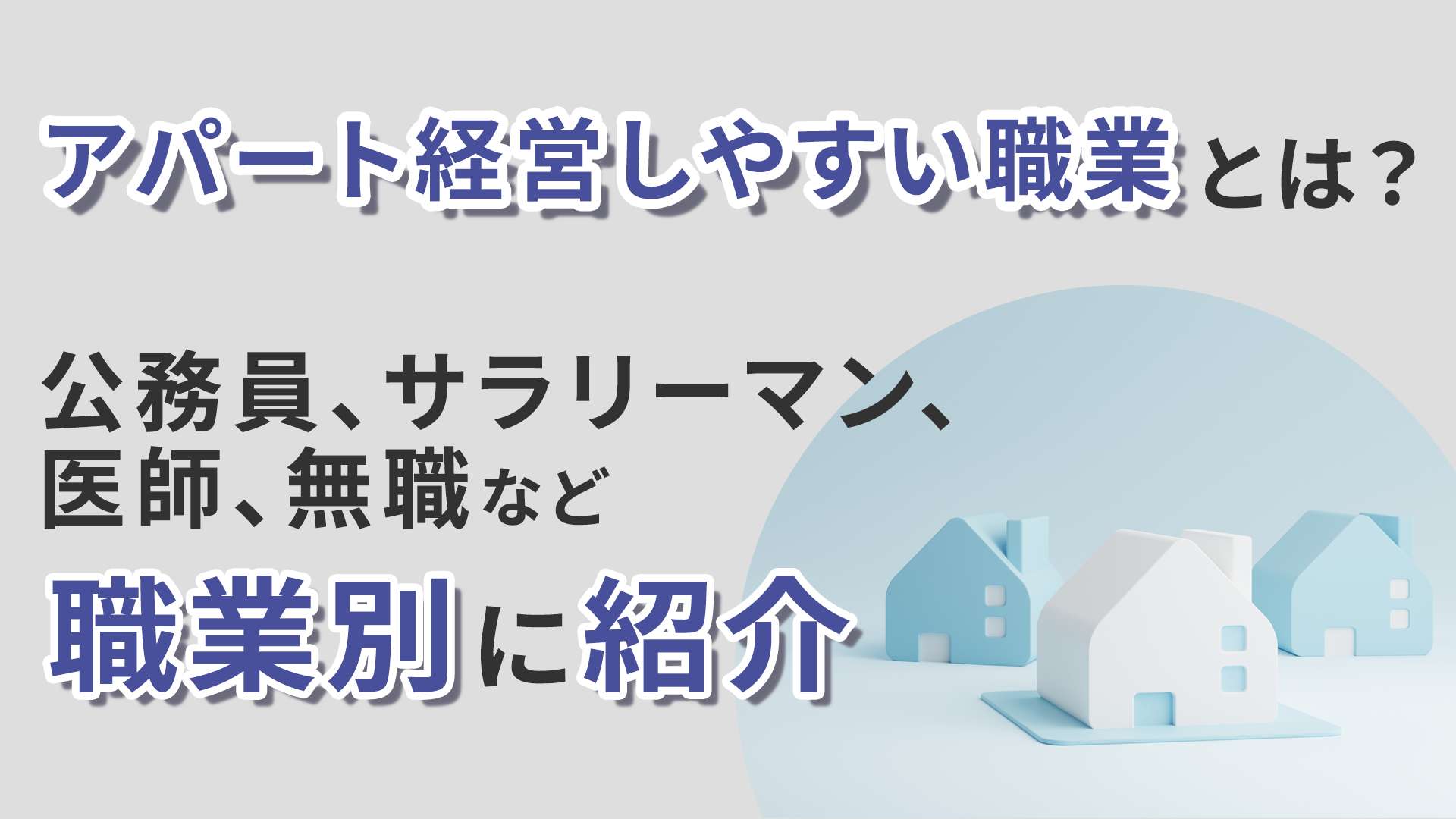
アパート経営を始めたいけど、サラリーマンの自分は向いているの?
自営業、医師、士業はどうなのか? 公務員はそもそもアパート経営しても問題ない?
アパート経営に興味を持っていても、自分の職業で本当にできるのか、不安を覚えている人もいると思います。
ここでは、「アパート経営をしたい!」と思っている人向けに、職業ごとのメリットやデメリット等を解説します。
1. サラリーマンにアパート経営は向いているのか
サラリーマンは意外にもアパート経営に向いている職業といえます。
というのも、アパートを経営するには、融資を受ける必要があります。
そのとき、毎月安定した収入のあるサラリーマンは融資が通りやすいのです。
会社員の場合、会社が副業を禁止しているケースもあります。
ただし、小規模であれば、副業と見なされないことも多いです。
不動産会社に管理を任せるなどして、自らの労働を少なくすれば、できることも多々あります。
なぜなら、労働を伴わない不動産投資は、本業に支障が出ないため、副業に当たらないというケースがよくあるからです。
会社の就業規定や周囲の先輩、同僚等から情報収集をして、アパート経営ができそうか判断してみましょう。
2. 自営業者にアパート経営は向いているのか
残念なことに、自営業は融資を受ける際、慎重な判断を下されることが多いです。
数カ月で融資がおりるケースもありますが、収入が不安定な場合など、ローンを組めるようになるまで数年かかることもあります。経営者個人の資産状況も重要ですが、それ以上に本業の内容が重要視されるようです。
不動産投資には、空き室リスクや天災リスク、家賃下落リスクなどさまざまなリスクがありますが、好不況の影響を受け難い面もあり、比較的安定的な事業と言えるでしょう。
たとえ不況の波が突如襲ってきても本当に大丈夫か。
よく考えてから、始めるようにしましょう。
3. 公務員にアパート経営は向いているのか
公務員がアパート経営をするにあたって、気をつけなければならないのが、副業規定です。
公務員は国家公務員法や地方公務員法で、副業が厳しく制限されています。
公務員がアパート経営をする際は、副業と見なされないよう、以下3つのポイントに留意する必要があります。
〇公務員がアパート経営をする際、副業と見なされないため留意すべき事項〇
・所有している不動産の規模
→5棟10室未満に。5棟10室を超えると、事業規模と見なされる可能性が高まります。
・家賃収入の限度額
→家賃収入は年間500万円未満に。
・自主管理はしない
→不動産の管理は管理会社に委託します。自主管理は“自営”と見なされます。
副業の範囲を超えない程度で、アパート経営を行うことをおすすめします。
4. 医師にアパート経営は向いているのか
医師の中にも、アパート経営に乗り出す人はたくさんいます。
多忙な医師が、資産形成しようと思ったら、比較的手間のかからない不動産投資は一つの選択肢です。
万が一、自分の身に何かあったときに、家族のためにも、不動産投資で安定した収入を得ることも考えたほうがいいでしょう。
そのうえ、高収入である医師は、金融機関から融資が下りやすく、節税効果も高いです。
しかし医師だからといって、誰もがアパート経営に成功するわけではありません。
収益を得るためには、不動産やビジネス等について、ある程度勉強しておく必要があります。
近年は医師を対象としたアパート経営セミナーや書籍もありますので、それらを参考にするのもいいでしょう。
5. 士業の方たちにアパート経営は向いているのか
弁護士、会計士、税理士などのいわゆる「士業」と呼ばれている人たちも、雇用形態などによって、アパート経営のしやすさは変わってきます。
正社員の士業は、会社員同様、ローンが通りやすい傾向にありますが、個人事業主だと自営業と見なされ、3年以上黒字でないといけないなど、色々と条件が付くようになります。
しかしアパート経営をするようになれば、アパートの一室を自分の事務所として活用できたり、本業の収入が安定しないときでも別途収益を得られるといった利点もあります。
士業の属性は高く、比較的融資が受けやすいため、正社員だったり、独立開業していても業績が好調な場合は、不動産投資を検討してみるのもいいでしょう。
6. 20代・30代がアパート経営をするメリット
20代、30代でアパート経営を始める方は、長期ローンが組めるというメリットがあります。
ほかにもメリットがありますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
7. 実際にどんな人がアパート経営をしているのか
アパート経営は、年齢・性別問わず、さまざまな人が実践していますが、特に40代以降の男性で、職業は会社員や公務員などの安定収入がある人の割合が高いです。
ちなみに、政府統計の総合窓口「e-Stat」の統計名「住宅・土地統計調査 平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村」表番号144-2によると、全国で現在の住居以外に貸家用の住宅を所有している人は、122万6,300世帯。
そのうち39万800世帯が自営業者で、46万9,400世帯が雇用者、34万9,700世帯は無職となっています。
ちなみに同調査の表番号143-1では、現在住んでいる家を除いて貸家用の住居を所有している世帯の年齢層の割合が示されていますが、20代以下は1万世帯以下と比較的少数なものの、30代後半では2万4,000世帯以上、40代前半では4万世帯以上、40代後半では6万世帯以上とどんどん増えていきます。
ここからも、高齢になるにつれて、アパート経営を考える人が増えるようです。
ただし、ある一定の年齢を超えてしまうと、事業の継承人がいないとアパートローンを組めなくなるといった注意事項もあります。
「定年したらアパート経営を始めよう」と思っていても、仕事をやめてしまうと、ローンを組めなくなる可能性が高まるため、早めに開始することをおすすめします。
アパート経営は、さまざまな職種・年齢の人が手がけていますが、成功するうえで大事なポイントは「どのような職業に就いているか」「何歳か」などではありません。アパート経営を考えるうえで「入居者」の存在は欠かせません。
引っ越しを考えている人が「ここに住みたい」と思えるような場所のアパートを購入できるか。住んでいる人たちが「ここを離れたくない」と思ってくれるよう、適宜メンテナンス、修繕ができるかなどといったことのほうが大切です。
会社員や医師など融資が下りやすい職種は、確かに、スタート地点では有利ですが、すべて管理会社に任せっぱなしでは、失敗してしまうこともあります。
自らの物件に愛情を注ぎ、丹念に育てる。それがアパート経営に最も向いている人だと思われます。
また、以下の記事ではアパート経営に向いている人の特徴をさらに詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。
株式会社マリモでは、長期に渡り安定したアパート経営をご提案しております。
弊社の木造アパート経営の情報はこちらからご確認ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要