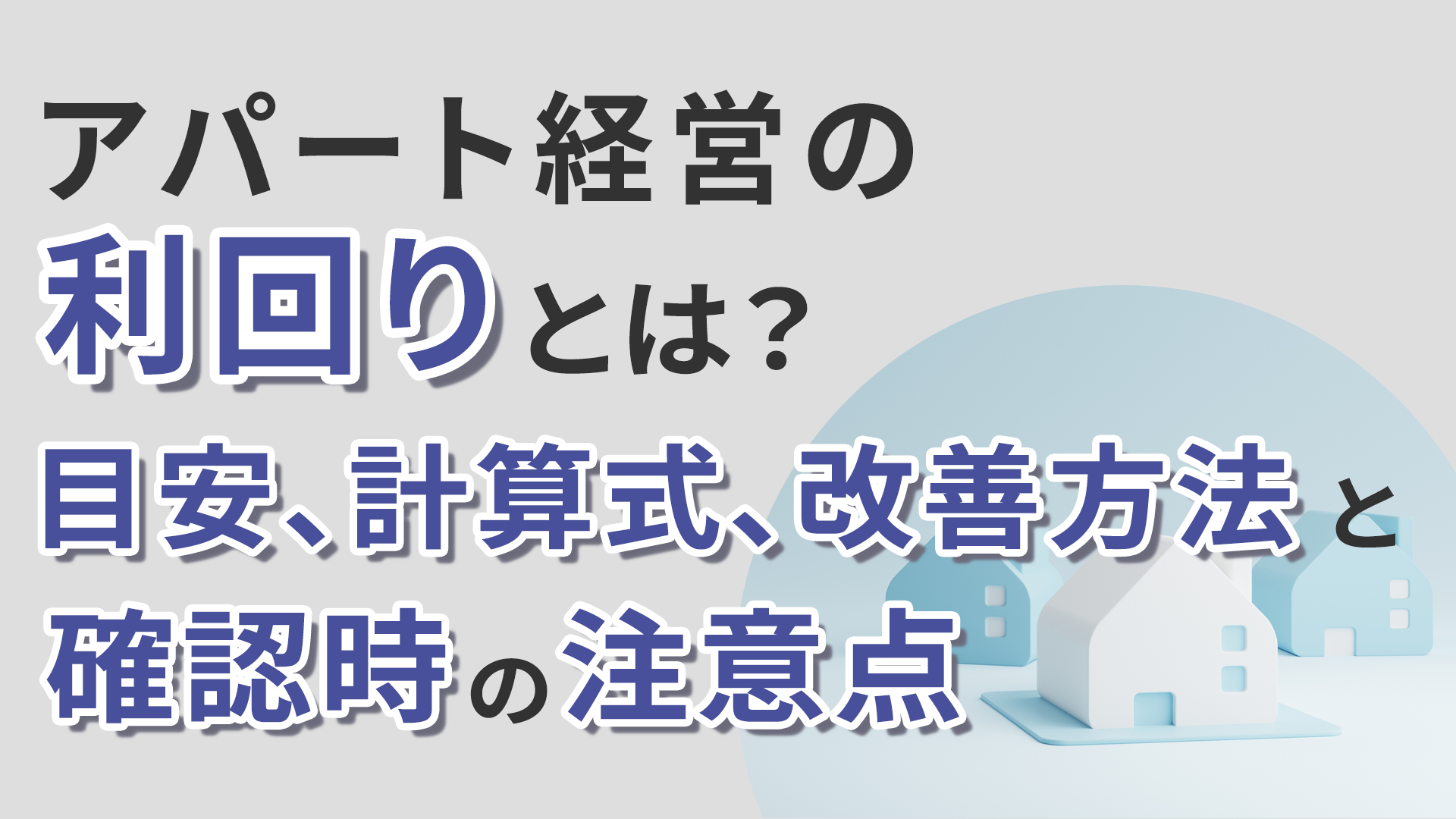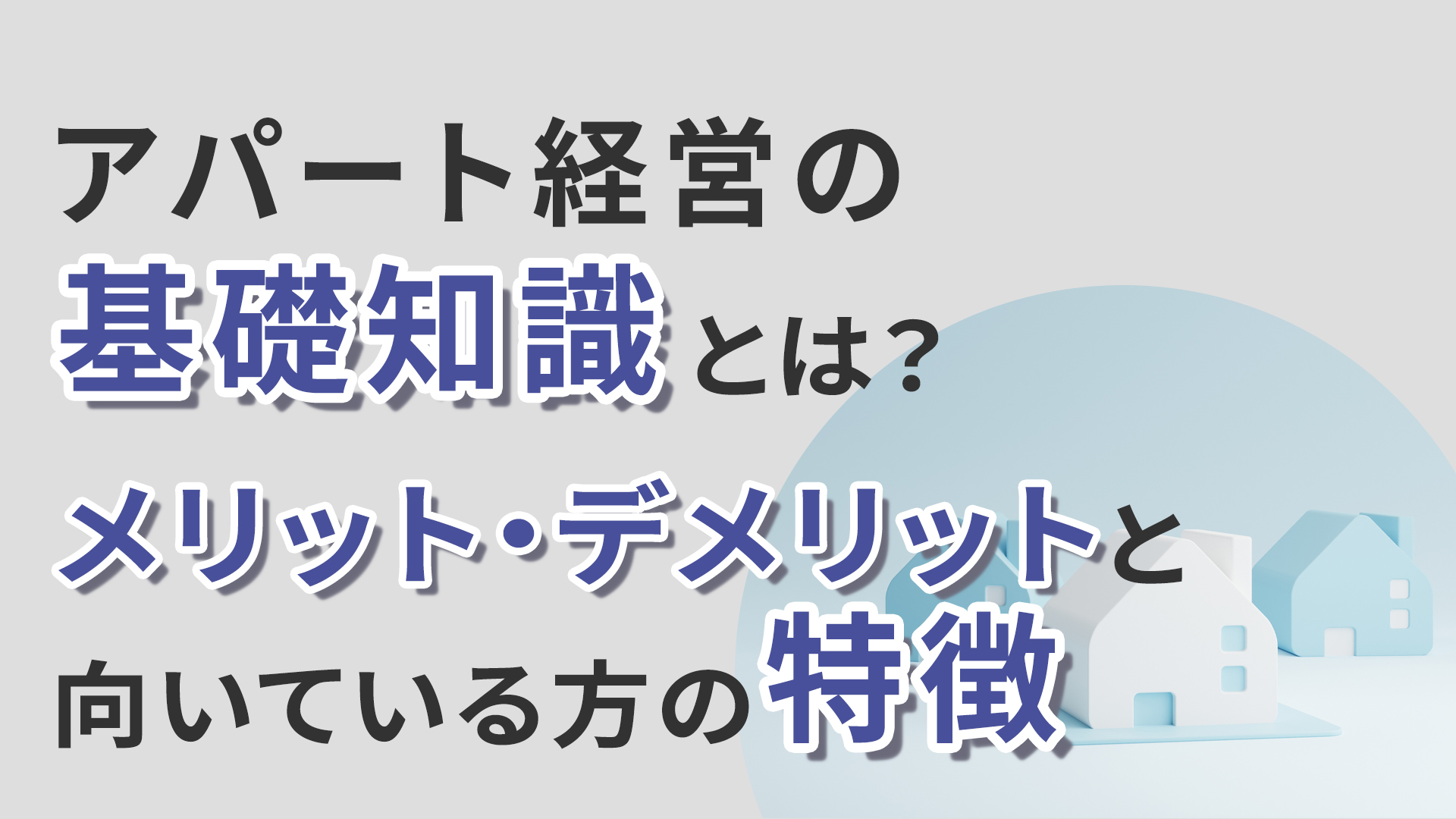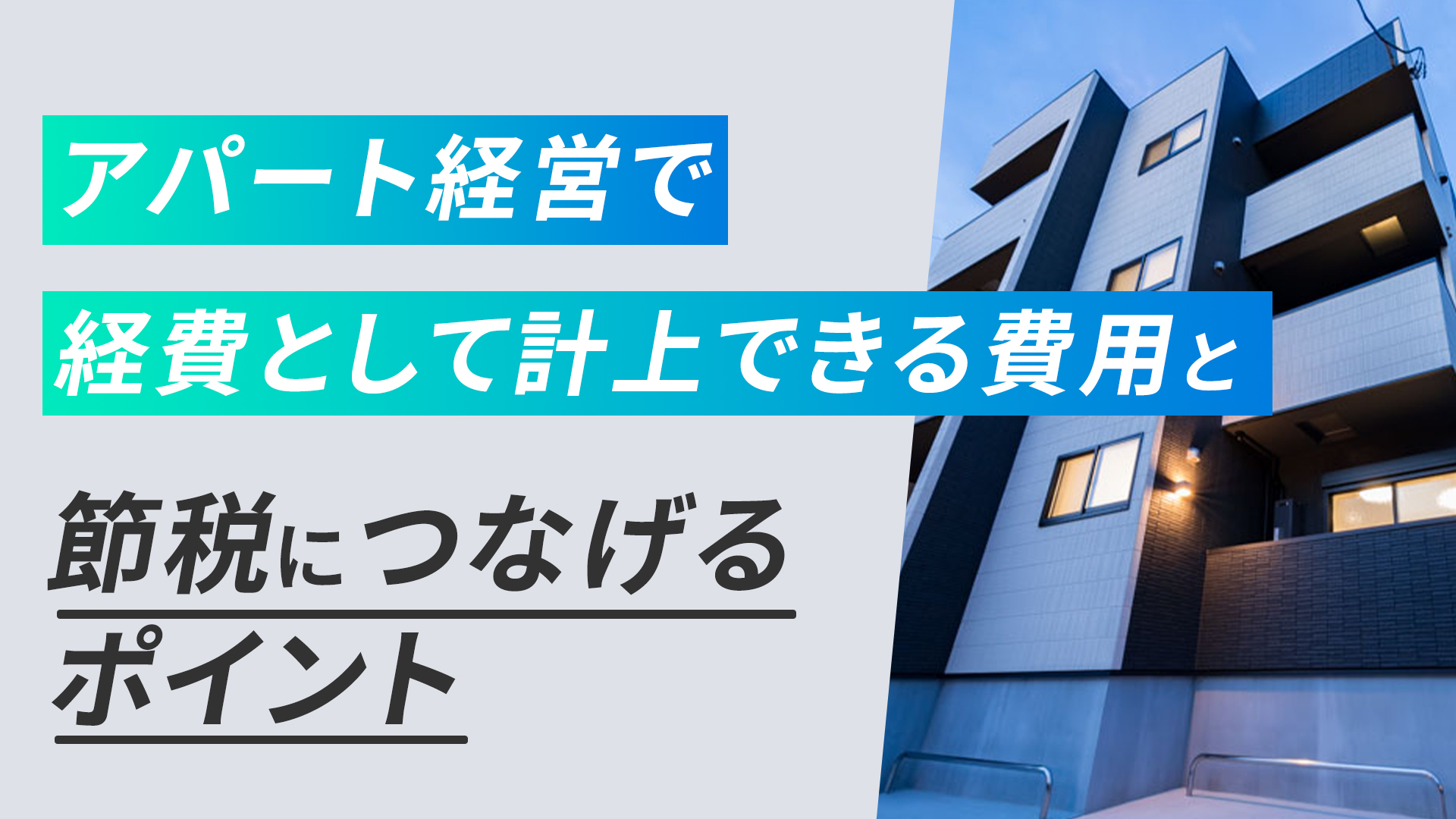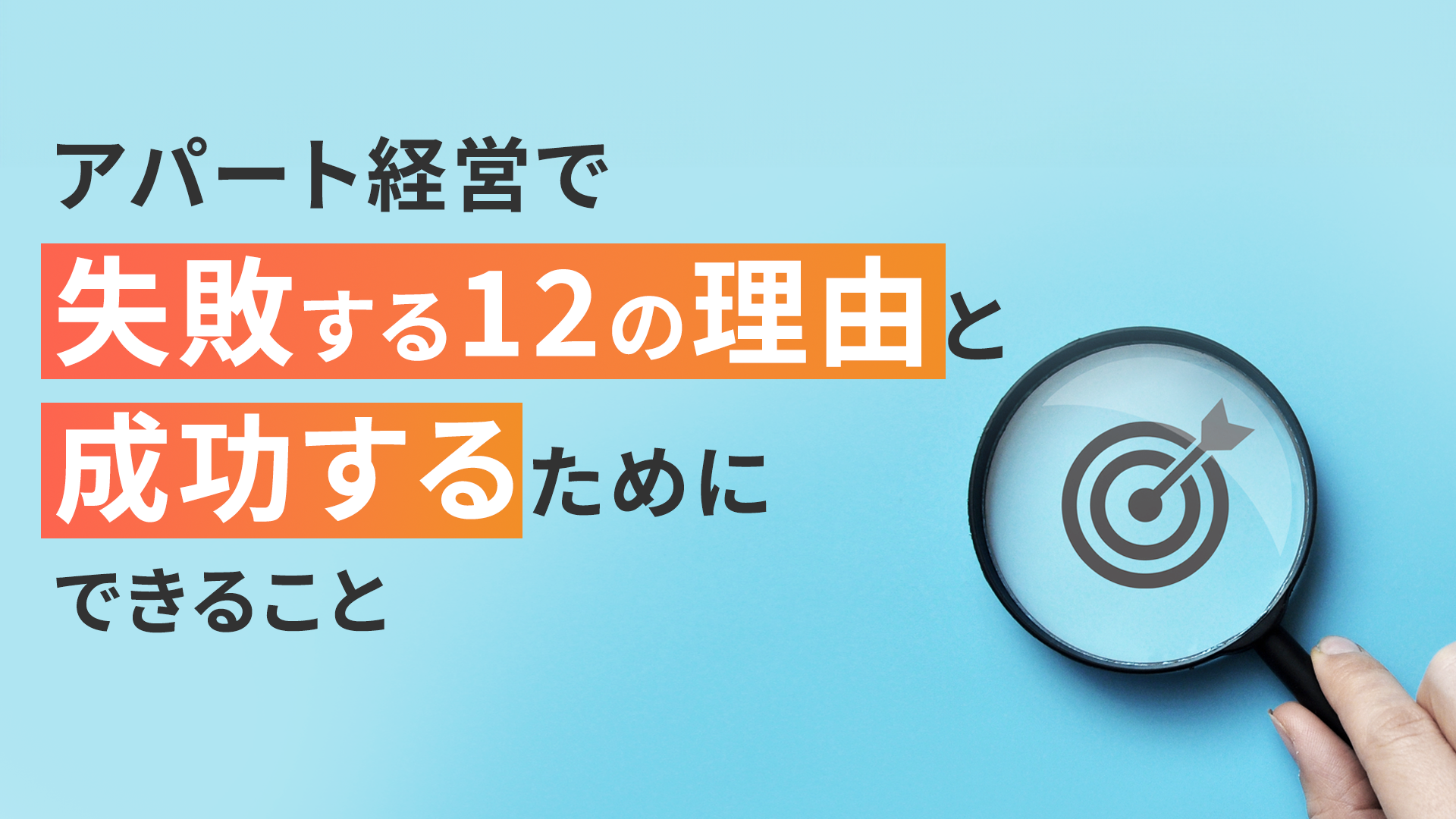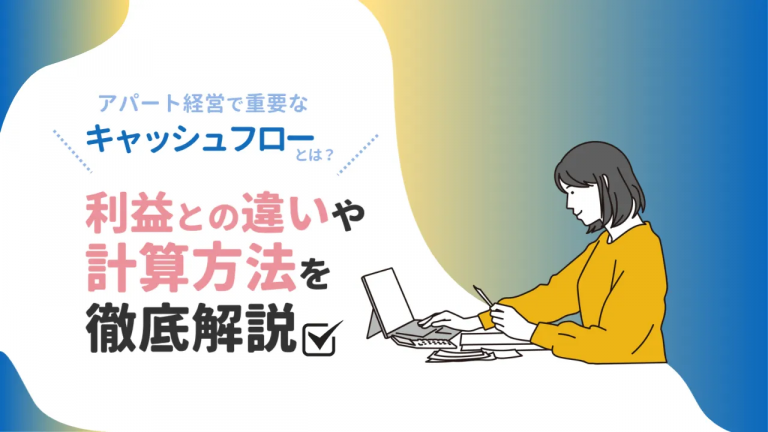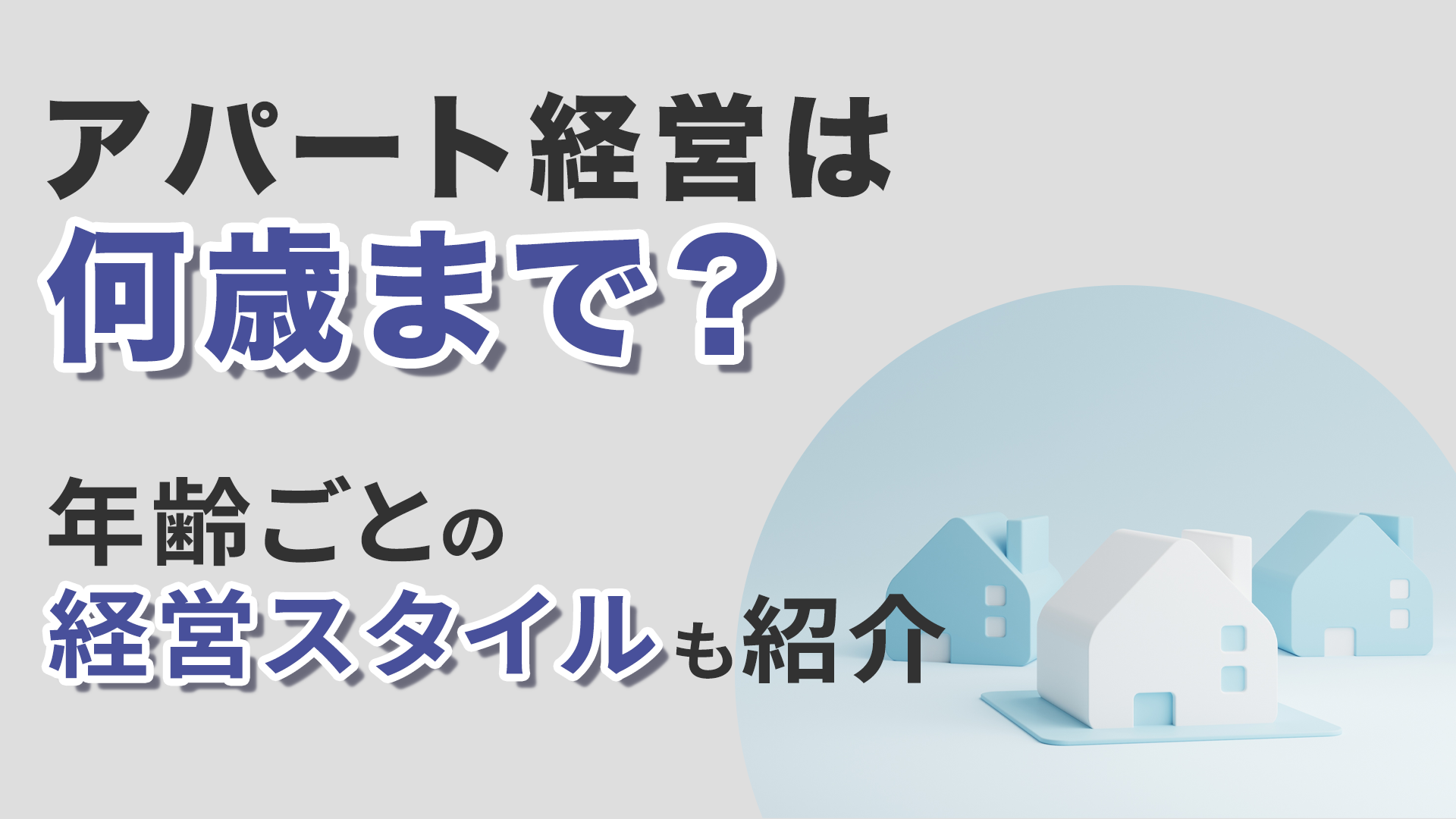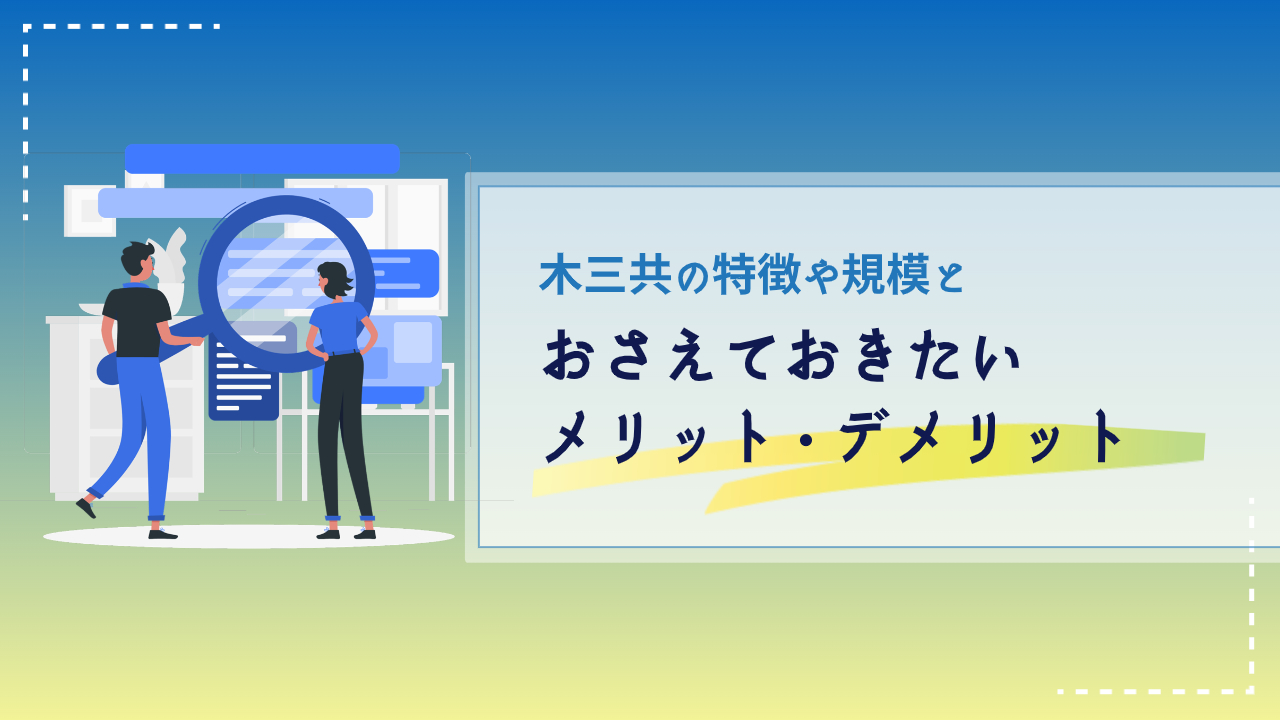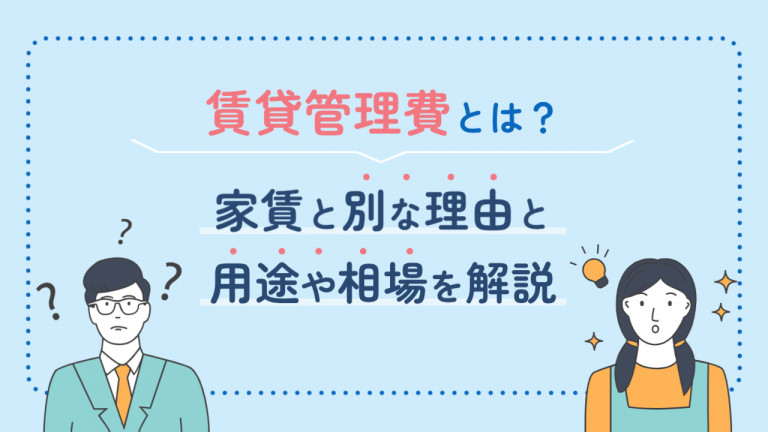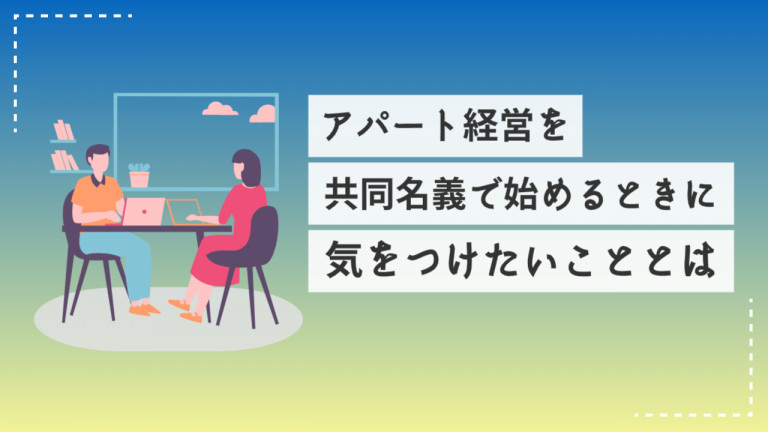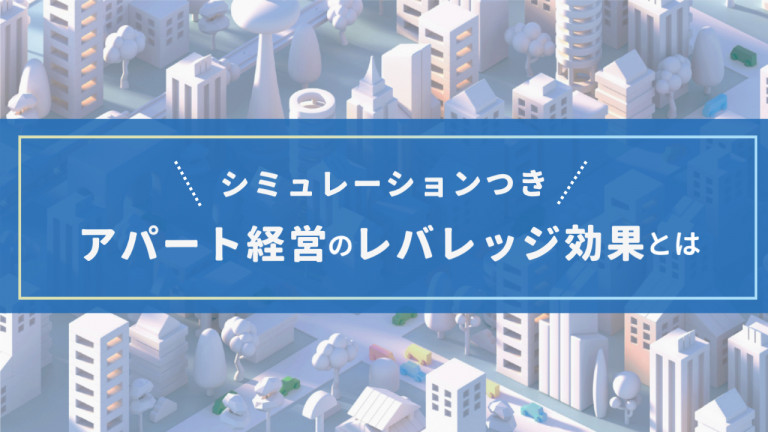
アパート経営について調べていると、「レバレッジ」という言葉を目にする機会があるかもしれません。
しかし「具体的にどのような意味なのかがよくわからない」と、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、アパート経営を行ううえで押さえておきたいレバレッジの概要を紹介します。
レバレッジを効かせるメリットやリスクも紹介するので、これからアパート経営を始めよう!とお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
アパート経営におけるレバレッジとは
レバレッジには、小さな力で重い物を動かすことが可能な「てこの原理」という意味が含まれています。
そこから転じて、アパート経営において使われるレバレッジには、少ない資金で大きな金額の資産運用を行い、収益性を高めるという意味があります。
具体的には、もともと持っている自己資金に借入金を加えることで、実質利回り以上の収益が得られるようになるということです。
よりイメージしやすいように、2,000万円の自己資金のみで投資を始める方と、3,000万円の借入金を加えた、5,000万円で投資を始める方を例に解説します。
【投資における条件】
自己資金のみ | 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
借入金額 | – | 3,000万円 |
物件価格 | 2,000万円 | 5,000万円 |
実質利回り | 5.0% | 5.0% |
年間収益 | 100万円 | 250万円 |
年間収益は「物件価格×実質利回り」で計算することができるため、自己資金のみを持っている方は100万円、そして自己資金と借入金を持っている方は250万となります。
同じ金額の自己資金を持っている場合でも、借入金を利用している場合のほうが、大きな収益を生み出せることがあるのです。
このように、同じ金額の自己資金に対して、大きな収益が得られることを「レバレッジ効果」とよびます。
レバレッジ効果の具体的なシミュレーション
レバレッジ効果の概要を押さえたところで、より具体的なシミュレーションを行ってみましょう。
一般的に、レバレッジを効かせるためには、実質利回りが借入金利を上回っていることが最低限の条件とされています。
この、実質利回りと借入金利の差を「イールドギャップ」とよびます。
たとえば、実質利回りが10%で、借入金利が3%であった場合のイールドギャップは、7%ということです。
イメージしやすいように、シミュレーションの内容を確認していきましょう。
レバレッジ効果が得られるケース
ここでは、投資の条件を、自己資金のみを利用した場合と、自己資金と借入金を利用した場合に分けてシミュレーションを行います。
まずは、それぞれの投資における条件と、シミュレーションの結果を確認していきましょう。
【投資の条件ごとのシミュレーション】
自己資金のみ | 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
借入金 | – | 4,000万円 |
物件価格 | 1,000万円 | 5,000万円 |
実質利回り | 10% | 10% |
借入金利 | – | 3.0% |
返済期間 | – | 30年間 |
年間返済額 | – | 約200万円 |
年間収益 | 100万円 | 500万円 |
手残り | 100万円 | 300万円 |
自己資金のみで投資を行った場合に得られる年間収益と、借入金を追加して投資を行った場合に得られる年間収益の差は、400万円であることがわかります。
さらに借入金を、月々の返済額が一定の「元利均等返済」で返済した場合、年間の返済金額は約200万円です。
続けて、年間収益の500万円から年間返済額の200万円を引くと、返済完了後の資金の手残りは300万円になります。
自己資金のみで投資を行った場合と比べると、手残りが増えていることがわかるでしょう。
なお、借入金の年間返済額は、以下のサイトでシミュレーションできるのでぜひ確認してみてください。
レバレッジ効果が得られないケース
反対に、どのようなケースであればレバレッジ効果が得られないのかを、前述したシミュレーションの条件と同様の数値をもとに、実質利回りの数値のみを変更して比較します。
【投資の条件ごとのシミュレーション】
自己資金のみ | 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
借入金 | – | 4,000万円 |
物件価格 | 1,000万円 | 5,000万円 |
実質利回り | 5.0% | 5.0% |
借入金利 | – | 3% |
返済期間 | – | 30年間 |
年間返済額 | – | 約200万円 |
年間収益 | 50万円 | 250万円 |
手残り | 50万円 | 50万円 |
自己資金における利回り | 5.0% | 1.0% |
借入金を活用しても手残りが増加せず、自己資金における利回りは低下していることがわかります。
上記のシミュレーションのように、借入金を使っても、収益が上がらないことを「逆レバレッジ」とよびます。
逆レバレッジの概要は後述しますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。
パート経営でレバレッジ効果を狙いやすい資金計画の立て方
アパート経営では、レバレッジを活用することで少ない自己資金でも大きな金額の物件を購入できるのが魅力です。
しかし、成功のためには、あらかじめ金利や返済期間を考慮に入れて資金計画を立てていないと期待した効果が得られず、損失が生じる恐れもあります。
特に、利回りと借入金利の差であるイールドギャップを意識しておくことが重要です。ここではイールドギャップの概要に加え、金利や返済期間によってレバレッジ効果がどのように変化するのかを解説します。
イールドギャップとは
イールドギャップとは「実質利回り-金利」のことをいいます。たとえば、実質利回りが6%、借入金利が2%であった場合、イールドギャップは4%ということになります。
ただし、レバレッジ効果はイールドギャップの大小だけで決まるわけではありません。これは、借入金の返済には金利だけでなく、元本の返済も含まれているためです。
不動産投資を成功させるためには、できるだけ利回りと金利の差を大きくしなければなりません。イールドギャップが大きいほど、一般的にレバレッジ効果が高まることが期待できます。
一方で、金利負担が利益を上回りイールドギャップが小さい場合やマイナスになった場合は借り入れによる投資が逆効果になる場合もあるため注意が必要です。
今後の金利上昇リスクを踏まえた計画を立てておくことが重要です。
金利が異なる場合のレバレッジ効果
レバレッジ効果を左右するものとして、借入金利が挙げられます。仮に1%でも金利が異なれば、長期的に総返済額やキャッシュフローに大きく影響することになります。
たとえば、借入金利が2%の場合と、3%の場合ではどのような違いがあるのか比較していきましょう。
前提として、以下の条件で比較します。
- 物件価格:8,000万円(うち自己資金1,000万円)
- 実質利回り:6%
- 借入額:7,000万円
- 返済期間:25年
借入金利2%の場合
借入金利が2%であった場合、実質利回り6%のイールドギャップは「6%-2%=4%」です。
物件価格が8,000万円で実質利回りが6%であった場合、年間収益は「8,000万円×6%=480万円」と予想できます。
年間ローン返済額を計算すると356万円です。
借入金利が2%であった場合、自己資金1,000万円に対するキャッシュフローは「480万円-356万円=124万円」となります。金利が2%と低い場合は、レバレッジ効果が高まりやすくなります。
返済の負担も押さえられることから、月々のキャッシュフローをプラスにしやすいのが特徴です。
借入金利3%の場合
前提条件は同じにして、借入金利が3%になった場合もシミュレーションします。実質利回りが6%と仮定するとイールドギャップは「6%-3%=3%」です。
年間収益は480万円で同じですが、年間のローン返済額は399万円となります。自己資金1,000万円に対するキャッシュフローを計算すると「480万円-399万円=81万円」となりました。
金利が1%違うだけで、キャッシュフローに43万円の差が出ることがわかります。ここからもわかるとおり、できるだけ低金利である方がレバレッジ効果は大きくなるといえるでしょう。イールドギャップが縮まると利回りの変動や空室率の影響を受けやすくなってしまう点に注意が必要です。
返済期間が異なる場合のレバレッジ効果
レバレッジ効果に影響を与えるもう一つの要素が、返済期間の長さです。月々の返済負担を軽くするために、返済期間を長く設定しようと考えている方もいることでしょう。
しかし、返済期間が長くなるほど総返済額が増えることになります。ここでは、返済期間が25年のケースと、30年のケースについて比較します。
比較条件は以下のとおりです。
- 物件価格:8,000万円(うち自己資金1,000万円)
- 実質利回り:6%
- 借入額:7,000万円
- 返済金利:2%
返済期間25年の場合
実質利回りが6%で返済金利が2%だった場合のイールドギャップは4%、年間収益は480万円、年間ローン返済額は356万円となります。
1,000万円の自己資金に対するキャッシュフローは124万円です。
将来的な金利上昇リスクを抑えたい場合は、返済期間を短く設定する方法があります。ただし、月々の返済額が高くなることについては十分理解が必要です。
返済期間30年の場合
続いて、返済期間が30年の場合についてです。同様にイールドギャップは4%、年間収益が480万円と考えます。年間ローン返済額は310万円です。
計算すると、1,000万円の自己資金に対するキャッシュフローは170万円になります。
借入金や金利の条件が同じでも、返済期間が5年違うだけでキャッシュフローに46万円の差が生まれました。このことを考えると、長期的な返済計画を立てるのも一つの選択肢です。
金融機関によっては30年以上のローンを取り扱っているケースもありますが、収益性とのバランスも事前に確認する必要があります。
逆レバレッジには注意が必要
ここまで、自己資金に借入金を追加して投資を行うことで、レバレッジが効かせられることを紹介しました。
しかし、レバレッジを効かせようとして借入金を利用した場合に、注意したいものが「逆レバレッジ」です。
逆レバレッジとは、借り入れを行ったことで、かえって収益が下がってしまうことです。
逆レバレッジが起こるケースとしては「金利が高い」「利回りが低い」の2点が挙げられます。
それぞれのケースを、詳しく確認していきましょう。
なお、前述したレバレッジ効果のシミュレーションで使用した条件と、同様の数値をもとに紹介します。
ケース①借入金利が高い
借入金利が高い場合、どのようなことで逆レバレッジが起こるのかを、自己資金と借入金を利用したケースで解説します。
以下のシミュレーションにおいて、借入金利の数値のみ変更しており、ほかの条件はすべて同じです。
【投資の条件ごとのシミュレーション】
① 自己資金と借入金 | ② 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
借入金 | 4,000万円 | 4,000万円 |
物件価格 | 5,000万円 | 5,000万円 |
実質利回り | 10% | 10% |
借入金利 | 3.0% | 11% |
利息 | 120万円 | 440万円 |
年間収益 | 500万円 | 500万円 |
実質年間収益 | 380万円 | 60万円 |
上記のように、同じ資金を使って同じ条件の物件を購入した場合でも、借入金利の数値によって必要な利息が大きく変わることがわかります。
借入金利が3.0%の場合、実質年間収益が380万円であることに対して、借入金利が11%の場合は実質年間収益が60万円しかありません。
借入金利が高くなるほど、手元に残る年間収益の金額が低くなり、収益が下がってしまうといえるでしょう。
ケース②実質利回りが低い
実質利回りが低い場合に起こる、収益の変化を確認してみましょう。
前述した、借入金利が高いケースと同様の条件を用いたうえで、比較対象として自己資金のみで投資を行った条件も追加しています。
なお、②と③は、同じ条件ですが、比較するために実質利回りの数値を変更しています。
【投資の条件ごとのシミュレーション】
① 自己資金のみ | ② 自己資金と借入金 | ③ 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
借入金 | – | 4,000万円 | 4,000万円 |
物件価格 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
実質利回り | 10% | 10% | 3.0% |
借入金利 | – | 3.0% | 3.0% |
利息 | – | 120万円 | 120万円 |
年間収益 | 100万円 | 500万円 | 150万円 |
実質年間収益 | 100万円 | 380万円 | 30万円 |
上記の②と③を比べると、実質利回りが10%の場合に得られる実質年間収益は380万円であり、3.0%の場合に得られる実質年間収益は30万円であることがわかります。
また、③のように実質利回りが低いと、借入金を利用しても、①の自己資金のみで投資を行った場合よりも実質年間収益が低く、逆レバレッジが起こることも明確になりました。
このように、同じ条件でも実質利回りが7.0%と違うと、実質年間収益に350万円もの差があることから、実質利回りは高ければ高いほどよいといえます。
なお、上記のシミュレーションは実質利回り以外の条件が同一であることから、実質利回りが低いと実質年間収益も低くなり、逆レバレッジが起こりやすいということもわかります。
レバレッジ効果を得られる実質利回りの目安
実質利回りが低いと逆レバレッジが起こることを前述しましたが、具体的にどの程度の実質利回りであればレバレッジ効果があるのでしょうか。
レバレッジを効かせるためには、実質利回りがある程度高い物件を選ぶ必要があります。
ただし、実質利回りが低い物件でもレバレッジ効果を得られるケースはあるため、一概に、実質利回りが低い物件ではレバレッジ効果が得られないというわけではありません。
実質利回りの数値によって変化するレバレッジ効果を、以下で詳しく解説します。
実質利回りによって異なるレバレッジ効果の有無
ここからは、実質利回りの大きさに対するレバレッジ効果の有無を、借入金利が2.0%の場合と、4.0%の場合に分けて紹介します。
なお、ここでは借入金を返済したあとの手残りにおける利回りが、実質利回りを上回ったときにレバレッジ効果があると判断します。
借入金利が2.0%の場合と4.0%の場合では、実質利回りがどのくらいの数値であればレバレッジ効果があるのかを、以下の表で確認してみましょう。
【借入金利が2.0%の場合】
自己資金 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
借入金 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
運用額の総額 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
実質利回り | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
借入金利 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
借入期間 | 30年間 | 30年間 | 30年間 | 30年間 |
年間の返済額 | 約220万円 | 約220万円 | 約220万円 | 約220万円 |
年間収益 | 320万円 | 400万円 | 480万円 | 560万円 |
返済終了後の手残り | 100万円 | 180万円 | 260万円 | 340万円 |
自己資金の利回り | 3.3% | 6.0% | 8.6% | 11.3% |
レバレッジ効果 | なし | あり | あり | あり |
【借入金利が4.0%の場合】
自己資金 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
借入金 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
運用額の総額 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
実質利回り | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
借入金利 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
借入期間 | 30年間 | 30年間 | 30年間 | 30年間 |
年間の返済額 | 約285万円 | 約285万円 | 約285万円 | 約285万円 |
年間収益 | 320万円 | 400万円 | 480万円 | 560万円 |
返済終了後の手残り | 35万円 | 135万円 | 195万円 | 275万円 |
自己資金の利回り | 1.1% | 4.5% | 6.5% | 9.1% |
レバレッジ効果 | なし | なし | あり | あり |
このように、実質利回りが5.0%もしくは6.0%を超えた場合は、レバレッジが効いていないことがわかります。
上記のシミュレーションの結果を踏まえると、実質利回りの目安は5.0~6.0%であるため、この数値を目安に物件を選定するとよいでしょう。
アパート経営でレバレッジ効果を活用するメリット
アパート経営を始める際、投資の収益性を高めるために、レバレッジを効かせたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、アパート経営でレバレッジを効かせる2つのメリットを紹介します。
メリット①投資の効率がよい
レバレッジを効かせると、投資の効率を上げることができます。
すなわち、少ない自己資金で、効率よく投資規模を拡大できるということです。
物件を自己資金のみで購入したケースと、自己資金と借入金を利用して購入したケースで比較してみましょう。
【ケースごとの投資シミュレーション】
自己資金のみ | 自己資金と借入金 | |
自己資金 | 500万円 | 500万円 |
借入金 | – | 900万円 |
物件価格 | 500万円 | 1,000万円 |
実質利回り | 5.0% | 5.0% |
借入金利 | – | 2.0% |
返済期間 | – | 30年間 |
年間返済額 | – | 約84万円 |
年間収益 | 25万円 | 100万円 |
手残り | 0円 | 16万円 |
上記を参照すると、500万円の自己資金を持っている場合でも、使用する自己資金を100万円に抑えて、借入金900万円を利用すると、レバレッジが効いていることがわかります。
さらに、自己資金のみで物件を購入すると手残りがほとんどない状態になりますが、借入金を利用する場合は自己資金が400万円残るため、別の投資を行うことも可能です。
このように、レバレッジ効果をうまく活用することで、自己資金を抑えて投資規模を拡大できることは、大きなメリットだといえるでしょう。
メリット②保険の効果が高い
アパート経営におけるレバレッジには、高い保険の効果が得られるというメリットもあります。
借入金を利用すると、団体信用生命保険に加入できることがほとんどです。
団体信用生命保険とは、借入金の返済期間中に契約者本人が死亡したり、高度の障害状態になったりした場合に、借入金がゼロになる保険のことです。
メリット①で紹介したケースを例に、物件の購入者が亡くなり、配偶者や子どもに相続されたとして考えてみましょう。
自己資金500万円を使って物件を購入した場合、借入金を利用していないので、物件をそのまま相続することができます。
一方、自己資金100万円で、借入金を利用して1,000万円の物件を購入した場合、団体信用生命保険によって、借入金の900万円がゼロになります。
そのため、物件を相続する方には、自己資金の残り400万円と、借入金を返済する必要がない物件を残せるというわけです。
このことから、アパート経営においてレバレッジを効かせて団体信用生命保険に加入できれば、高い保険の効果が得られる場合があるといえるでしょう。
メリット③手元に資金を残しておける
レバレッジ効果をうまく活用することで、少ない自己資金で投資を始められるため、手元に資金を残しやすい点がメリットといえます。アパート経営では想定外の修繕費が発生することがあるほか、空室リスクについてもよく考えておかなければなりません。
そのため、手持ちの資金をすべて投資にあててしまうと、何かあった際に対応できなくなってしまう恐れがあります。残した資金は複数投資やリスク対応のために活用しましょう。
メリット④機会損失を防げる
投資機会を逃さないためにもレバレッジを活用できます。条件のよい物件はすぐに売れてしまいますが、その際に購入資金が不足しているケースもあるでしょう。
しかし、借り入れを活用することで機会損失を防ぐことが可能です。
また、中には将来的にアパート経営を始めたいと考えているものの、そのための資金が不足している方もいるはずです。こういった方もレバレッジ効果を活用し融資を受けて物件を購入すれば、早期に投資できるのがメリットといえます。
メリット⑤団信に加入できる
アパート経営を始めたいと考えているものの、仮に自身に何かあった際に残りの借入金の返済が遺族の負担になってしまうことを心配している方もいるのではないでしょうか。
万が一の際に遺族にローンを残さないための安心材料となるのが、団信(団体信用生命保険)への加入です。
不動産投資ローンを組む際には一部例外を除き多くのケースで団信に加入することとなり、団信ではローン契約者に何かあった際は残りの借入金が保険で完済されます。保険料の総支払い額が高くなるなどの注意点もありますが、団信に加入できるのは大きなメリットといえるでしょう。
アパート経営でレバレッジ効果を活用するリスク
アパート経営でレバレッジを効かせることには、さまざまなメリットがある一方で、リスクがあることも押さえておきましょう。
メリットだけを確認すると、かえって赤字になる可能性もあるので注意が必要です。
ここでは、レバレッジを効かせる前に押さえておきたい、2つのリスクを紹介します。
リスク①借入金の返済リスクがある
レバレッジを効かせる場合、借入金を返済しなければなりません。
アパート経営における、基本的な収入源は入居者からの家賃です。
入居者で埋まっている満室の状態であれば、毎月安定した家賃を得られるので、借入金の返済は問題ないでしょう。
しかし、空室が埋まらない状態が続けば、得られる収入が少なくなるので、借入金の返済が厳しくなることが想定されます。
月々の返済額が数万円程度であれば、空室があっても返済できる可能性はありますが、仮に返済額が数十万円に及ぶ場合は、返済できずに自己破産してしまう危険性もあります。
このような事態を回避するためには、空室リスクの低い物件を選ぶことが大切です。
リスク②金利が上昇する可能性がある
アパート経営を行ううえで借入金を利用する場合は、借入金利の数値も考慮する必要があります。
たとえば、5,000万円の物件を借入金利2%、返済期間30年で購入した場合で考えてみましょう。
この場合、月々の返済額は、約18万円となりますが、借入金利が3%に上昇すると、月々の返済額が約21万円になります。
このように、借入金利が1%上昇するだけでも、毎月返済しなければならない金額は大きく増えることがわかるでしょう。
なお、借入金利が上昇するリスクにおいては、予測できないため回避することが困難です。
レバレッジを効かせるためにも、借入金利が上昇するリスクを押さえたうえで、余裕のある返済計画を立てることが大切です。
レバレッジ効果を活用してアパート経営を成功させるためには
アパート経営で、レバレッジを効かせる場合には、借入金利を低く、実質利回りを高くすることがポイントです。
くわえて、イールドギャップをできるだけ高く、実質利回りが借入金利を上回っている状態を保ちつづけられるように意識しましょう。
借入金を低金利で利用するためには、すでに付き合いのある金融機関へ打診したり、物件の購入を検討している業者に紹介してもらったりすることがおすすめです。
また、実質利回りの高い物件を探す際は、入居者の状態や、家賃の下落リスクなどを考慮して、さまざまな条件の物件を確認することが大切です。
なお、イールドギャップには、借入金の返済期間が含まれていません。
そのため、アパート経営を成功させるためには、イールドギャップだけで収益性を判断するのではなく、借入金の返済期間も考慮することも重要です。
以下の記事では、アパート経営の基本的な知識を解説しています。自己資金を抑えてのアパート経営であれば挑戦してみたいと思ったものの知識がなく不安だと感じる方は、ぜひご覧ください。
低い金利で借りる
レバレッジ効果を最大化するために大切なのは、できるだけ低い金利で融資を受けることです。借入額や期間によっては、金利1%の差で総返済額が数百万円規模で変動する場合があります。
金利が低い分だけイールドギャップが高くなるので、付き合いのある金融機関に相談したり、不動産業者の紹介を受けたりして低金利で融資が受けられるようにしましょう。
実質利回りの高い物件を選ぶ
表面利回りだけではなく、維持費・管理費・修繕費などを差し引いた実質利回りの高い物件を選ぶことも重要です。金利が低い場合と同様にイールドギャップが広がることで投資効率が高まりやすくなります。
都市部の物件は需要がありますが購入価格が高くなる一方で、地方物件は取得価格が比較的低い傾向があるため選択肢に含めてみてはいかがでしょうか。
シミュレーションする際は満室のみを想定するのではなく、空室率も含めて確認しておきましょう。
借入期間を長く設定する
借入期間を長く設定することで月々の返済額が少なくなります。これにより、キャッシュフローに余裕が生まれやすくなるでしょう。
ただし、返済期間を長くするほど総返済額が増えることは理解しておかなければなりません。物件の耐用年数や収益性も考慮し、どの程度の返済期間を設定するか検討することが必要です。
適切な工事費でアパートを建てる
アパートを建てて運用しようと考えているのであれば、イールドギャップを確保できる適切な工事費で建物を建てることが重要です。工事費が高ければそれだけ利回りが下がり、イールドギャップが小さくなってしまいます。
とにかく安くアパートを建てようと考えると耐久性やメンテナンス性に問題が出てしまう可能性もあるので、収益性を確保するためには工事費と品質のバランスを検討することが重要です。
自己資金は3割を目安にする
レバレッジ効果を得るために借入金を活用する際は、どの程度を自己資金とすべきか悩んでしまうこともあるはずです。レバレッジを活用するといっても自己資金が少な過ぎると返済負担が重くなってしまう点に注意しておきましょう。
どの程度の自己資金で始めるかは考え方によって変わってきますが、1つの目安は3割です。物件価格の3割程度の自己資金が準備できれば、物件購入に必要な頭金や諸費用をまかなえる可能性が高くなります。
また、融資審査でも一定の自己資金が評価される場合があるので、1つの目安としてみましょう。
アパート経営のレバレッジ効果とは自己資金を抑えて高い収益性を得ること
いかがでしたか?
レバレッジ効果とは、自己資金を抑えて大きな資産運用を行い、収益性を高めることです。
同じ金額の自己資金でも、借入金を利用している場合のほうが、大きな収益を生み出せることがあります。
このように、同じ金額の自己資金に対して、大きな収益を得られることがレバレッジ効果だというわけです。
なお、借り入れを行ったことで、収益が下がってしまう逆レバレッジには注意しつつ、実質利回りや借入金利などの条件を考慮して物件を選びましょう。
株式会社マリモでは、多くの物件を提供しており間取りの種類も豊富です。
また、優良物件を多く抱えており、利用される方に最適な物件を提供しています。
豊富な経験から、初めてアパート運営される方でも安心してご利用してもらえます。
弊社の木造アパート経営の情報はこちらからご確認ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要