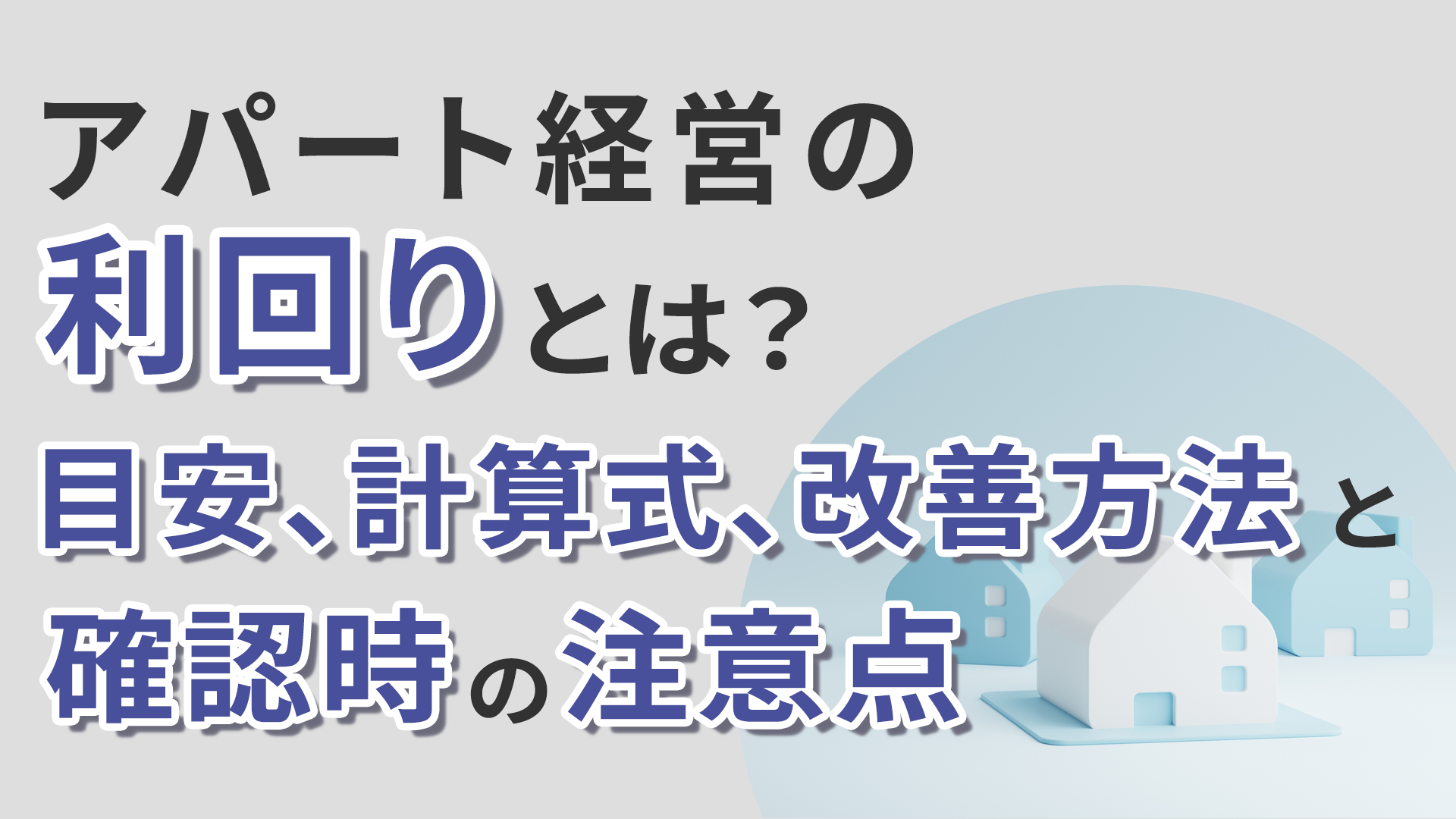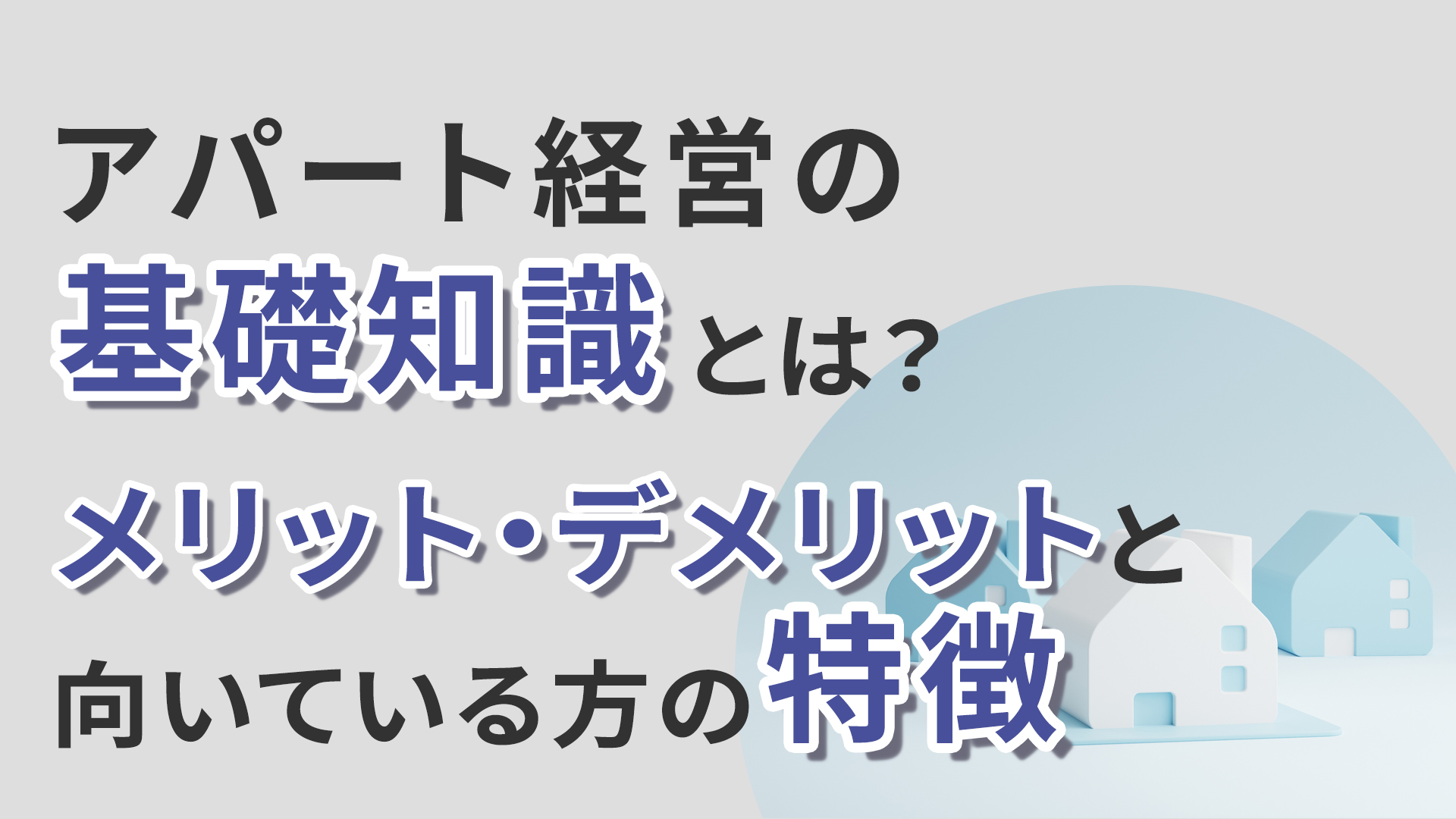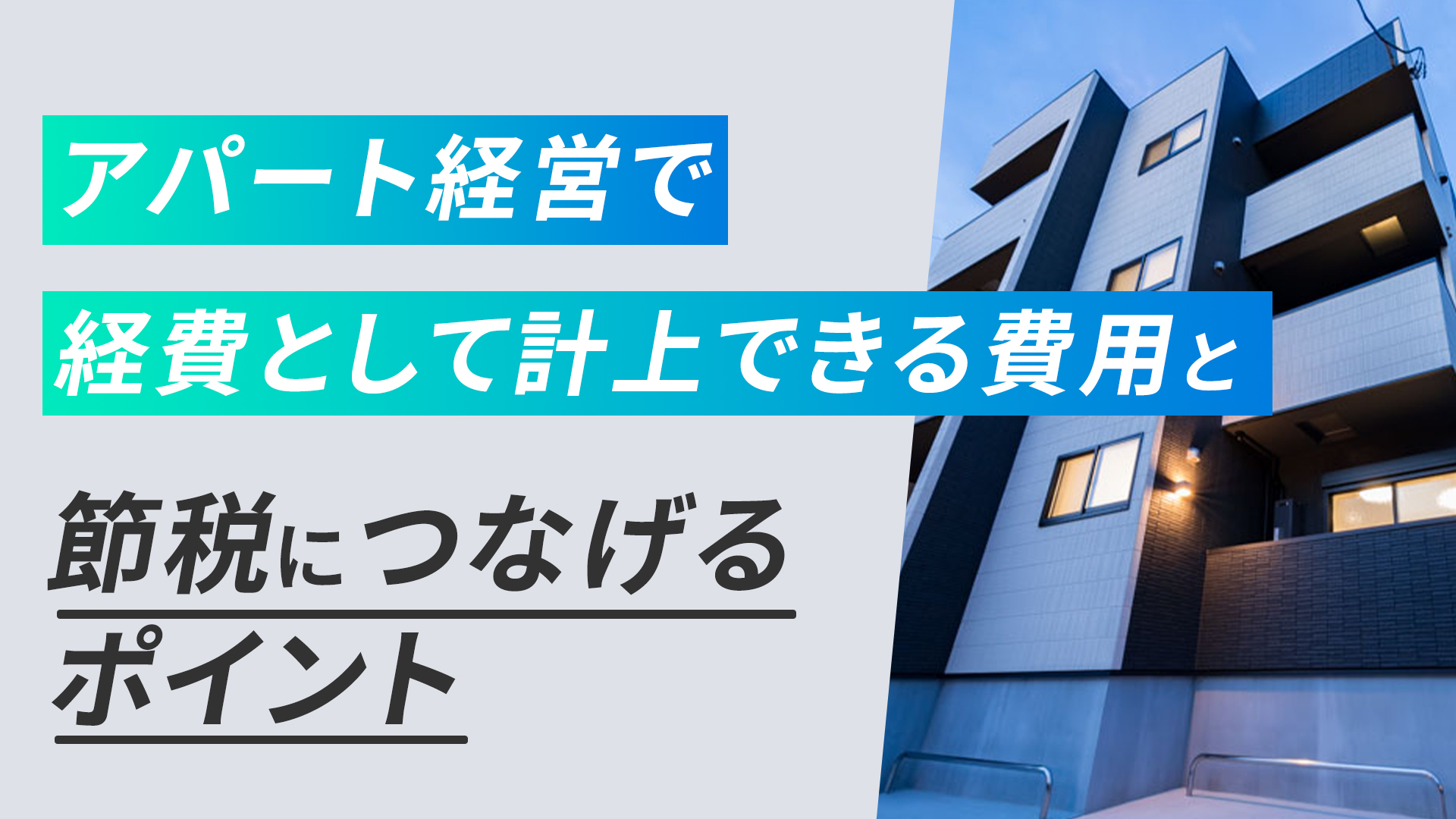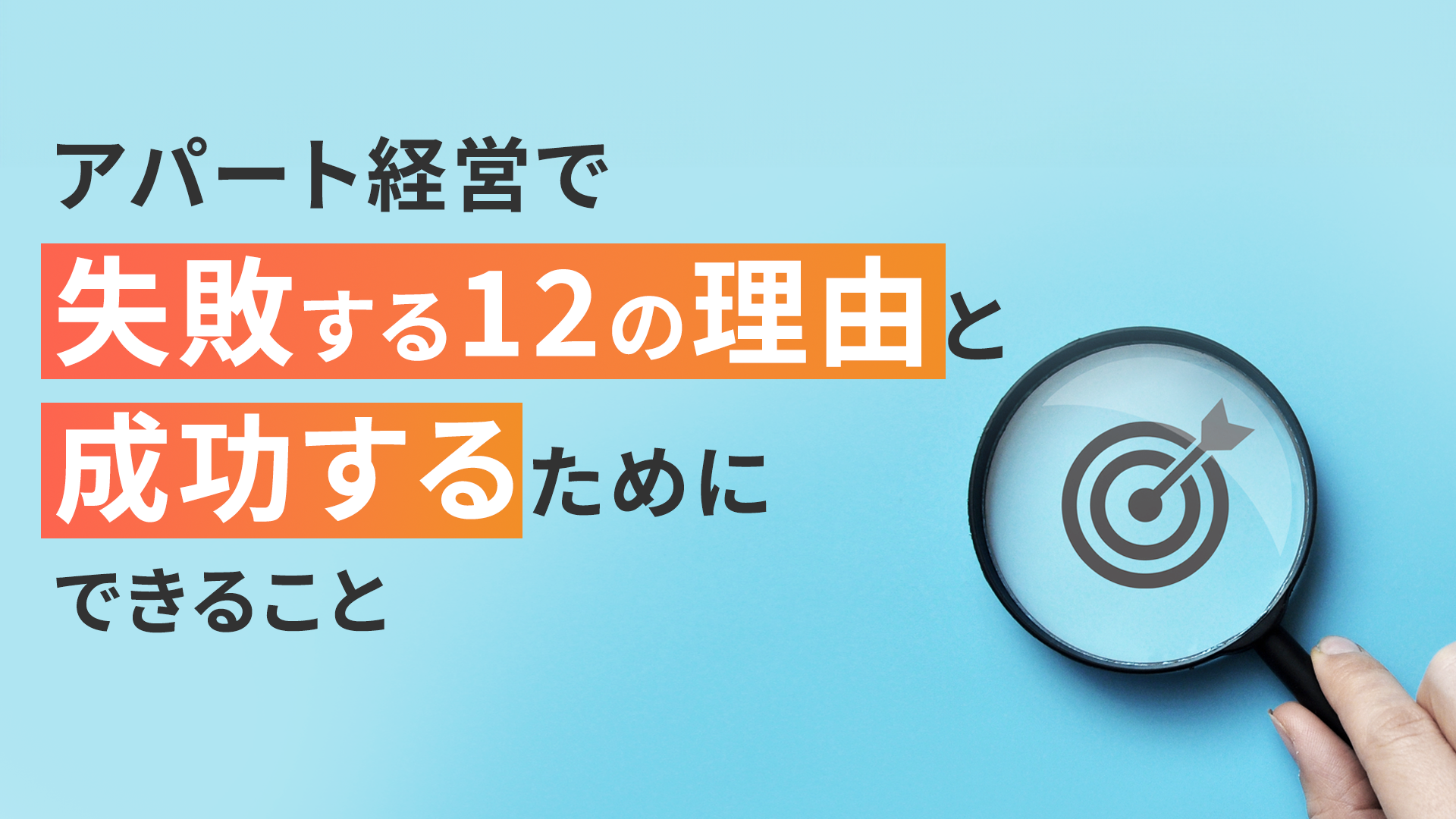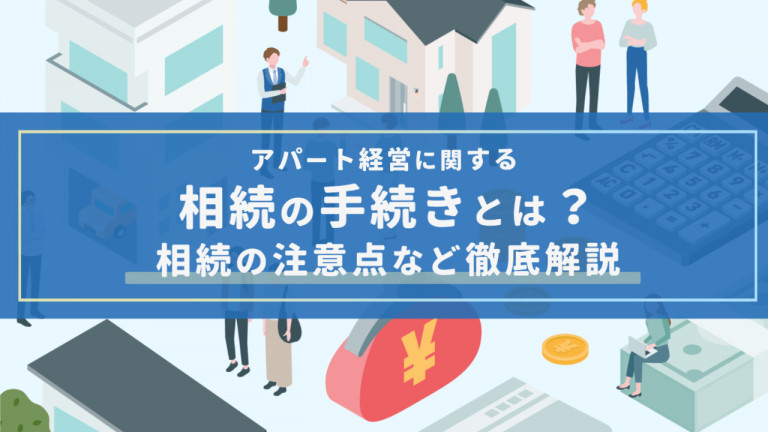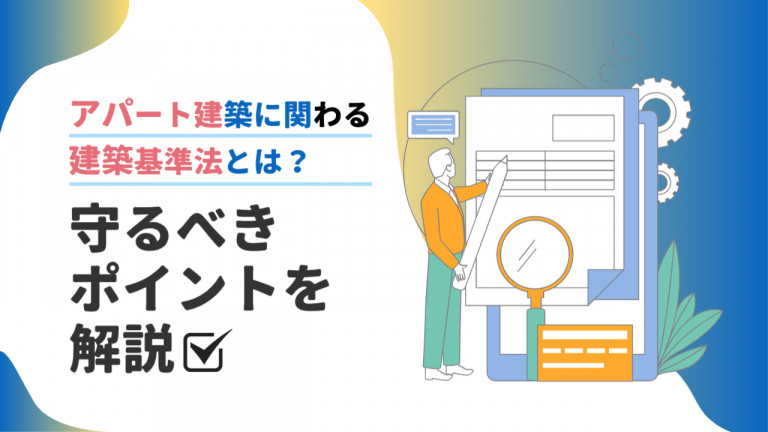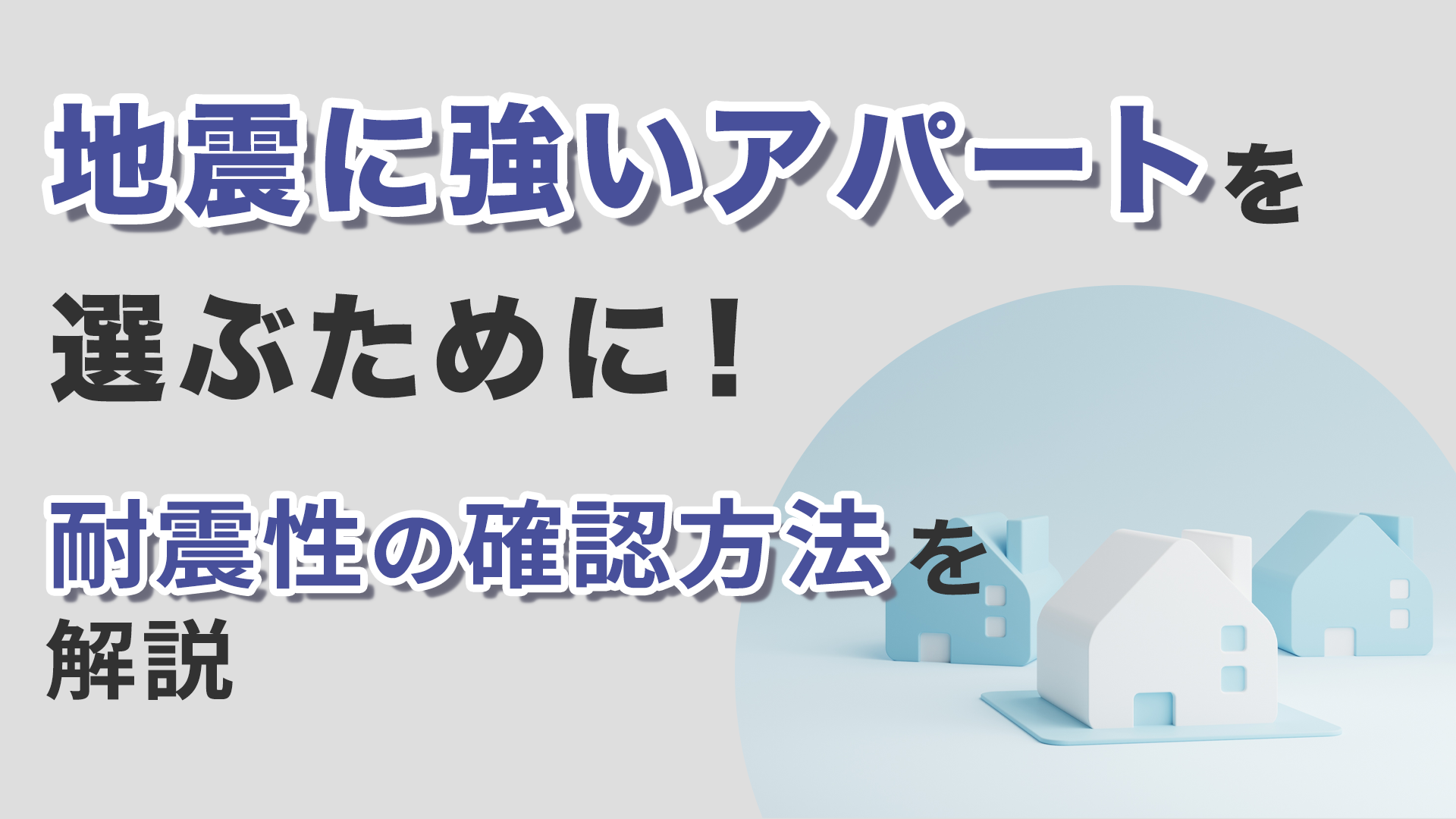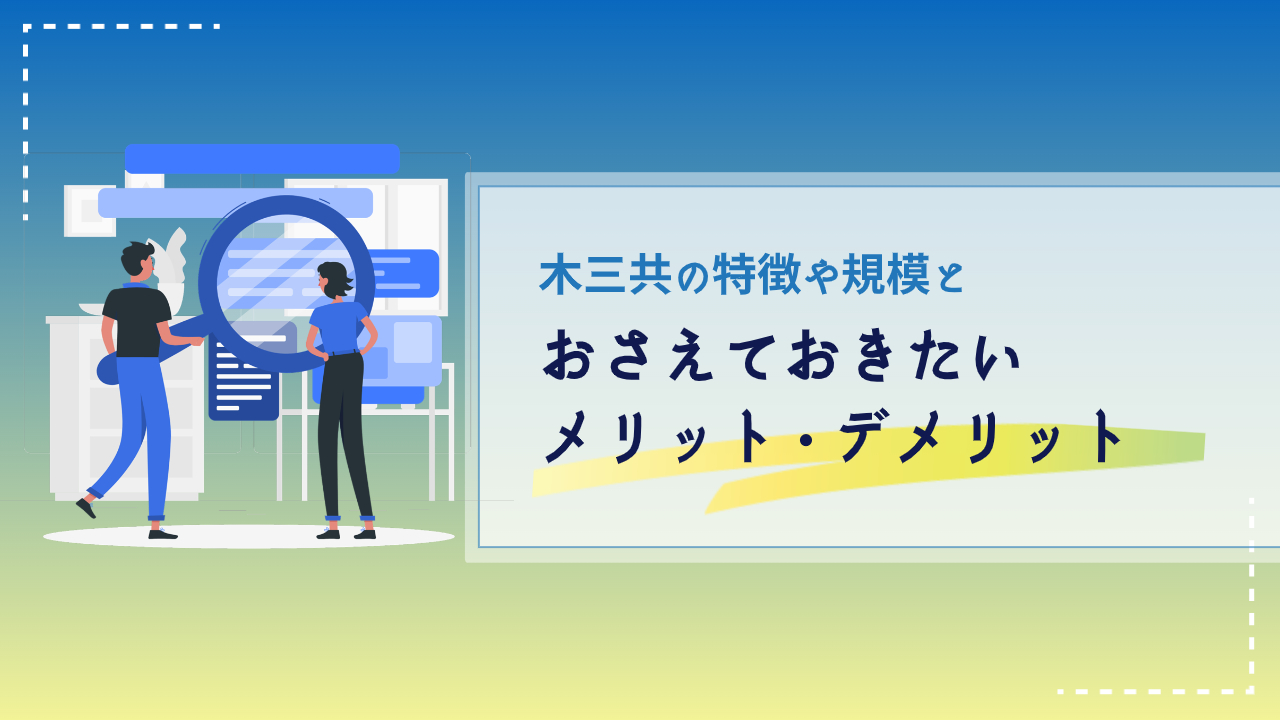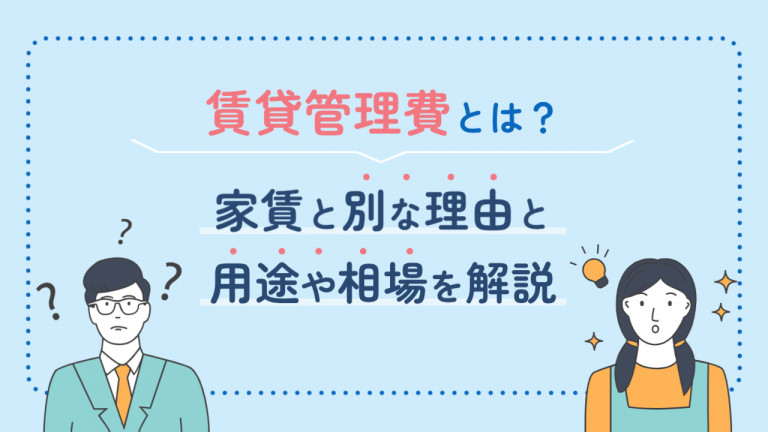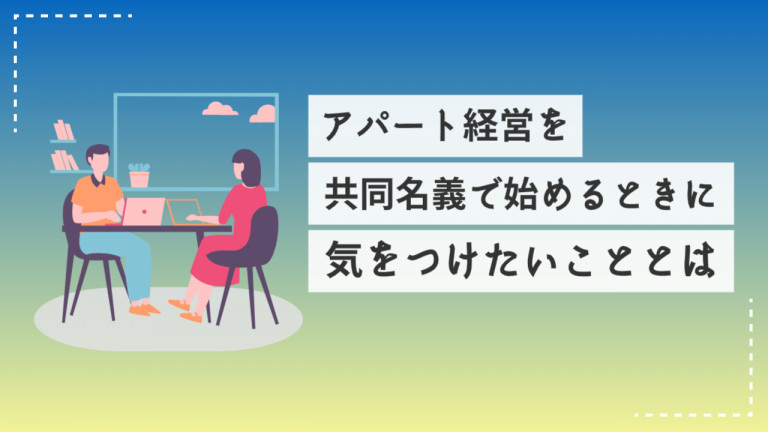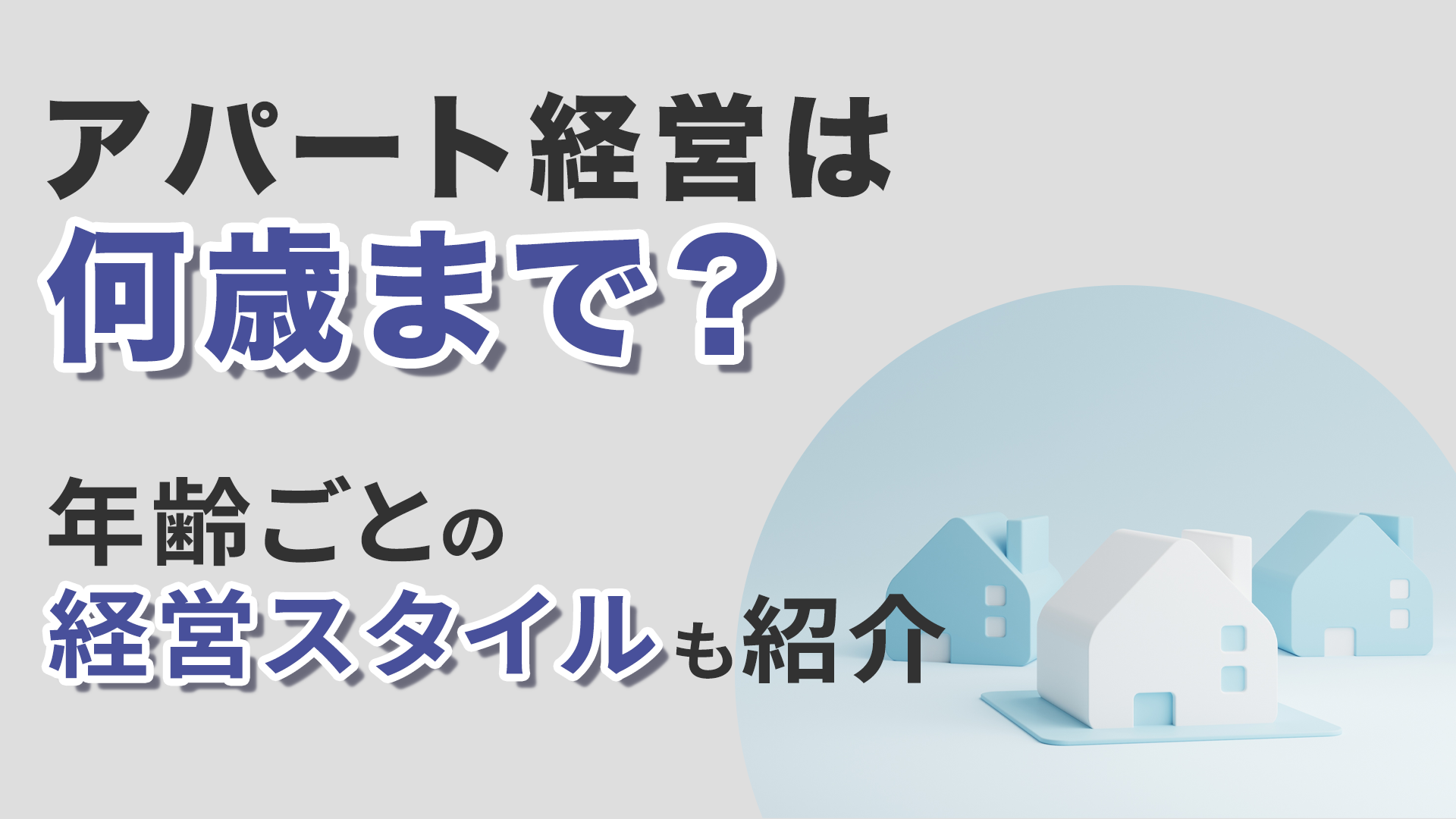
アパート経営は、老後の資金対策や投資の手段として有効です。
しかし、「アパート経営を始めてみたいけど、年齢が不安……」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、アパート経営を始める際のポイントやアパートローンの年齢制限について解説します。
アパート経営を投資手段の一つとして始めることを視野に入れている方は、ぜひ最後までお読みください。
1. アパート経営に年齢制限はある?
アパート経営に、年齢制限はありません。
アパートの経営を始める平均的な年齢層は、40~50代です。
ただし、それよりも若い20~30代から始めるとリターンを得られる期間が長くなるため、余裕をもって資産を形成できます。
反対に、平均より遅い定年後にアパート経営を始めたとしても、十分な収入を得て老後資金が築けます。
公的年金にプラスして家賃収入があれば、預貯金をほとんど切り崩さない生活が送れるでしょう。
1.1 アパートローンの年齢制限
アパートローンとは、その名の通りアパートやマンションを購入するためのローンのことです。
ほとんどのアパートローンは、ローン契約時や完済時の年齢制限が設けられておらず、満20歳以上であれば、何歳でも借り入れることができます。
ただし、団体信用生命保険に加入する際は、対象となる年齢に制限があります。
団体信用生命保険は生命保険の一種で、一般的に満15歳以上70歳未満の方が加入の対象です。
アパートローンを借り入れる際に、団体信用生命保険の加入を義務づけている金融機関はほとんどありませんが、事前に借り入れの条件を確認しておくと安心です。
契約する建築会社によっては、アパートローンの借入先を指定されることがあります。
2. アパート経営を始める年齢と経営スタイル
アパート経営は、年齢によって経営スタイルが変わります。
ここからは、年代別の課題やアパートを経営するにあたっての注意点などを解説します。
2.1 20代
20代の方は期間に余裕をもった返済プランを組めるため、ほかの年代の方よりも月々の負担を抑えられます。
健康面を理由に、ローンの審査に落ちにくいのも20代でアパート経営を始めるメリットの一つです。
繰り返しになりますが、金融機関によっては、高額ローンを契約する際に団体信用生命保険の加入が必要です。
団体信用生命保険は、傷病歴がある方や、基礎疾患がある方は加入できない場合があります。
ただし、20代であればそれらの病気にかかっていることも少ないため、ローン審査に通りやすく、ほかの年代の方よりも融資を受けやすくなります。
2.2 30代
30代は、20代よりも資産があるので、金融機関から好条件で融資を受けられる可能性が高くなります。
そのため、資産の潤沢さを活かしてローンの頭金を多く払えたり、繰り上げ返済ができたりと、アパート経営にも余裕が生まれます。
また、30代で長期ローンを組んだ場合、ローンを完済するのは定年前後となるため、老後に資金繰りを心配することもありません。
会社での給料も安定する時期なので、アパート経営を始めるのにもっとも適した年代といわれています。
2.3 50~60代
50~60代の方も、余裕のあるアパート経営が行える年代です。
長期返済ローンを活用して、月々のローン返済額を抑えることで、定年後の負担も減らせるでしょう。
退職金を含めると、ほかの年代の方よりも資産が多いので、設備の修理など突然の出費にも対応しやすくなります。
また、20~40代の方より多く頭金を用意できるため、家賃収入が毎月のローン返済額を大きく上回ることもあります。
支払う金利をできるだけ減らしたい方は、ボーナスや退職金を活用した繰り上げ返済も可能です。
2.4 60代以降
定年を迎えた60代以降は、定職に就いていない方も多いため、ほとんどの方がローンを利用できません。
これまでのボーナスや退職金などを貯蓄していれば、資産に関しては現役世代よりも余裕があります。
ローンを利用できない方は、現金で物件を購入する方が多くいらっしゃいます。
アパートなど賃貸用の不動産は、株や現金を相続するのに比べて、相続税の負担が小さくなるので、相続税対策としても有効です。
オーナーである自身が亡くなった際、土地や建物の価値は、時価よりも低く評価されます。
資産を多く蓄えている方は現金でもっておくより、不動産に換えたほうが相続税を節税できるのです。
オーナーが大きな病気にかかったり、亡くなったりしたときは、不動産という資産や家賃収入を家族に残せます。
3. 返済期間やプランを考えるうえで重要な“法定耐用年数”
ローンの返済期間を計算する際は、建物の法定耐用年数を用いるのが一般的です。
法定耐用年数とは、定期メンテナンスを欠かさずに行った新築の建物が、継続して使用できるとされる年数のことです。
法定耐用年数は建物の構造や使用用途によって、大きく異なります。
法定耐用年数の目安
構造 | 法定耐用年数 |
木造・合成樹脂造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
レンガ造・石造・ブロック造 | 38年 |
金属造:鉄骨材の肉厚が4mmを超えるもの | 34年 |
金属造:鉄骨材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの | 27年 |
金属造:鉄骨材の肉厚が3mm以下のもの | 19年 |
新築の木造アパートを購入した場合、法定耐用年数と同じ47年が返済期間です。
なお、中古アパートを購入した場合の返済期間は、“法定耐用年数-築年数”で求めることができます。
4. アパートローンの審査通過率を上げる方法
アパートローンは、年齢よりも重視される項目がいくつかあります。
審査を通過するためには、どのような対策が必要なのでしょうか。
4.1 高い収益性・利回りの物件を購入する
まずは高い収益性・利回りを見込める物件を購入することが大切です。
アパートローンの審査では、物件の利益を測る指標として、実質利回りが重視されます。
ローンの返済は、主に家賃収入からまかなうため、しっかりと収益が得られそうなアパートを選びましょう。
金融機関はアパートを審査するにあたって、空室を伴った最悪の状況を想定します。
立地や周辺の家賃相場、税金なども含めたシミュレーションの結果をもとに、ローンの返済が現実的かどうか、これらの点をシビアに審査し、融資の可否を決めます。
4.2 経営戦略を明示する
アパートローンの融資を受ける際、具体的な経営戦略を明示することが大切です。
副業であってもアパート経営は立派な事業として扱われるため、事業目的や空室リスク、収支シミュレーションを事業計画書に記載します。
事業計画書は、貸し倒れを防ぐため、融資を決めるアパート経営が実現可能かどうか判断するのに必要な書類です。
申し込み者本人が、返済を滞らせることなく、高い収益を見込める人物であるとしっかりアピールできる資料を作成しましょう。
4.3 クレジットカードの審査に通過する
20代の方は、40~60代と比べて給与所得による返済能力が高いわけではないため、アパートローンの審査に通りにくい場合があります。団体信用生命保険に加入できる健康な体だけでは、希望する金額の融資を受けるのは難しいといえます。
そのとき役に立つのが、クレジットカードの審査に通過できるだけの信用度です。
余裕のあるアパート経営のために、まずはクレジットカードの審査に通過し、融資を受けるための信用を得ましょう。
クレジットカードは、アパート経営の頭金や初期費用を支払う際に役立ちます。
また、2017年4月1日から施工された税制改正により、国税および地方税の多くはクレジットカードでの支払いにも対応しました。
そのため、不動産を購入したときにかかる固定資産税や登録免許税の支払いにもクレジットカードが使用できます。
5. 定年後にアパート経営を始める際のポイントと注意点
高齢でアパート経営を始める際は、余裕をもった自己資金の確保と出口戦略を考えておきましょう。
定年を過ぎた60代以降の方がアパートローンを組む場合、長期での借り入れはできないことがほとんどです。
高齢者は、年齢を重ねるとともに重大な病気にかかるリスクが高くなることから、金融機関は融資の可否を慎重に判断するためです。
仮に契約できたとしても、返済期間が短かったり、融資額が低くなったりする可能性があるため、自己資金は多めに確保してください。
また、購入したアパートを先々どうするか、出口戦略も立てておきましょう。
出口戦略とは、アパート経営をやめて所有する物件を売却する際に、できるだけ利益を確保するための計画のことを指します。
具体的な出口戦略は、“更地にして売却”“物件をそのまま残して売却”“自己居住用として売却”の3つがあります。
アパートの一室のみなど、購入の仕方によっては出口戦略の幅が狭まるため、先々の売却のことも考えて経営を始めましょう。
6. アパート経営を始める年齢に、制限はない
本記事では、年代によって異なるアパート経営のスタイルや、アパートローンの審査通過率を上げる方法を解説しました。
アパート経営は大変かもしれませんが、軌道に乗ると潤沢な老後資金が確保できたり、副業として安定した収入が得られたりと、メリットはたくさんあります。
しかし、アパートローンを契約する際は金融機関によっては年齢制限が設けられている場合もあるため、事前の情報収集が大切です。
株式会社マリモでは、長期経営に適した地震に強い木造アパートをご用意しております。
プロの相談員が、アパート経営に対するお悩みを一つひとつ解消していくので、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要