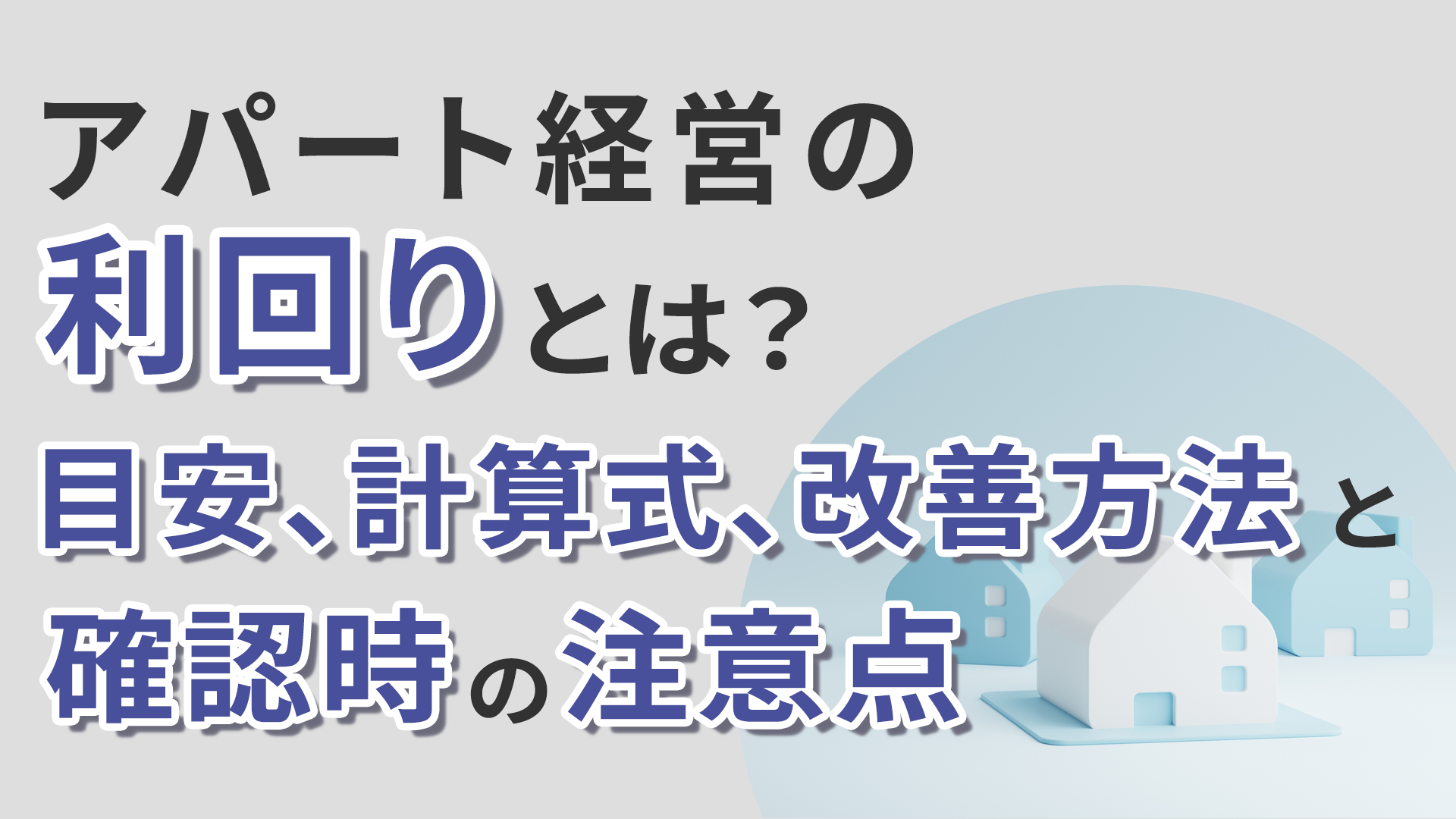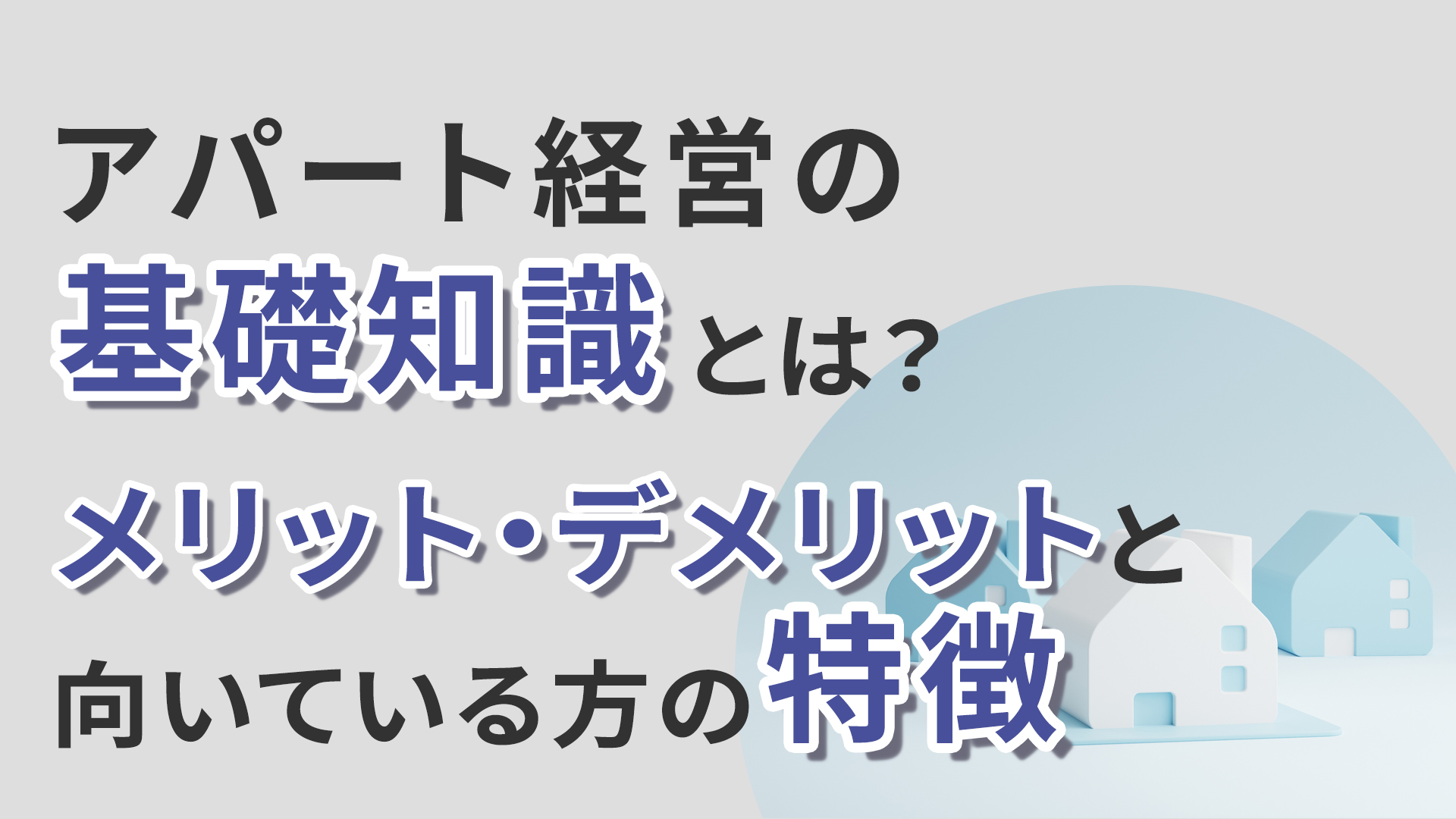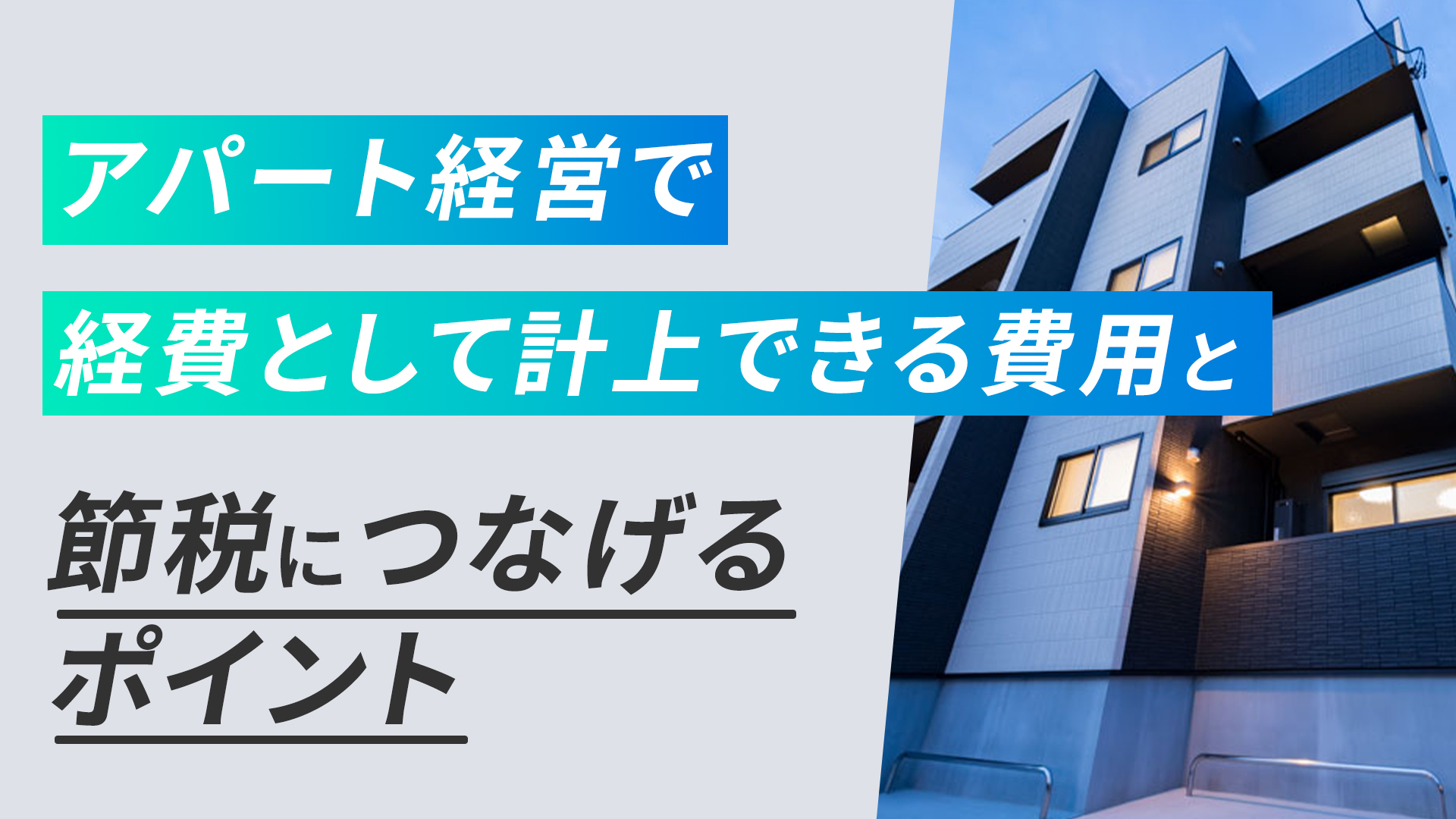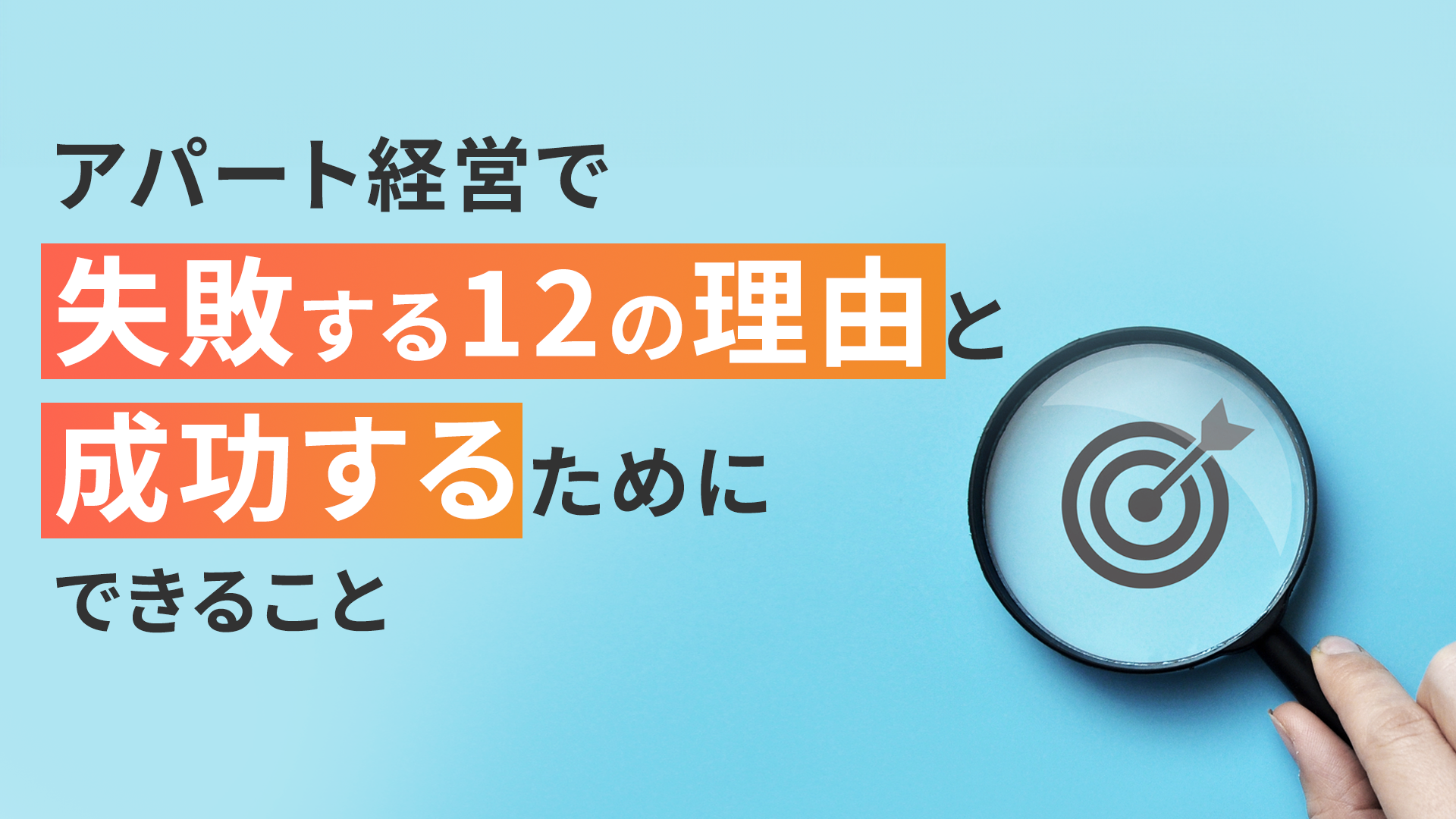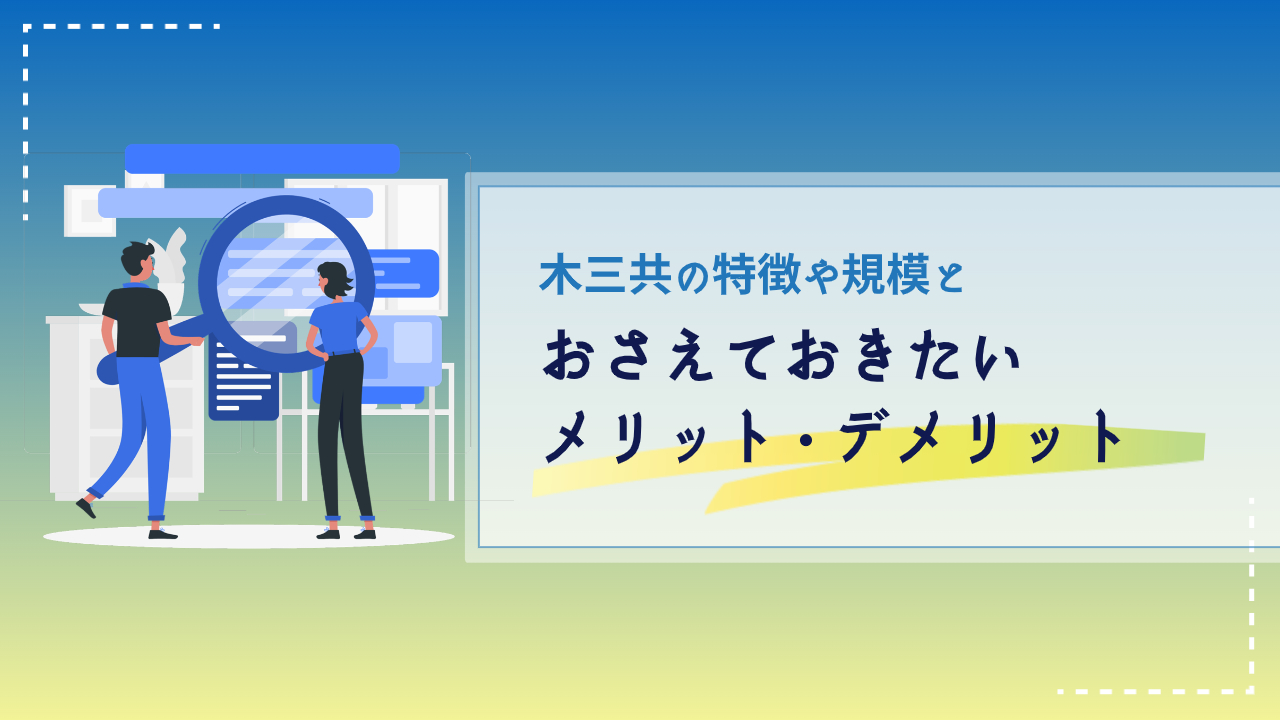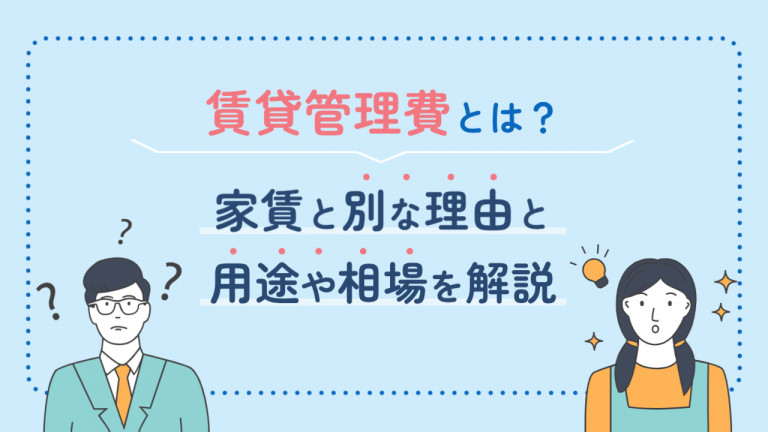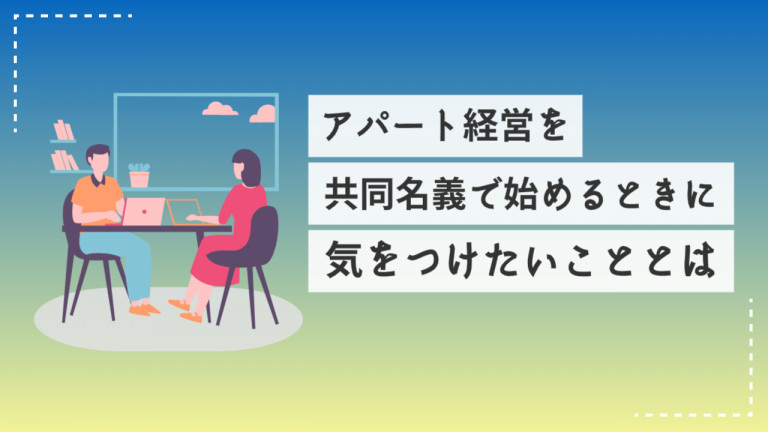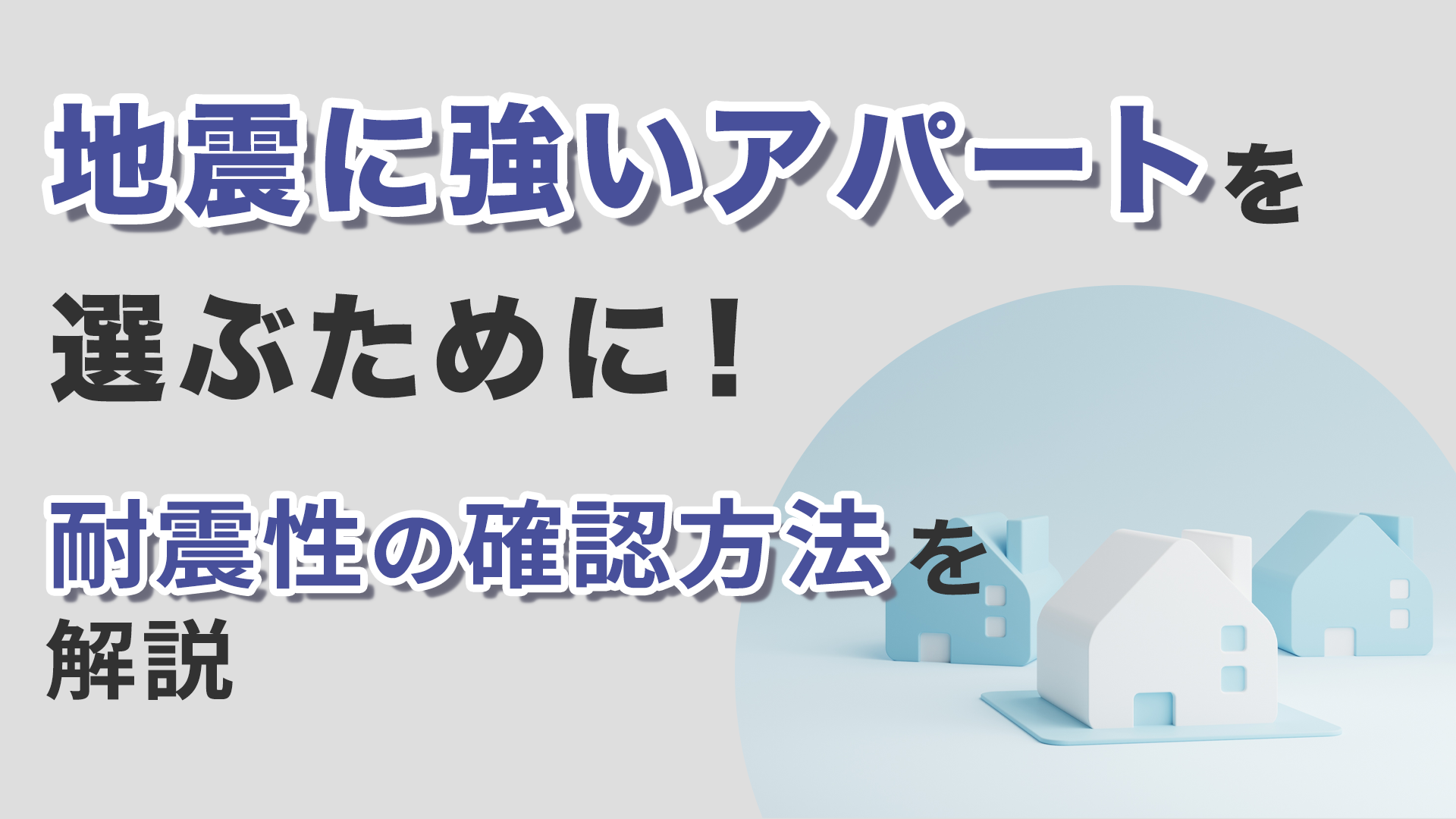
アパート経営に興味があるものの「地震による倒壊リスクが心配……」と感じ、一歩踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
地震大国である日本に住んでいる以上、この不安は尽きないものですよね。
そこで本記事では、アパートの耐震性を確認する方法を詳しく解説します。
地震から、ご自身の資産と入居者の安全を守ることができるアパートを選ぶために、ぜひ最後までご覧ください。
1. 建物の構造と耐震強度の関係
そもそも建物の構造と耐震強度のあいだに、関係性はあるのでしょうか?
「木造は地震に弱く、鉄骨造やRC造は地震に強い」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、実は、いずれの構造であっても耐震性は変わりません。
その理由は、建物構造の種類にかかわらず、建築基準法に定められた耐震基準によって、震度6強から7程度の地震に耐えられるように設計することが求められているからです。
この基準を遵守して適正な設計を行っていれば、どの構造のアパートでも、地震に対して十分な耐久力をもっているといえます。
ただし、構造によって耐震の仕組みは異なります。
以下で構造別の耐震設計の特徴を紹介しますので、ご参照ください。
1.1 木造の耐震の仕組み
木造の建物は、建物を支える“筋交い”や、水平方向からの力に抵抗する“耐力壁”をバランスよく設置することで、地震の揺れを全体に分散するように造られています。
この特徴と木材特有の“しなり”によって、地震の揺れを逃すのです。
くわえて、木造はほかの構造と比べて軽量なため、揺れ自体が小さく済みます。
1.2 鉄骨造の耐震の仕組み
鉄骨造は、骨組みに用いられる鉄や鋼の“粘り”の性質によって、地震の揺れに耐える構造です。
地震によって力が加わる際は、その粘りによって鉄骨がしなり、変形することで、地震のエネルギーを吸収します。
このため、鉄骨造は倒壊しにくく、また倒壊するにしても一気に、ということはありません。
ただし、重量があるぶん、地震の際に感じる揺れは大きくなります。
1.3 RC造の耐震の仕組み
RC造は、コンクリートの圧力に対する強さと、鉄筋の引っ張られる力に対する強さの2つの長所を活かし、地震に耐える構造です。
縦揺れにはコンクリートの圧力への耐性が、横揺れには鉄筋の引っ張りに対する耐性が働き、総合的な耐震性を高めています。
3種の構造のなかで、もっとも重量があるため、地震による揺れは大きくなりますが、倒壊しづらいのが特徴です。
2. アパートの耐震性を確認するためにみるべき基準
アパートの耐震性を確認する方法として、何年に施行された耐震基準に準じて建てられたのかをチェックすることが挙げられます。
耐震基準とは、国が法令で定めた、建物を建てる際に最低限満たすべき、地震に対する耐性基準のことです。
日本では、大きな地震が発生して被害を受けるたびに、耐震基準を強化してきました。
そんな耐震基準の変更の流れを、以下にまとめました。
耐震基準の変遷
施行年月 | 名称 | 耐震基準の変化 |
1950年5月制定 | 旧耐震基準 | 耐震基準を“震度5程度の中規模地震で倒壊・崩壊しない”と制定 |
1981年6月改正 | 新耐震基準 | 耐震基準を“震度5程度の中規模地震で損傷せず、震度6強~7程度の大規模地震で倒壊・崩壊しない”に変更 |
2000年6月改正 | 2000年基準 | 新耐震基準にくわえ、“地盤に応じた基礎設計”“基礎と柱の接合部に金具の取り付け”“偏りのない耐力壁の配置”を義務化 |
現行の2000年基準は、新耐震基準の内容に、上記の3つの変更が加わったものとなっています。
2000年6月以降に建築確認されたアパートは、すべて2000年基準に準じて建てられているため、耐震性は問題ないといえるでしょう。
なお、2000年5月以前に建てられたアパートにおいても、“耐震基準適合証明書”が交付されている場合は、十分な耐震性があることが認められています。
耐震基準適合証明書は、その名の通り、対象となる建物が耐震基準に適合していることを証明する書類です。
国土交通省が指定した機関による調査を受け、2000年基準の条件を満たしていると判断された場合に交付されます。
地震によるアパート損壊のリスクを抑えるためには、上記のように2000年基準に準じた物件を選ぶことが望ましいです。
3. 耐震基準以外で確認すべき項目
アパート経営を行う物件選びでは、耐震基準のほかにも、確認すべき項目があります。
ここでは、物件選びで確認すべき項目として、“耐震等級がいくつか”“検査済証があるか”“どのような工法が採用されているか”の3つを紹介します。
3.1 耐震等級がいくつか
耐震等級は、2000年に施行された“住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)”によって創設された、木造住宅の耐震性の評価基準です。
倒壊防止と損傷防止の2つの指標からなっており、低い順に1~3の等級がつけられます。
耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たす水準です。
耐震等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の強さがあると定義されています。
耐震等級1の時点で、十分な耐震性はあるものの、より安心感を得たいのであれば、等級2または等級3の物件を選ぶことが望ましいでしょう。
3.2 検査済証があるか
検査済証の有無も、アパートを選ぶうえでチェックしておきたい項目です。
検査済証は、地方公共団体に所属する建築主事、または民間の確認検査機関によって行われる、“建築確認”と“完了検査”の2つに合格すると交付される書類です。
建築確認では、アパートの建築計画が、建築基準法やそれに関連する法律に適合しているか否かを審査します。
そして、アパートの建築工事が完了したあとで行われるのが完了検査で、建築確認時の申請の通りに工事が竣工されたかどうかを検査します。
検査済証は、以上の2つに合格しないともらえないので、アパートの品質を証明するものといえるでしょう。
もちろん、耐震基準も考慮して建てられたかも審査・検査されるため、検査済証が交付されていれば、耐震性が十分である証となるわけです。
3.3 どのような工法が採用されているか
アパート経営の物件を選ぶ際は、耐震性を上げるためにどのような工法が採用されているのかも確認しておきましょう。
建物を守る工法は、以下の3通りです。
耐震工法
耐震工法は、建物自体の強度を高めることによって、地震による揺れを軽減させる工法です。
日本の建物で多く取り入れられている一般的な工法で、筋交いや耐力壁を入れることで揺れに抵抗し、倒壊を防ぎます。
制震工法
制震工法では、地震エネルギーを制震装置によって吸収し、揺れを軽減します。
アパートの構造部分に制震装置を設置し、地震によって建物が変形した際に、制震装置が一緒に変形することで地震エネルギーを吸収します。
震動が軽減されるうえ、建物の歪みや亀裂が入るのを防げるため、大きな揺れが繰り返し襲ってきても安心です。
免震工法
建物に震動を伝えないために、基礎と建物のあいだに免震装置を設置するのが免震工法です。
免震装置を入れることによって、地震が起きた際に建物が平行方向にゆっくりと揺れるようになります。
この効果で、建物に対する被害を防げるだけでなく、家具の転倒による二次災害を防ぐこともできます。
4. 地震被害によるアパートの倒壊リスクを軽減させる方法
経営するアパートがいかに現行の耐震基準を満たしていたとしても、地震への不安をぬぐい切れない方もいらっしゃるでしょう。
そこでここでは、アパート倒壊などによる損害を少しでも軽減する方法を紹介します。
4.1 地震保険に加入する
地震保険に加入することによって、アパートが倒壊、もしくは損壊して経営が続けられなくなったという万が一の状況に備えられます。
地震保険は、地震および津波や噴火などの地震に併発する被害に備えるための保険です。
“地震保険に関する法律”に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営しているため、どこの保険会社で加入しても保証内容や保険料は変わりません。
なお保険金額は、以下のように決まっています。
損害の状況ごとの保険金額
損害の状況 | 支払われる保険金額 |
全壊 | 設定した保険金額の100% |
大半壊 | 設定した保険金額の60% |
小半壊 | 設定した保険金額の30% |
一部損壊 | 設定した保険金額の5% |
このように、地震による損害状況に応じて保険金額が支払われます。
もしものときは、この保険金を損壊部分の修理費やアパートローンの返済に企てることが可能です。
地震による物的被害に備えたい方は、地震保険に加入することをおすすめします。
4.2 耐震補強工事を行う
すでに完成しているアパートでも、耐震補強工事を施すことで、耐震性の向上が期待できます。
主な耐震補強工事
方法 | 工事の概要 |
壁の増設 | 外壁やクロスの下地に耐震壁を設置することで耐震性を高める |
基礎の補修 | 基礎の打ち増しやひび割れの補強によって、アパートの強度を上げる |
屋根の軽量化 | 屋根に用いられている素材を、より軽いものに変更することでアパートにかかる負担を軽減する |
金具の設置 | アパートを構成する土台や柱と交わる部分に金具を設置することで、強度を補強する |
上記のなかから、ご自身のアパートに適した耐震補強工事を行うことで、地震による被害を最小限に抑えられるでしょう。
また、耐震性向上をアピールすることで、入居率のアップやアパートの資産価値上昇などのメリットも見込めますよ。
5. アパートの耐震性の判断では“何年に施行された耐震基準に準拠しているか”が重要
本記事では、アパートの耐震性を確認する方法を解説しました。
アパートの耐震性を判断するうえでは、何年に施行された耐震基準をもとに建てられているかが重要です。
2000年に施行された現行の耐震基準では、大規模地震で倒壊しないことにくわえ、接合部への金具の取り付けや偏りのない耐力壁の配置などが義務づけられています。
地震によるアパート経営のリスクを抑えるためには、この2000年基準に準じた物件を選ぶようにしましょう。
株式会社マリモでは、枠組み工法(2×4)を用いて建てられた、地震に強い木造アパートの販売を行っております。
アパート経営の不安を解消できるようにスタッフ一同全力でサポートしますので、まずはご相談ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要