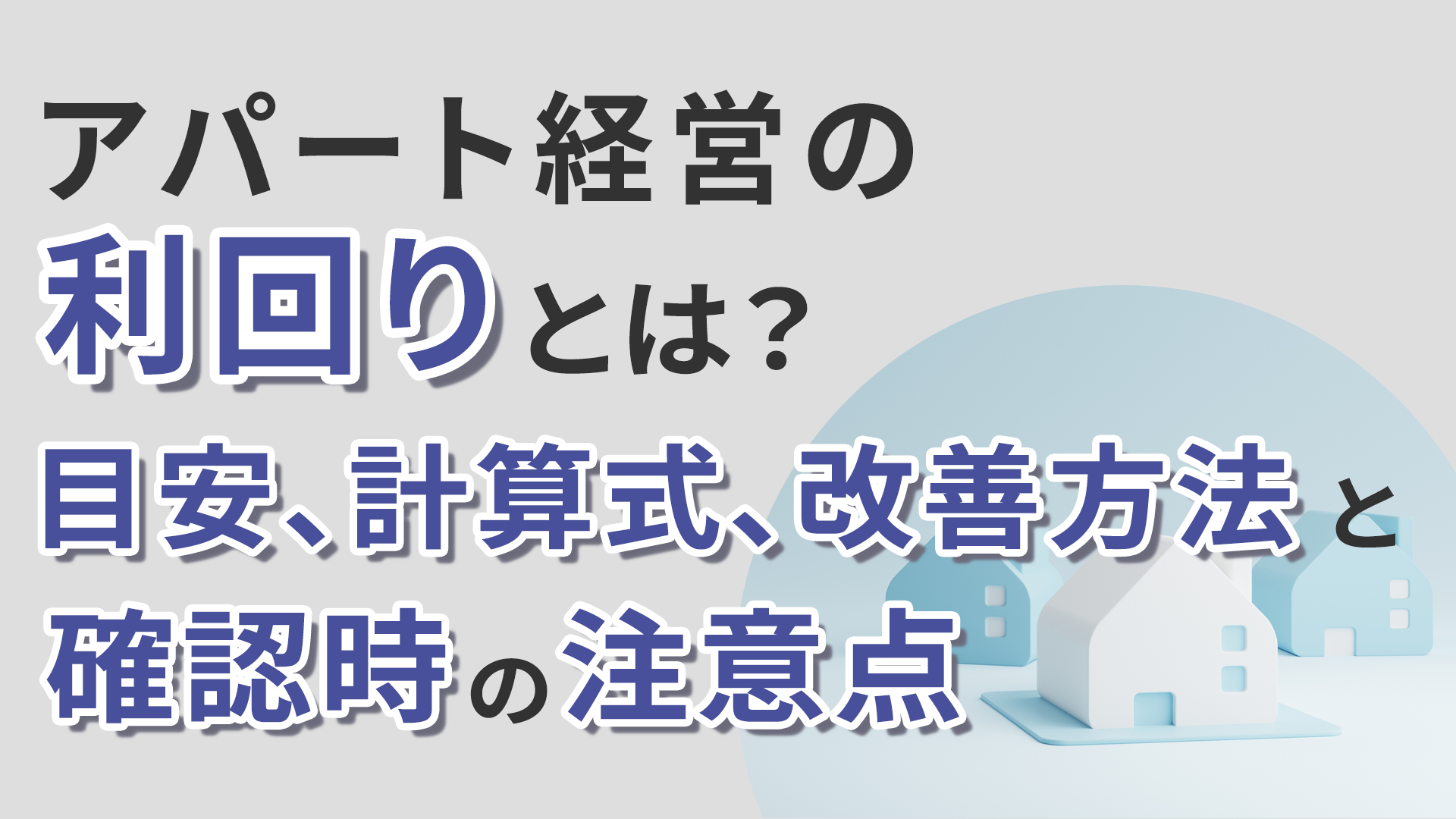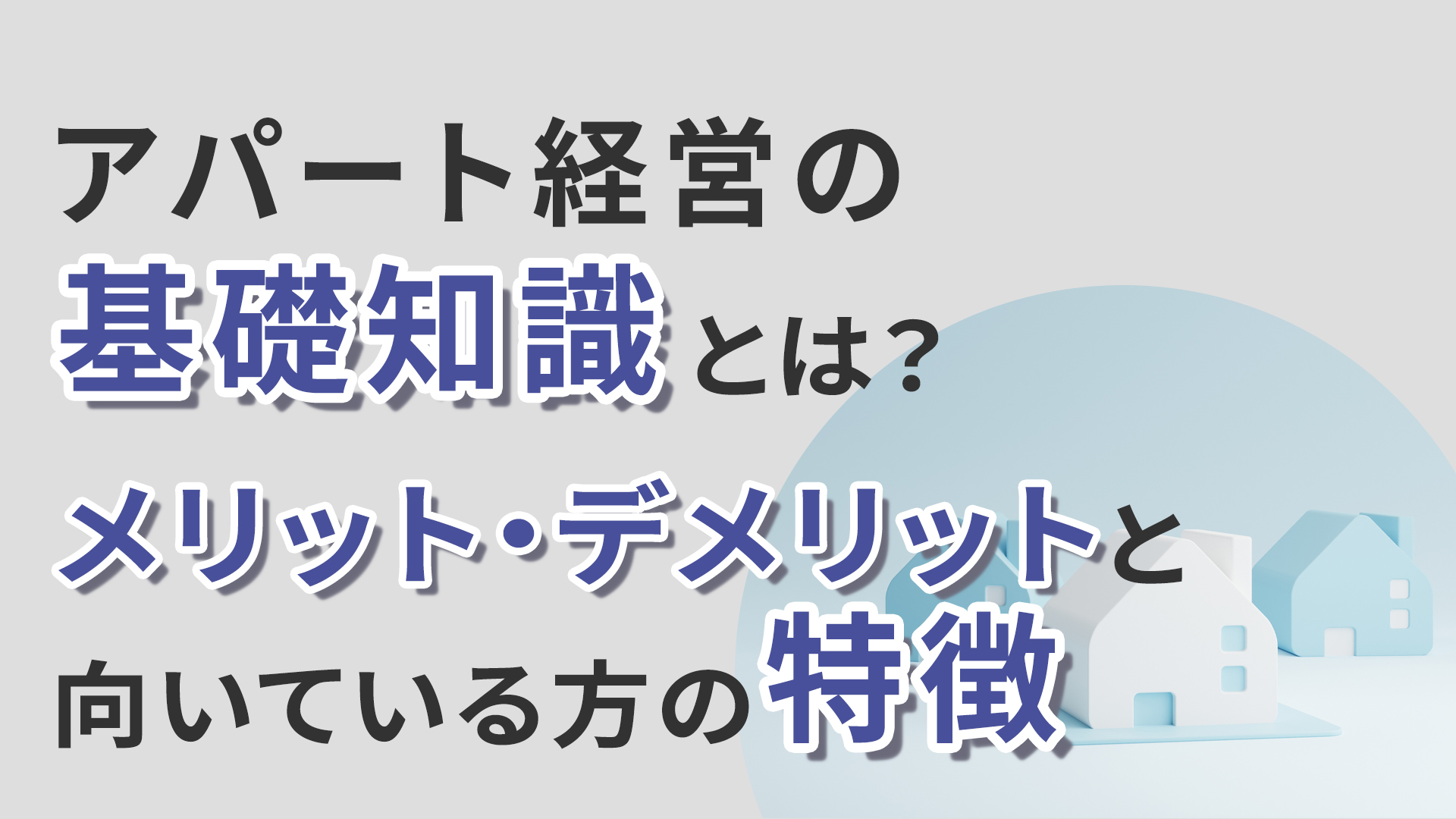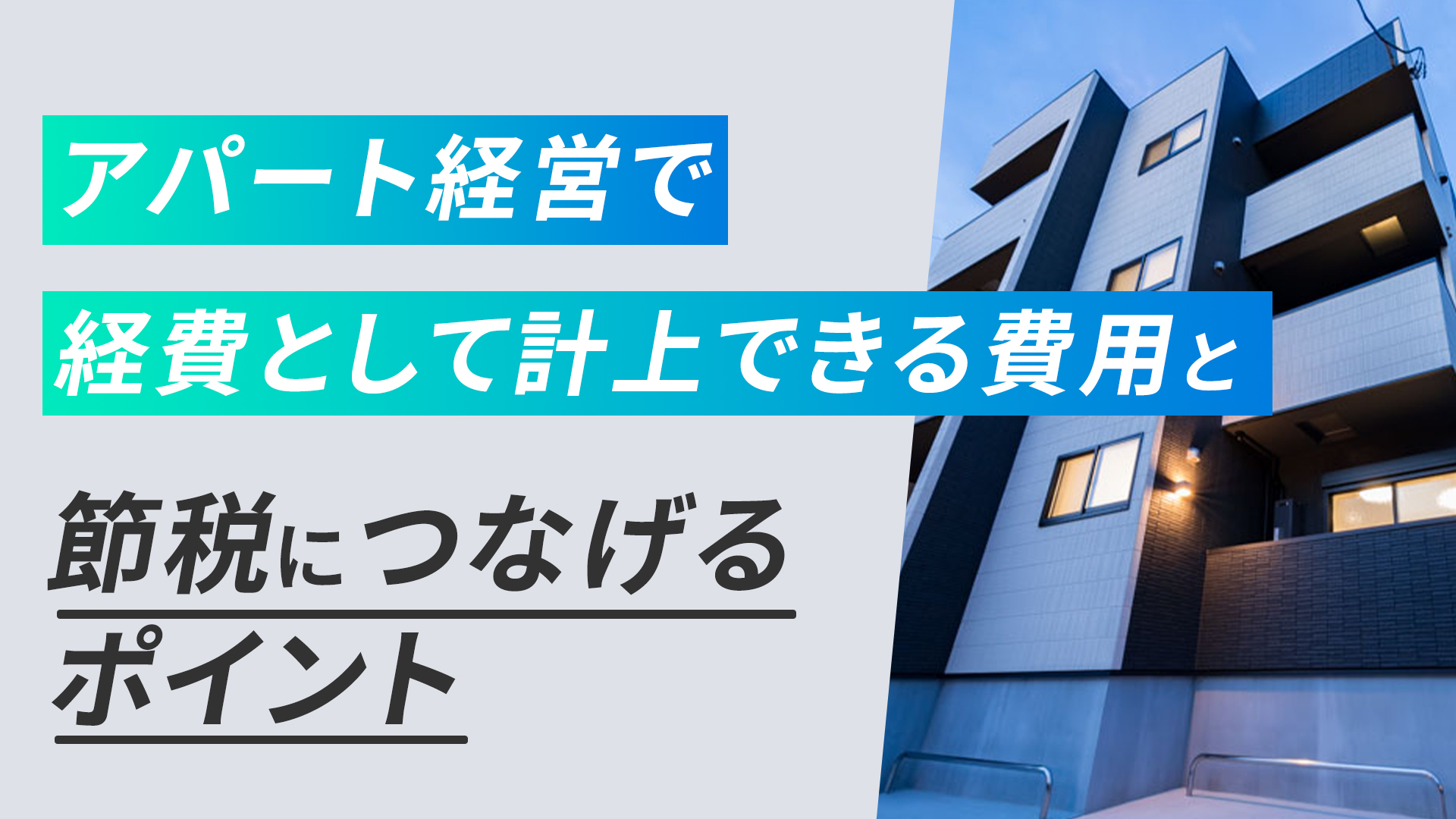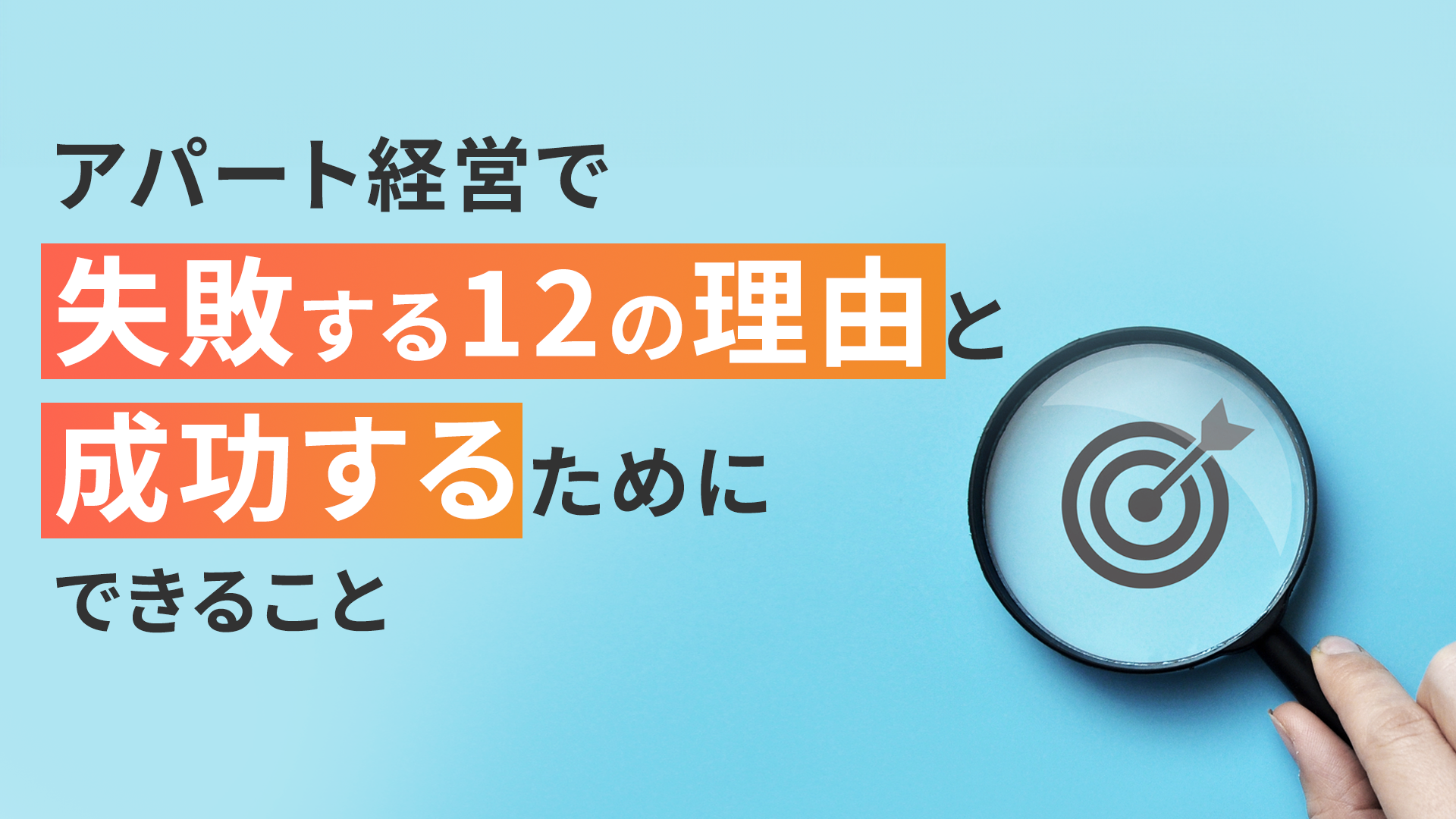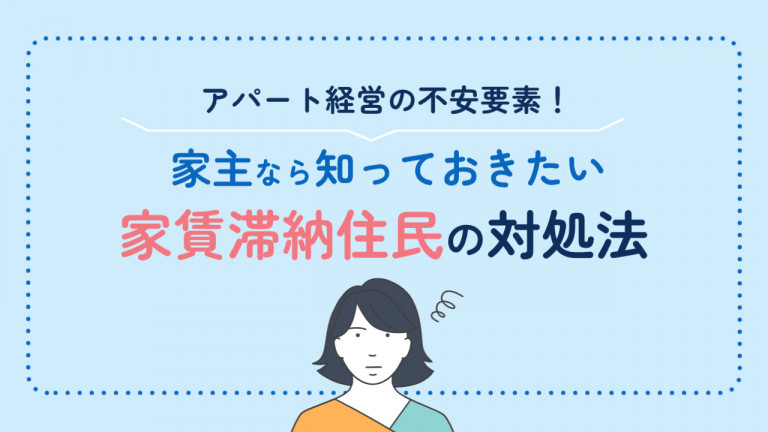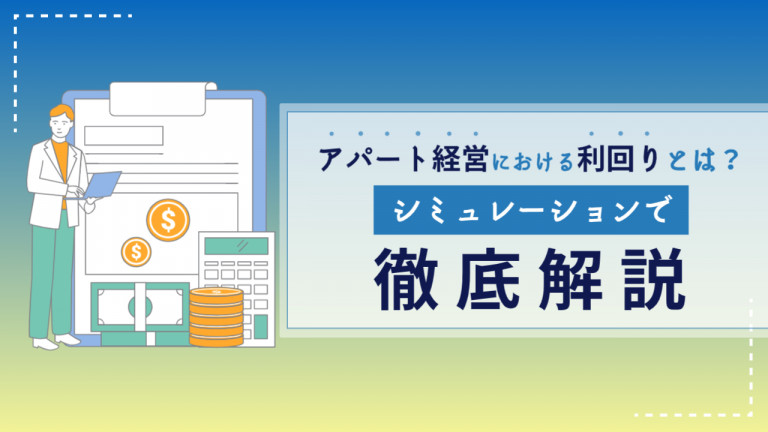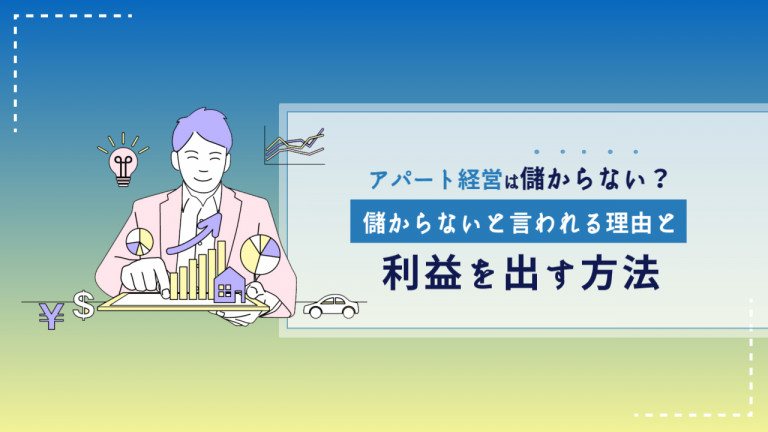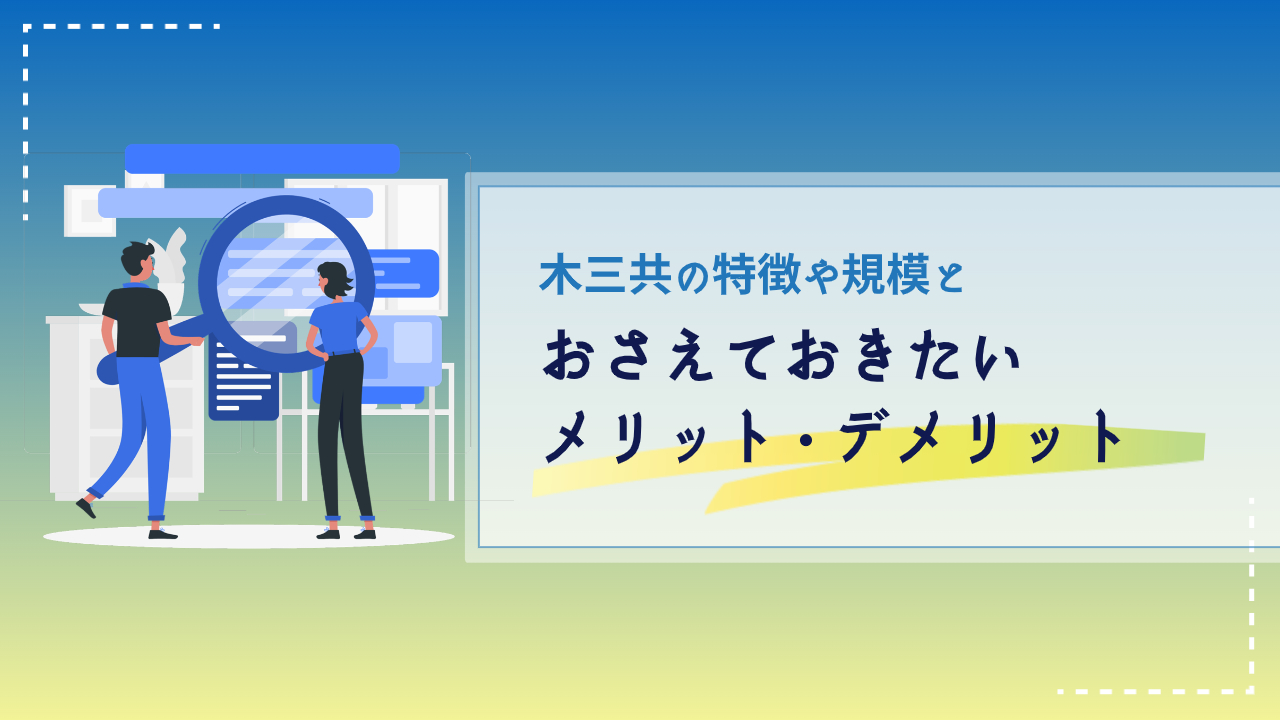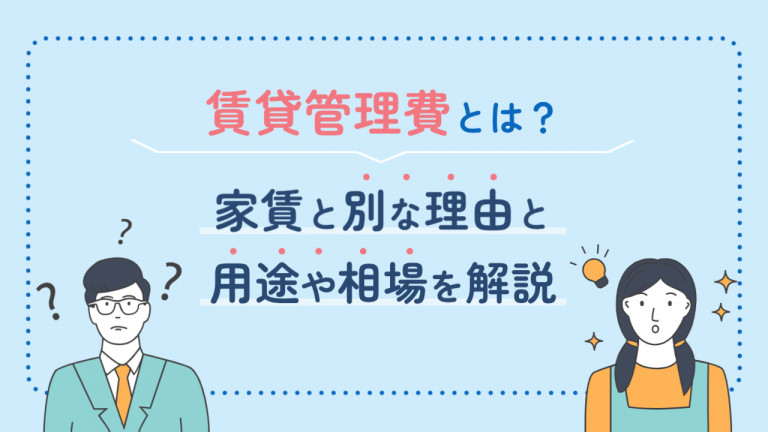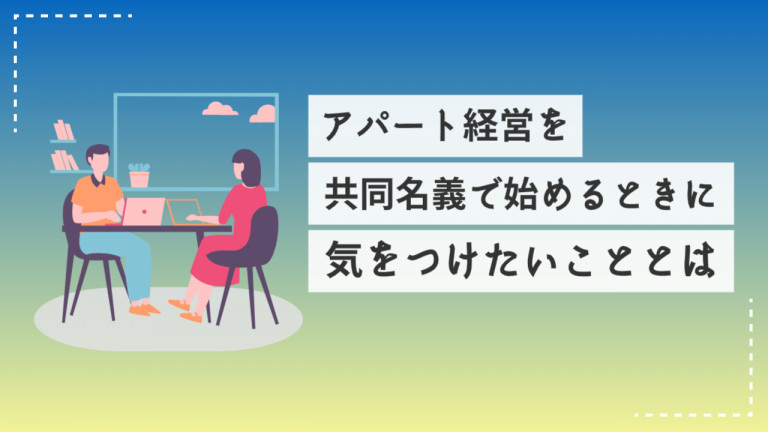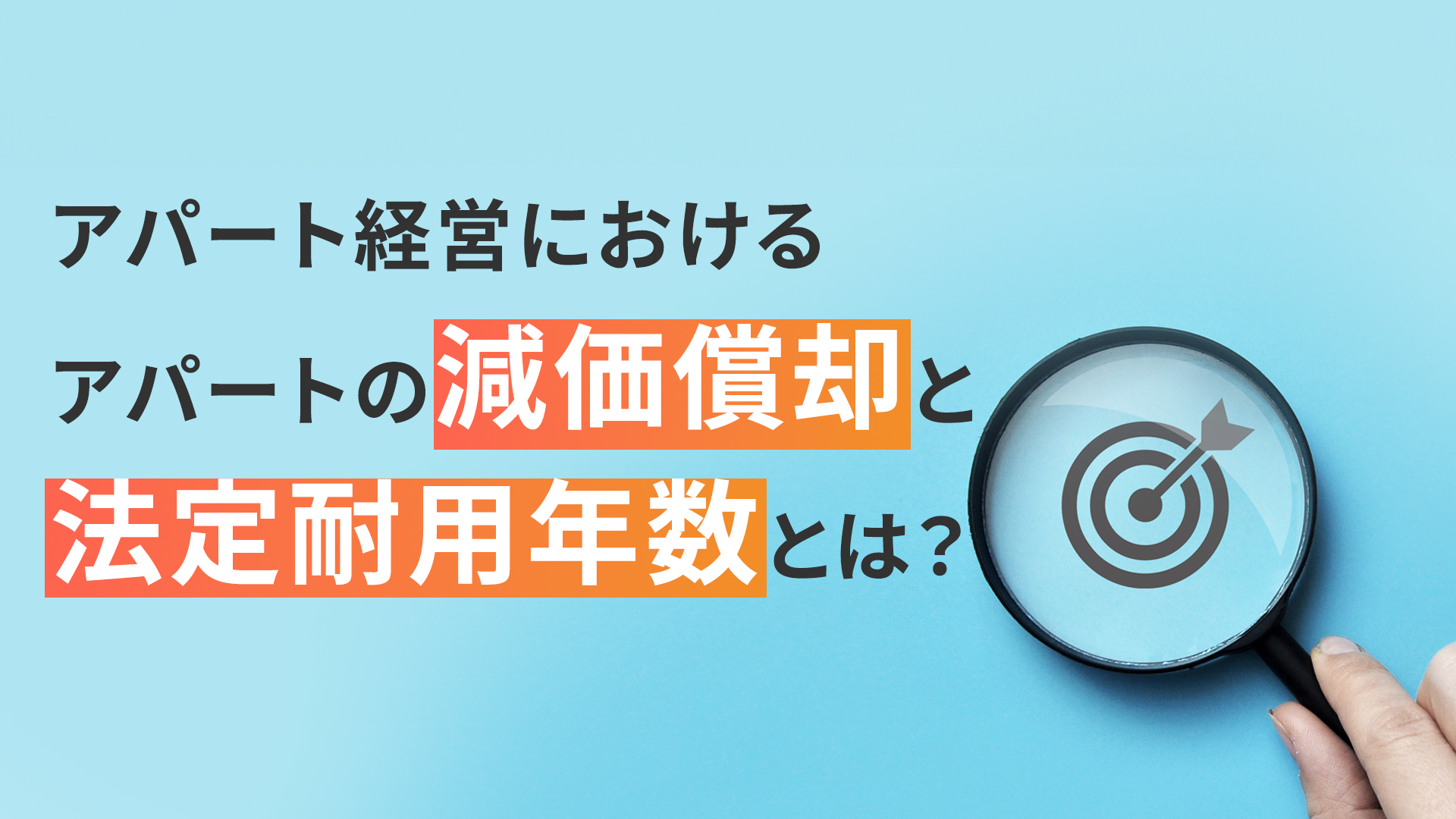
アパート経営をするにあたって、よく聞かれる言葉の一つが“減価償却”ではないでしょうか。
でも、「聞いたことはあるけど、意味はよく解っていない」という人も少なくないと思います。
ここでは、アパート経営をするうえで、欠かせない「減価償却」について解説。
アパート経営をするうえでの、記帳などに不安のある人は、参考までにぜひ読んでおいてくださいね。
1. アパートの減価償却とは
減価償却とは、資産は時間がたつにつれて、徐々に価値が目減りしていくという考え方。
例えば、建物を2,500万円で購入したとします。
キャッシュで購入した場合、その年に2,500万円分の現金が手元からなくなるでしょう。
しかし、会計上はそのような考え方はしません。
たとえ2,500万円の建物を購入したとしても、その価値は毎年少しずつ減少していく、と考えるのです。
例えば、2,500万円の建物の場合、毎年100万円分ずつ価値が減っていくという考え方。
これが減価償却です。
というのも、減価償却という考え方がないと、企業は新たな投資のために機械等を購入したら、一時的に赤字になってしまいます。
たとえ、利益が例年と変わりなくても、大型の投資を行うことで、赤字と見なされてしまうのです。
赤字となると、銀行側も融資をためらいます。
融資が下りなかったら、新たな投資や事業規模の拡大ができず、会社は成長できなくなってしまうでしょう。
そのような悪循環をなくすためにも、減価償却という考え方が取り入れられています。
以下の記事では、そもそもアパート経営とはなにか?アパート経営の基礎知識を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
2. アパートの減価償却の種類
アパート経営や投資を検討する際は、どの種類の減価償却を適用できるかを正しく理解しておくことが重要となります。
通常の減価償却のほか、少額の資産を処理する場合に向いている一括減価償却、少額減価償却資産の特例などがあります。それぞれ解説します。
2.1 減価償却
減価償却とは、一般的に用いられる会計処理方法です。
償却とは、収益に貢献した資産の取得額を費用として計上することを指します。減価償却は、設備投資などの費用を一定期間に分けて計上する会計処理です。
2.2 一括減価償却
一括減価償却(一括償却)とは、資産の取得価格が10万円以上20万円未満だった場合の選択肢です。
取得日・対応年数を考慮することなく3年で償却する方法のことをいいます。
一般的な減価償却の場合、購入した資産は固定資産税の対象です。一方、一括減価償却の場合は固定資産税の対象外となります。
一括減価償却制度を利用すると、通常より短期間で経費を計上でき、結果として税負担を軽減できるのが特徴です。節税のために活用できる制度となっています。
ただし、一括償却資産の3年均等償却の対象となっている資産は、その途中で売却や処分を行っても減価償却を取りやめることができない点に注意が必要です。
2.3 少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の資産を取得した場合に限り、一定の要件を満たすことで購入した年に全額を経費として計上できる特例のことをいいます。
対象となるのは青色申告を行っている中小企業や個人事業主です。
少額減価償却資産の特例を利用することで対応年数に基づく長期分割計上を待つことなく即座に経費化できることから、利益が多く出た年に利用すれば利益額を減らし、節税効果が得られます。
少額減価償却資産の特例は、適用できる取得時期が法律で定められていますが、これまで何度も延長されてきました。
ただし、今後制度が変更される可能性もあるため、利用を検討する際は最新の情報を確認しておきましょう。
3. アパートの法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、購入した資産を償却できる期間のこと。
法定耐用年数は、財務省が減価償却できる資産ごとに定めており、企業(所有者)は法定耐用年数に則ったうえで減価償却をしなくてはなりません。
というのも、法定耐用年数がなければ、企業(所有者)は好き勝手な年数で減価償却を行ってしまい、利益の大きなときに費用計上することで、節税することができてしまいます。
そのため、法定耐用年数に則って、減価償却し、適切な会計を行う必要があるのです。
以下、主なアパートの法定耐用年数です。
・木造……22年
・鉄骨造(軽量鉄骨:骨格材の厚みが3mm以下)……19年
・鉄骨造(軽量鉄骨:骨格材の厚みが3mmを超え、4mm以下)……27年
・鉄骨造(重量鉄骨)……34年
・鉄筋コンクリート造……47年
すべての法定耐用年数は国税庁のホームページ内の「耐用年数表」にて確認できます。
アパートは法定耐用年数を過ぎてしまうと、融資を受けられなくなる可能性があります。
木造のなかでも中古の物件はさらに法定耐用年数が短くなります。
中古の場合、減価償却の計算時の法定耐用年数は、以下の数式を用います。
◆中古物件の法定耐用年数◆
中古物件の法定耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
すでに耐用年数を経過している場合は、以下の計算式を使用してください。
◆中古物件の法定耐用年数(減価償却済み)◆
中古物件の法定耐用年数=法定耐用年数×0.2
ほかに、節税効果を期待したいのであれば、建物本体と設備・器具などの付属物を細かく分けて、減価償却する方法があります。
例えば、アパートを建てる際、以下のような設備・器具が必要になると思います。
◆主なアパートの付属物の法定耐用年数◆
・電気設備(照明設備を含む)……15年
・蓄電池電源設備……6年
・給排水・衛生設備、ガス設備……15年
・冷房用・暖房用機器……6年
これらは法定耐用年数が短いため、減価償却費を大きく計上できる傾向にあります。
キャッシュフローなどを考慮したうえで、最適な会計方法を適用していきましょう。
4. アパートの減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法は以下の2つがあります。
4.1 定額法
毎年同じ額の減価償却費を計上する方法です。
◆定額法の減価償却費の算出の仕方◆
定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率
上記の計算式にて求められます。
4.2 定率法
定率法では、年数がたつにつれて、減価償却費が安価になっていきます。
初年度の償却費が一番高く、徐々に安くなっていく方式です。
しかし償却保証額に満たなくなると、毎年同額を計上するようになります。
◆定率法の減価償却費の算出の仕方◆
定率法の減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率
上記の計算式にて求めることができます。
ただし、償却保証額を下回った場合は、以下の計算式を用いて、毎年同額を計上することになります。
◆償却保証額未満の減価償却費の求め方◆
定率法の減価償却費(償却保証額を満たさない場合)=改定取得価額×改定償却率
定額法、定率法に関わらず、最後は備忘価額として1円を残しておきます。
平成28年4月以降に取得したアパートに関しては、基本的に定額法が用いられます。
そのため、アパート経営をする方は、定額法を覚えておけばとくに問題ないでしょう。
5. アパートの減価償却費の計算例
具体的な例を挙げて、減価償却費の計算方法を説明します。
新築アパートの場合と中古アパートの場合、それぞれの計算例を見ていきましょう
5.1 新築のアパートの場合
以下の条件で新築アパートの場合の減価償却費を計算します。
【例とする条件】
・構造:木造(耐用年数22年)
・物件価格(諸経費込み):4,000万円
・物件取得日:2025年1月
・償却率:0.046
減価償却資産の償却率は以下の国税庁サイトから確認可能です。
紹介したように、平成28年4月以降に取得したアパートの減価償却費の計算で用いられるのは、基本的に定額法です。
国税庁のサイトで定額法での耐用年数22年の物件の償却率を見てみると、0.046となります。
定額法の計算式は「取得価額×定額法の償却率」なので、この例を計算すると以下の通りです。
減価償却費=4,000万円×0.046=180万円
2025年に取得した場合、22年間、毎年180万円を減価償却費として計上できます。
5.2 中古のアパートの場合
中古アパートの場合は、新築とは減価償却費の計算方法が異なります。
残存耐用年数をもとに計算する必要があるため、注意が必要です。
例として、以下の条件の中古アパートを購入した場合を考えます。
【例とする条件】
・構造:木造(耐用年数22年)
・物件価格(諸経費込み):3,000万円
・築年数:10年
・物件取得日:2025年1月
耐用年数を超えていない中古物件の場合、アパート取得時の耐用年数は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」という計算式で求められます。
この例の場合、計算は以下の通りです。
アパート取得時の耐用年数=(22-10)+10×0.2=14年
耐用年数14年の償却率は0.071なので、減価償却費は以下の通りとなります。
減価償却費=3,000万円×0.071=213万円
2025年に取得した場合、14年間、毎年213万円を減価償却費として計上できます。
次に、築年数が法定耐用年数を超えている場合(すでに減価償却が終了している場合)についてです。
耐用年数22年の木造アパートで、築年数が25年の場合を例に計算してみましょう。
築年数が法定耐用年数を超えている中古物件の場合、耐用年数は「法定耐用年数×0.2」で求められます。
耐用年数を計算すると、以下の通りです。
22年×0.2=4年(小数点以下切り捨て)
耐用年数4年の場合の定額法の償却率は0.250のため、減価償却費は以下の通りです。
減価償却費=3,000万円×0.250=750万円
4年間、毎年750万円を減価償却費として計上できます。
6. アパート経営で減価償却を行う際のメリット
アパート経営で減価償却を行うことにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。
以下3つのメリットがあるため、減価償却を行ったほうがよいといえます。
6.1 メリット①計画的にアパートを管理できる
減価償却を行うことで、毎年一定の費用を経費として計上できるため、修繕時期などの見通しを立てやすくなります。
その結果、計画的にアパートを管理できるようになるでしょう。
経営者は資産価値が減少する期間を正しく把握できるようになることから、投資判断や資金調達にも役立ちます。
6.2 メリット②キャッシュフローの改善を図れる
キャッシュフロー(お金の流れ)の改善にも、減価償却は有効です。
アパート経営で利益が増えると税金も増えますが、減価償却によって利益を圧縮し、税負担を抑えることが可能です。
6.3 メリット③法人税の負担を軽減できる
法人税を計算する際は、家賃収入から必要経費を差し引いた所得に税率を掛けます。
そのため、減価償却によって所得を抑えることで、法人税の負担を軽減できる点がメリットです。。
7. 減価償却費を多く計上するポイント
減価償却費を多く計上することで、節税効果が高まります。
より多くの減価償却費を計上するためには、「中古のアパートを選ぶこと」と「建物と附属設備それぞれの法定耐用年数を適用すること」の2点が重要です。
7.1 ポイント①中古のアパートを選ぶ
中古のアパートを選ぶことで、減価償却費を多く計上できます。
中古アパートの法定耐用年数は、先ほど紹介した通り「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)」という式で計算できます。
新築と比較すると短い年数で減価償却できるため、1年あたりの減価償却額を多く計上できます。
ただし、耐用年数満了後にローンが残っている場合は、経営が厳しくなる可能性があるため注意が必要です。
7.2 ポイント②建物と附属設備のそれぞれの法定耐用年数を適用させる
建物全体をまとめて減価償却するのではなく、建物と附属設備それぞれの法定耐用年数を適用することで、減価償却費を多く計上できます。
設備部分は建物よりも耐用年数が短いものが多く、区分して計算することで短期間に多くの減価償却費を計上できるからです。
ただし、所有者が工事の明細を確認してそれぞれの法定耐用年数を調べる手間はかかります。
8. アパートの減価償却を終える前にできる対策
アパートの減価償却が終了すると、帳簿上の経費が減少し、課税所得が増えて税負担が重くなります。
そこで、減価償却を終える前にできる対策を確認し、今後に備えておきましょう。
8.1 対策①売却する
アパートを売却するのも一つの方法です。減価償却が終了している物件は、購入時に融資を受けにくくなるだけでなく、金利も高くなる傾向があるため、売れにくくなる点に注意が必要です。
減価償却を終える前に売却することで、買い手を見つけやすくなり、資産を効率的に現金化できるようになります。
8.2 対策②建て替える
古くなった建物は入居者の募集力が低下するため、減価償却が終了するタイミングでアパートを建て替えるという選択肢もあります。
新築物件になれば、法定耐用年数に基づく減価償却が再び行え、継続して経費に計上できます。
ローン返済を終えている場合は、新たにローンを組むことも検討できます。
8.3 対策③法人化する
個人経営の場合、所得が増えるほど税率も上昇します。一方、法人化すると法人税率が適用されるため、減価償却が終了する前に法人化することで節税につなげることが可能です。
手続きや法人化の維持費はかかりますが、長期的な資産運用を考えている場合は選択肢の一つとなります。
8.4 対策④新たな物件を購入する
新たな物件を購入すれば、そのアパートは再び減価償却の対象となります。
不動産による収益は損益通算によって他の所得と合算されて総課税所得を減らせるため、物件の購入は節税対策にも有効です。
特に中古アパートの場合は、短期間で多くの減価償却費を計上できる点がメリットです。
9. 減価償却終了後も長期的に利益を得るポイント
減価償却が終了したアパートは価値がなくなってしまうのでしょうか?
そんなことはありません。
確かに、法定耐用年数を超えると、毎年の減価償却費は計上できなくなるため、節税効果といった面では期待できなくなるかもしれません。
そのため、法定耐用年数が過ぎた時点で売却などを検討する大家さんも少なからずいます。
しかし法定耐用年数の過ぎたアパートは融資を受けることが難しく、買い手がなかなか見つかりません。
買い手が現れなければ、更地にして売却するしかありませんが、解体するのにも費用がかかります。立地が良ければ、建て替えもできますが、すでに入居者がいる場合、一時退去などの問題が持ち上がり、実行に移すのはなかなか大変でしょう。
法定耐用年数が過ぎたアパートであっても、実際に入居者が満足して住むことができれば、家賃収入を生み出してくれます。
法定耐用年数は、建物の使用期限(寿命)を定めているわけではありません。
近年の建物は以前より堅固で丈夫な傾向にあり、法定耐用年数を超えても、とくに問題ないものもたくさんあります。法定耐用年数を過ぎても、入居者が満足して住み続けられるアパートづくりをおすすめします。
そのために重要なのが「修繕」と「メンテナンス」です。
建物は、手入れをしなければ、どんどん荒れ果ててしまいます。
しかし、管理が行き届き、常にきれいに保つことで、いつまでたっても清潔なアパートをキープできるのです。
10年に1度の大規模修繕だけでなく、日頃から掃除や器具の修理、空気の入れ替えなどまめに行いましょう。
ほかにも3~5年に1度くらいは、外壁塗装などのチェックを行えるといいでしょう。
10. アパートを経営するなら減価償却の知識は必須
いかがだったでしょうか。アパート経営やアパート投資をする上で理解しておきたい減価償却や法定耐用年数について解説しました。
具体的な計算方法についてもご理解いただけたのではないでしょうか。
減価償却は税金対策にとどまらず、経営の安定性にも直結する重要な仕組みです。正しく理解しておくことが欠かせません。
株式会社マリモでは、地方都市を中心に耐久性とデザイン性を兼ね備えた投資用木造アパートを提供しています。アパート経営を始めたいとお考えの方は、弊社の木造アパート経営の情報からお気軽にご相談ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業本部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
会社概要