アパート経営を始めようとする方のなかには、「大家は火災保険に入るべき?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
突然の火災でアパートが損壊すると、多額の損害を被ってしまいます。
そんな、万が一の事態に備えるためにも、火災保険について理解を深めることが大切です。
今回は、火災保険に入るべき理由や、火災保険の利点などを、詳しく解説します。
この記事を参考に、健全なアパート経営を実現していきましょう。
1. 大家も火災保険に入るべき?
一般的に火災保険とは、入居者のみが加入するイメージが強いですが、実際は、賃貸物件の大家も火災保険に加入する必要があります。
火災や災害などで建物に損傷が発生した場合、損害を被るのは建物を所有する大家であるためです。
そのため、賃貸物件においては、大家が火災保険に加入し、入居者は、自分の家財を補償する家財保険に加入するのが一般的です。
以降で、火災保険について詳しく説明していきます。
2. そもそも火災保険とは?
火災保険とは、損害保険の一種で、火災などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償する保険です。
火災が起こり、建物や家財が損傷した場合、賃貸経営が立ち行かなくなり、金銭的に大きなダメージを負うことになります。
家の建て直しや、家具の買い直しには、さらに高額な費用がかかることでしょう。
火災保険は、そのような火災による経済的なリスクをカバーしてくれます。
また、意外と知られていませんが、火災保険は名称とは裏腹に、火災以外の損害にも対応します。
たとえば、水害や台風、落雷のような自然災害や、爆発や盗難のような人為的な被害にも適用されるのです。
火災保険は、私たちが安心して日々を過ごすうえで、欠かすことのできない“備え”といえます。
2.1 補償対象
火災保険では、補償対象を、“建物のみ”、“家財のみ”、“建物+家財”の3つのなかから選択できます。
詳細は、以下の表にまとめたのでご覧ください。
補償対象の内訳
補償対象 | 内容 |
建物のみ | 建物、玄関ドア、窓、門、塀、垣、庭木、物置、車庫、冷暖房設備など |
家財のみ | 家具、衣類、家電製品、自転車、原動機付自転車など |
建物と家財 | 建物のみ+家財のみの内容 |
上記はあくまでも一例であり、保険会社によっては詳細が異なるので注意してください。
また、火災保険には、さらなるリスク回避のための“特約”というオプションがあります。
大家ならではのリスクに備えた特約を、付帯しておくことが望ましいでしょう。
以降で、大家が加入すべき特約について説明します。
2.2 施設賠償責任特約
火災保険に入る際は、“施設賠償責任特約”を付帯してはいかがでしょうか。
この特約は、建物が原因による入居者のケガなどで、損害賠償責任を負った場合に適用されます。
たとえば、施設のエントランスが破損しており、入居者がそこでつまずいて骨折してしまった場合などが当てはまります。
2.3 家賃収入特約
“家賃収入特約”は、火災などの事故、あるいは災害で賃貸経営が不可能となり、家賃収入が得られなくなった場合に、その損害を補償するものです。
ただし、いつまでも補償が受けられるわけではなく、契約時に決めた復旧期間が限度です。
ですので、その期間に建物の修復や入居者の再募集などを行い、経営を立て直していきましょう。
2.4 家主費用特約
“家主費用特約”は、アパートで住居者が病気や、不慮の事故などで亡くなってしまった場合に、原状回復費用、遺品整理費用などが補償されます。
また、上記の作業に伴う空室期間が発生した場合の家賃損失費用も補償されます。
3. 入居者向けの特約
火災保険には、入居者にも加入してもらう必要があります。
さらに、その際に特約もつけておけば、入居者の家財のみならず、アパートの再建費用なども補償されるのです。
ここでは、入居者向けの特約について説明します。
3.1 借家人賠償責任特約
入居者には、万が一アパートへの損害賠償責任を負った場合に備えて、“借家人賠償責任特約”に加入してもらいましょう。
借家人賠償責任特約とは、事故によって借りている物件に損害が生じた場合に、家主に対して支払う修理費用や賠償費用などを補償してくれる特約です。
例を挙げると、入居者の料理中の失火で、キッチン全体のリフォームが必要になった場合などがあります。
3.2 個人賠償責任特約
“個人賠償責任特約”とは、日常生活で発生した事故による損害が補償される特約で、こちらも入居者に加入してもらうべき特約といえます。
たとえば、水漏れで階下の部屋に損害を与え、修繕費用が必要になったケースなどが当てはまります。
4. 大家が火災保険に加入することの利点
大家が火災保険に加入するメリットは、“万が一のリスクに備えられる”という点です。
火災保険に加入しておけば、火災や風災、水災などで損害を被った際に、復旧・修繕などにかかる費用が補償されます。
加入してない場合は、自己資金を使用することになり、不動産運営で金銭的な損失が生じたときに対処できなくなってしまいます。
また、大家が火災保険に加入していることは、入居者にとっては安心材料の一つです。
物件の基本的な条件に差異がなければ、補償内容が手厚い物件のほうが、選ばれる可能性は高くなるといえるでしょう。
5. 火災保険の保険料の目安
火災保険の保険料は、さまざまな条件によって決まります。
以下に主な要素をまとめたので、まずはこちらをご覧ください。
火災保険の保険料が決まる主な要素
- 建物の構造
- 築年数
- 戸数や延床面積
- 立地
- 家賃収入
- 契約期間
- 付加する特約
このように、細かい要素によって決まるため、一概に平均値を出すことは困難ですが、少しでも参考になる目安は知っておきたいところですよね。
そこで、大家が入るべき特約に加入した場合に想定される、保険料の相場を以下にまとめました。
大家向け火災保険の保険料額の目安
内容 | 1年間にかかる保険料額 |
基本金額 | 5万~10万円 |
施設賠償責任特約 | 合計35万円前後 |
家賃収入特約 | |
家主費用特約 | 1万円程度 |
合計 | 約75万~85万円 |
特約を付加しなければ、保険料は安く抑えることができますが、万が一を考慮すると付加しない手はないので、基本的にはこれだけかかるものと想定しておきましょう。
6. 火災保険の選び方のポイント
ここでは、大家が火災保険を選ぶ際のポイントを解説します。
6.1 補償範囲で選ぶ
火災保険を選ぶ際は、補償範囲を考慮しましょう。
火災保険でいうところの補償範囲とは、損害の原因を指します。
つまり、火災のみならず、そのほかの事故や災害にどこまで対応してくれるのかが重要ということです。
以下に、火災保険の代表的な補償範囲をまとめたので、参考にしてみてください。
火災保険の補償範囲
補償範囲 | 補償内容 |
火災、落雷、破裂、爆発 | 失火、放火、落雷が原因による火災や、ガス漏れによる破裂事故、爆発事故の損害 |
風災、雹災(ひょうさい)、雪災 | 台風や豪雪などで発生した損害 |
水災 | 台風や集中豪雨などが原因による、洪水で発生した損害 |
外部からの衝突 | 飛来物など、外部からの衝突による損害 |
暴力行為 | 建物への破壊行為による損害 |
盗難 | 建物の備品の盗難、家財の盗難などの損害 |
保険によっては、特定の災害を選択から除去できる場合もあります。
降雪が少ない地域では、雪災害の項目を外すといったように、必要のない項目を外せば、それだけ保険料も下がります。
基本的な補償範囲と、除外できる項目は保険によって差があるため、ご自身が住む地域の気候や過去の災害事例を考慮し、確認しておくことが大切です。
6.2 地震保険を付帯する
火災保険には、地震保険を付帯することをおすすめします。
実は、火災保険には、自然災害のなかでも地震を原因とした被害の補償は含まれていません。
そこで必要になるのが、地震保険というわけです。
地震保険とは、通常の火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする損害を補償する保険です。
日本は地震が多いため、地震による火災は常に想定しておいたほうがよいでしょう。
なお、地震保険は、地震保険法により、単独では加入ができません。
「火災保険とセットで加入することになっている」と覚えておいてください。
6.3 保険期間と支払い方法を考慮する
火災保険を選ぶ際は、保険料を考慮しながら保険期間と支払い方法を決めましょう。
火災保険は、保険期間が長いほど保険料が割安になるように設定されているので、1年ごとの更新よりも長期契約のほうが、トータルで見れば経済的です。
また、保険期間とあわせて検討したいのが、支払い方法です。
保険料は、短期間よりも長期間、月払いよりも一括払いのほうが安く抑えられる傾向にあります。
ご自身の資金で賄える範囲で、保険期間と支払い方法を選択するとよいでしょう。
7. 火災保険に関する注意点
火災保険に加入する際には、これまでに述べた内容以外の注意点がいくつかあります。
加入する直前になって慌てないように、事前に把握しておきましょう。
7.1 所在地によって保険料は変わる
火災保険の保険料は、立地によって変動します。
地域によって自然災害の発生率や、損害状況の予測結果は異なります。
そして、自然災害の発生率が高い地域は、火災保険の補償が生じることも多くなるため、必然的に保険料が高くなるのです。
たとえば、台風や大雪によって被害が出ている場所や、崖崩れや洪水が起きやすい場所などは、災害による被害が生じる可能性が高いため、保険料が高くなる傾向があります。
7.2 構造の違いでも保険料は変わる
保険料は、建物の構造によっても変わります。
なぜなら、建物の構造の違いから、被害の大小に差が生じるためです。
たとえば、木造のような、火災時に燃え広がりやすい建物より、コンクリート造のような燃えにくい建物のほうが保険料は低くなります。
なお、建物構造は3種類に分けられ、それぞれ保険料が異なります。
以下に、建物構造の種類を表にまとめたので参考にしてみてください。
構造級別の建物
建物構造 | 内容 |
M構造 | コンクリート造の建物 |
T構造 | 鉄骨造の戸建て |
H構造 | 木造の戸建て |
保険料は、構造別にM構造→T構造→H構造の順に高くなる仕組みです。
保険に加入する際は、この構造による保険料の差異も把握しておいたほうがよいでしょう。
8. 賃貸の大家も火災保険に加入して火災や災害などのリスクに備えよう
この記事では、アパート経営を行う際に、大家が加入すべき火災保険について詳しく解説しました。
火災保険に入っておけば、火災や災害などで損害を被った際に補償を受けて、賃貸経営を継続させることができます。
また、付帯する特約の種類や、ご自身の居住する地域、建物の種類によって、火災保険の内容は変わってくる点も頭に入れておいてください。
本記事の内容を参考に、万が一のリスクにも万全に備えた、健全なアパート経営を行いましょう。
株式会社マリモは、豊富な経験と知識から、火災保険についてのご相談に応じます。
アパート経営が初めての方でも、全力でサポートしますので、ぜひ気軽にご相談ください。
この記事の監修
マリモ賃貸住宅事業部
不動産事業を50年以上続けてきたマリモが、お客様目線でお役に立つ情報をお届けしています。不動産投資初心者の方に向けての基礎知識から、経験者やオーナー様向けのお役立ち情報まで、幅広い情報の発信を心がけています。部内の資格保有者(宅地建物取引士、一級建築士、一級施工管理技士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者など)が記事を監修し、正しく新鮮な情報提供を心がけています。
この記事を読んだ人におすすめ
-
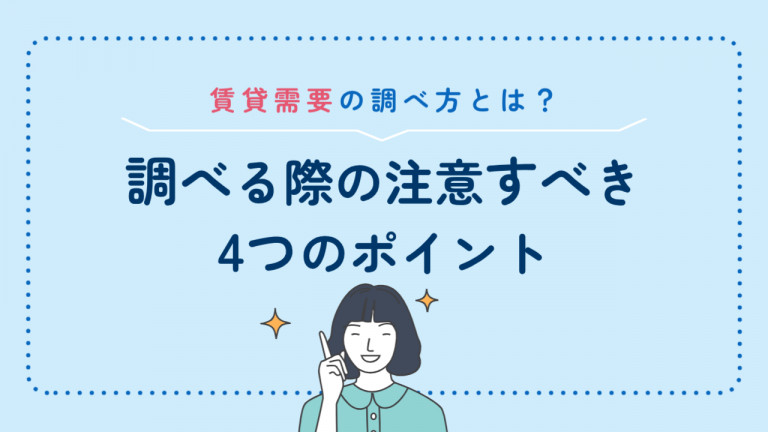
25.01.27
賃貸需要の調べ方とは? 調べるときに注意すべき4つのポイント
賃貸物件の経営をする際に欠かせないのが「賃貸需要」の把握です。 賃貸需要、別名賃貸ニーズともいいますが、賃貸需要を知っておけば、経営に失敗することがありません。 自分で調べることもできますし、仲介管理会社にヒアリングして調査することもできるなど、様々な調査方法があります。 本記事では賃貸需要とは?をはじめ、賃貸需要の調査方法や調べるときの注意点について詳しく紹介します。 これから賃貸経営をしようと思っている方や検討中の方はぜひ参考にしてみてくださいね。
-
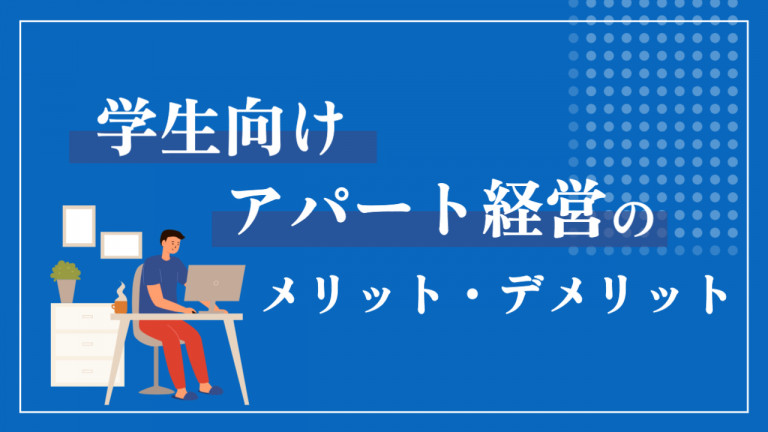
24.06.26
学生向けアパート経営のメリット・デメリット
学生向けアパートは、その名の通り、学生を入居者の対象とした物件です。そのため入退去の時期の目途が立ちやすいため、管理しやすいメリットがあります。 一方でキャンパス自体の移転や少子化による、そもそもの子どもの数の減少は、学生向けアパートを経営する上で大きなデメリットでもあります。 メリット・デメリットそれぞれの側面を持つ学生向けアパート経営ですが、本記事ではその詳しいメリット・デメリットをご紹介します。 メリットをできるだけ最大化し、安定した経営を目指しましょう。
-
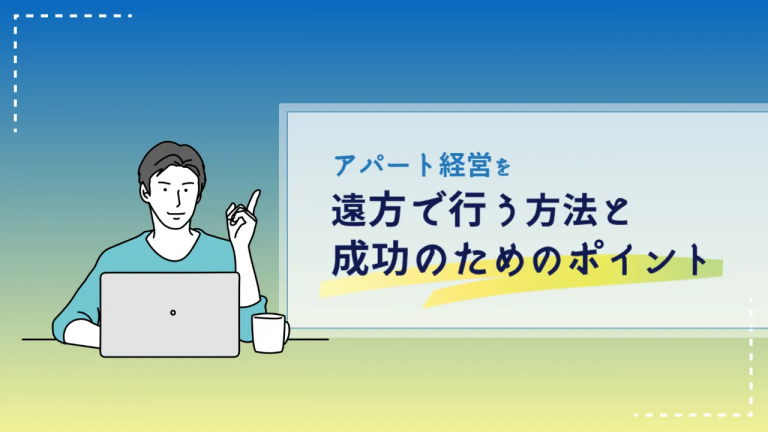
24.06.26
アパート経営を遠方で行う方法と成功のためのポイント
アパート経営は、自宅の近くや住み慣れたエリアに限らず遠くでも行えます。遠方に不動産を所有している場合も同様に、所有する土地や建物を活かして新たな収入源にすることができます。 新たに遠くの土地でアパート経営をする場合、どの程度離れた場所にするのか・地域に土地勘があるか・アパートの購入または新規建築のどちらを選ぶかなどを考えながら検討していきますが、遠方で不動産投資を行うメリットとデメリットも押さえておきましょう。 ここでは、遠方の物件でアパート経営を行う方法について順番に紹介し、気になるメリット・デメリットと成功のためのコツをお伝えします。アパート経営を遠くの土地で行う予定がある方は、ぜひ参考にしてください。





